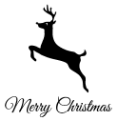
みんなと過ごすクリスマス
※このお話は『たしかに恋をしていた』の番外編です。
「あっ、お疲れさま!」
遠くから手を振る小さな人影が見えて、サボの心は温められていくのと同時に小さな不安も芽生えた。今日は仕事を早く終わらせて大事な人が待つ家へまっしぐら。途中で買い物を済ませた間に雪がちらつきはじめ、サボが帰宅する頃にはかなりの量が降っていた。
「フレイヤ、お前なんで外で待ってるんだ。中にいろって言っただろ?」
「早く帰れるって聞いて待ちきれなかったから……ダメだった?」
防寒対策なのか、暖かそうなコートに帽子と手袋とマフラーを装備したフレイヤが首をかしげる。寒さで身を縮める姿はいつにも増して小動物感がにじみ出ていて余計に心配になった。
――全然ダメなんかじゃねェけど。嬉しいしかわいいし。いや、ダメだろ。
自身の心が忙しなく葛藤し、けれど最終的には彼女の体のほうが心配だという結論に至る。
「そりゃ嬉しいけど、鼻を赤くして震える姿を見るこっちの気持ちも考えてくれ。心配になる」と、彼女の鼻を軽く摘まんだ。どのくらい外にいたのか知らないが、赤くなった鼻が数分程度ではないことを物語っていた。
「……ごめんね」
「もういいよ、寒い中ありがとう」
「うん。おかえりなさい」
かわいらしいリップ音とともに、頬に冷たい感触が伝わる。仕事から帰ってきたサボに、フレイヤが必ずしてくれることだ。革命軍にいたときからの名残だったが、ここへ移り住んでからも変わらず(というかサボがねだるせいで)彼女は健気に応えてくれている。
セント・ヴィーナス島に移住してから二年目の冬。港町の中心地からはずれた丘の上に建てた家は、二人暮らしするには少し広いが、この先家族が増えたらちょうどいい大きさで彼女の店からも近い場所に位置する。
今日がクリスマスという宗教的なイベント日だと聞いたのは昨年のことだ。昔聞いたハロウィンという文化に珍しさを覚えた記憶があるが、クリスマスというのもまたこの島の文化だと教えてくれた。この日は誰もが早めに帰宅して家族とともに過ごすのが通例だというから、いつもより長く彼女と一緒にいられるというわけだ。
こうして心躍りながら帰宅したサボが玄関の扉を開けたとき、しかしパーンという耳をつんざく音が聞こえて「うわっ」と後ずさって何事か瞬時に確認する。後ろにいたフレイヤをとっさにかばってしまうのは、昔からの習性だ。
しかし辺りを見回しても不審な人間はいないし、物音も最初の一度きりで家の中の様子は朝に見たときと変わっていなかった。どういうことだ……?
「相変わらず仲良くて羨ましいです。かわいい奥さんが出迎えてくれるって最高ですね」
「お邪魔してます総長。あ、もう総長じゃないか……」
「なんでしたっけ、メリークリスマス?」
次々に飛んできた騒がしい声に、サボは文字通り目を丸くさせて呆気にとられた。ソファからひょっこり顔を出して現れたのは、サボがまだ革命軍としてあちこち飛び回っていた頃の部下たちだった。
あまりに突然すぎて懐かしさを覚えるでもなく、「……なんでお前らがいるんだ」開口一番に文句が出た。
「そんな不機嫌そうにしないでください。おれ達が言い出したわけじゃないんすからね」
「実はコアラさんもハックさんも一緒です」
「……あいつらも来てるのか」
「二人がどんなふうに過ごしてるか気になるし、二年目だからそろそろお邪魔してもいいよねってコアラさんが言い出して、数週間前にフレイヤさんに連絡したそうです」
矛先がフレイヤに向く。
「あ、黙っててごめんね。コアラちゃんが"サボ君を驚かせたいから言わないで"って口止めされたの」
フレイヤが取り繕うように言ったが、実際は違うことが手に取るようにわかる。どうせこっちに伝わったら「来るな邪魔するな」と一蹴されると思ったからに違いない。そしてコアラの推測は間違っていないだけに、サボは悔しい思いで「そういうことか」と嘆息した。
「コアラちゃんクリスマスを見てみたいって楽しそうにしてたし、久しぶりに皆さんに会えるのもいいなって思って。革命軍は家族みたいなものでしょう?」
曇りのない目がサボを見つめてくる。そんなふうに言われたら断る理由が一切なくなる。結局フレイヤが楽しくしているならなんだってよかったし、コアラ達を懐かしく思うのはサボも同じだった。
根負けしたというほどでもないが、純粋な瞳に「そうだな」と頷いてから、
「で? 肝心のコアラの姿が見えねェが」家の中を見回す。
「ハックさんと観光してるよ。吹雪いてきたし、そろそろ戻ってくると思うからサボは皆さんと積もる話があるでしょう? 座って待ってて」
言ってからフレイヤはぱたぱたと早足でキッチンに向かっていった。
その後ろ姿を見ながら特別な料理を作ると朝から張りきっていたのを思い出す。やけに意気込んでいると思えば、客人が来ると知っていたからだと納得した。浮足立って部屋の飾りつけをしていた姿が思い出されて、思わずサボの頬が緩む。
ふいに視線を感じてソファに顔を向けると、こちらを見ながらニヤニヤする部下と目が合ってばつが悪い。
「あ、別に何も思ってませんよ。すげー好きなんだなー程度です」
「……」
「というかフレイヤさんって相変わらず優しいですね。ほかの人にもあんな感じなんですか」
「そんなわけねェだろ。おれが許すか」
「あーその感じ懐かしい。小さなことですぐ嫉妬してましたね」
「それから周りには笑顔で牽制したり……」
「そもそも総長の恋人だとわかってて手を出す人なんかいませんって」
好き勝手に自分とフレイヤの話で盛り上がる彼らを見ていると、ふとあの頃に戻ったような錯覚を起こす。まだ世界は混乱の中にあって、それでもフレイヤや彼らと何気ない会話をしているときは平和で心が休まるひと時だった。今の生活は二人きりだが、仲間がいることで簡単にサボの記憶はあの頃に引き戻される。
ゆっくりと懐かしい光景が次々に脳内で再生されていき、自然と話はお互いの近況のことになる。現在も本部で生活している者もいれば、家族の元へ戻った者もいるそうだ。
そうして昔話を織り交ぜながら盛り上がっている中、扉をノックする音とコアラの声が室内に届いた。
「サボ〜私いま手が離せないから開けてくれる? あ、文句は言っちゃダメだからね」
「わかってるって」
口止めしたことをまだ根に持ってるとでも思ってるのか、フレイヤが釘をさしてくる。少し面白くないと思っているのは事実だが、確かに久しぶりに大勢で過ごすのも悪くない。それに彼女とは仲間が帰ったあともずっと一緒にいられるのだから、ここで目くじらを立てる必要はなかった。
サボは玄関まで移動して扉を開けると、寒さで身を震わせている二人を出迎えた。