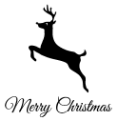
パーティーのその後
※このお話は『たしかに恋をしていた』の番外編です。
クリスマス当日は案の定賑やかな場となった。ハロウィン同様、彩られた中庭に豪華な料理と酒――と、今回はプレゼント。保護施設の子どもたちが来ると決まって騒がしくなるが、それもまた部下の言う"平和の象徴"というやつだろう。サボも宴は嫌いではない。ただ一点を覗いては。
サンタクロースという赤と白を基調とした不思議な格好をすることになった自分とフレイヤは、パーティーの間中ずっと異なる装いで過ごしていた。ところが、彼女のスカートの丈がやけに短く、普段隠れている膝から下が周囲に晒されていたのでサボの機嫌はすこぶる悪い。子どもたちへプレゼントを配り終えてそのまま部屋へ直行したものの、ソファから動かずにじっと床を睨みつけている。自分に見せたいと思ったと言われたが、それなら二人きりのときだけでいいのにと思わなくもない。
「ねえ機嫌直して。サボにもプレゼント用意してあるんだよ」
そんな自分にしびれを切らしたフレイヤが隣に座って近寄ってくる。サンタ服から普段着になった彼女の足はもう無防備に晒されていない。布できちんと隠されていた。いや、逆だろ。おれと二人でいるときに着るべきだ――という悪態を胸中でついてから、彼女のほうに顔を向ける。
「……悪くねェ」
あからさまな態度をとっておいて「悪くない」とはどの口が言っているのか。フレイヤも隣でため息をつく。
「この前からサボは子どもみたいだね……仕方ないな」とクスっと笑みをこぼした彼女が立ち上がり、一度ソファから離れてテーブルのほうに向かった。その上には折りたたんである子どもたちへ配ったプレゼントを入れていた袋のほかに、もう一つ小さな紙袋が置いてあった。そこから何かを取り出した彼女は、ぱたぱたと駆け足でこっちに戻ってくる。
「メリークリスマス、サボ」
「え」
「言ったでしょう? サボにもプレゼントがあるって。一か月半くらいかけて編んだの」
魔法の言葉のように紡いだ「メリークリスマス」のあと、フレイヤが持っていた何かをサボの首に巻きつけたので、感触を確かめるべくそれに手をかける。目線を真下に向けてモノの正体を確認した。
手触りの良いそれは、薄いグレーのマフラーだった。シンプルに一色だけだが、よく見ると表面が隆起していて面白い編み目だ。「編んだ」ということは手作りなのだろう。
「……おれの、ために?」
「もちろん。内緒で編むの大変だったよ」
そうこぼしたフレイヤが再びソファに腰かけてこちらに歩み寄る。こんな感じかな、と綺麗に巻き直してくれた。肌に触れる面積は少ないが、心は妙なくすぐったさを覚える。
「なら、通信部の仕事が忙しいってのは――」
「あ、それはごめんね。先輩たちにも話を合わせてもらって忙しいってことにしといてもらったの」
「……」
その話を聞いて、いろいろなことが繋がっていった。
連日残って仕事をしていたこと、かと思えば急に「大丈夫になった」と言って部屋に来たこと、部下がフレイヤの忙しさに対して「メニューの考案もやっている」などと話をふってきたこと。すべて自分に気づかれないようにするためだったのだ。
手編みなんていう健気な方法をとってプライベートの時間を削り、夜な夜な自分を想ってマフラーを編む彼女の姿を想像したら急に胸が軋む音がした。一か月半とか言ってたな。結構な期間だ。
「フレイヤ」
「ん〜?」
「ありがとう。すげェ嬉しい」
言葉とともにフレイヤの身体を力強く抱き寄せた。マフラーが彼女の顎あたりにも触れる。犬や猫がそうするように、サボは彼女の頬にすり寄って体をより一層密着させた。くすぐったいと身をよじる彼女が、けれどとても嬉しそうで楽しそうなので構うことなく続ける。
「ふふ、機嫌直ってよかった。せっかくのクリスマスだもん、気持ちよく終わりたいよ」
髪を撫でられて、いつかの――犬耳が生えてしまったときのことを思い出す。気分は高揚し、さっきまでのモヤモヤとした気持ちがすでにどこかへ吹き飛んでいたサボは、可愛すぎる目の前の彼女を食べたい衝動に駆られた。
「じゃあ気持ちよくなれることするか」フレイヤの体を持ち上げて自身の股の間に収める。直後、かあっと頬を染めた彼女が「そういう意味じゃないよッ……! えっち!」とサボの体を押しやったが、弱々しい抵抗は無駄に終わる。そんな小せェ力じゃ自分はびくともしない。
「マフラーはもちろん嬉しいけど、サンタ服に関しては許してねェ。……ベティに簡単に触らせやがって」
「んッ」
項に唇をあてがう。腰を掴んで逃げられないようにしてから何度もそこに吸いついた。
「前にも言ったろ? フレイヤに下心がある奴は女だろうとダメだって」
「でも……下心があるってどうやって判断するの」
「おれにはわかるんだよ。そいつらと同じだから」
こういうのは態度でわかるものだ。なぜなら、自分もフレイヤをそういう目で見ているから。同類だから匂いを嗅ぎ分けられるという訳だが、まあ彼女に詳しく説明する必要はないだろう。案の定、こちらの返しによくわからないといった顔をしている。
「ともかく、お前に何してもいいのはおれだけだ。わかったか?」
「……何してもいいとは言ってない」
「細けェことはいい。もうこっちに集中しろ」
これ以上話すことはないと会話を断ち切って、服の上から胸に触れる。形を楽しむ程度の手つきだが、敏感になったフレイヤの身体はたちまち小さく震えて可愛らしい反応を見せた。
パーティーの喧騒から離れて、とても穏やかな聖なる夜だった。巻かれたままだったマフラーを一度ほどいてソファの肘掛け部分に置く。くるりとフレイヤの身体を反転させ向かい合うように抱え直したサボは、甘ったるい吐息をこぼしてその気になりはじめた彼女の唇に文字通り噛みついた。