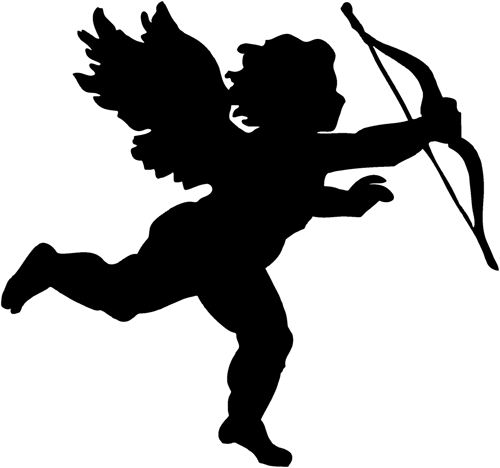
幸せはいつもすぐそばにある
※『たしかに恋をしていた』の番外編
立ち寄った大きな港町へ、サボはフレイヤと買い物に繰り出していた。食糧などの物資を調達するため、帰還中にちょうどいい島があることがわかり、休憩をかねて一日ほど滞在することになったのだ。
珍しくフレイヤも任務同行していたので、サボは彼女をデートに誘って朝から景色のいい港町を歩いている。コアラから頼まれた買い物リストと照らし合わせながら、次々に必要なものを見つけていく彼女を見て、さすがこういうことは慣れているなと思いつつ、完全に荷物持ち状態になっている自分が近い将来こうなるのではないかと妙に納得がいって、思わず笑みがこぼれた。
何か催しでもやっているのか、通りに沿って露店がずらりと並んでいた。アクセサリーやちょっとした置物などの雑貨のほか、肉や野菜、パンといった食品の店も多い。中には呉服なんかも出ている。人通りが多いせいで、小さいフレイヤがはぐれてしまいそうに感じたサボは両手の荷物を片手で持ち、空いた左手で彼女の手を握った。
「こうしておけば大丈夫だな」
ぽかんとしたフレイヤは、けれどすぐに笑顔になって「ありがとう」と答えた。嬉しそうにぎゅっと握り返してきた小さな力が愛おしくて自然とサボの頬は緩む。そしてこちらのもう片方の手に視線を向けて、「荷物持ちさせちゃってごめんね」申し訳なさそうにフレイヤが眉尻を下げた。
「気にしなくていいよ。これくらいどうってことねェし」
「でもあとは薬屋で薬草を調達するだけだからそんなに重くならないはず」
「よし、じゃあさっさと済ませてメシにしよう」
意気込んでフレイヤの手を引き、薬屋があるという町の西側へ向かうべく時計台のほうへ歩き出したときだった。
「ママ!」
突然横から何かが飛び出してきたかと思うと、自分の腰ほどしかない少年がフレイヤの腰に飛びついてきた。その勢いに驚いた彼女がたたらを踏んで堪えようとしたが、「きゃっ……」少年の勢いに負けて地面に尻をついてしまった。
「大丈夫かッ」
慌てて駆け寄り怪我がないか確認する。幸い、どこも怪我している様子はなく無事だったのでほっと安堵したのも束の間、いまだにフレイヤの腰に抱きついたまま離れない少年にサボは眉をひそめた。
十歳にも満たなそうな黒髪の彼は、聞き間違いでなければ先ほどフレイヤのことを”ママ”と呼んでいたが、彼女を母親と認識しているなら勘違いだと教えてやらなければならない。
「おい。いつまでくっついてる気だ」
「ちょっと待ってサボ。もしかしたら迷子かもしれないよ」
ボク、どうしたの?と少年を抱き起こしたフレイヤがやさしい声音で聞いた。
その声に反応した少年は大きな目をぱっと開き、目の前の彼女をしばしば見つめると「ママじゃない……」とあからさまに落胆して涙目になった。ようやく間違いであることに気づいたようだが、今度は母親とはぐれたという問題にぶち当たる。
しかし、フレイヤは動じる様子がなくいたって冷静に「ボク、お名前言える?」と質問していた。
「リト。ろく、さい」
「リトくん。ママは?」
「……さっきまでいっしょに、あかときいろとおれんじのひと、みてた」
でもいなくなった。
悲しそうに目が伏せられる。拙い言い方で少年は説明してくれたが、「赤と黄色とオレンジの人」とは一体なにを表しているのかさっぱりだ。
なんだそりゃと呆れるサボとは正反対に、フレイヤのほうは何か思い当たる節でもあるのか表情が明るい。
「お前、何かわかってるのか?」一人答えにたどり着いていそうな彼女に問いかける。
「きっと、あれのことだよ」
そう言ってフレイヤが指をさしたのは、自分達の行く先にある時計台の広場だった。何やら人だかりができているのが目に入り、よく見ればその中心には蛍光色の派手な髪にカラフルな化粧を施した人間が滑稽な動作をしていた。
なるほど。あれは俗に言うピエロと呼ばれる道化を演じて人々を笑わせる存在だ。確かに赤と黄色とオレンジで埋め尽くされた格好をしているので、少年の言うことは間違っていない。母親と一緒に見ている途中で、人の波にのまれて押し出されたのだろうか。あの様子じゃ子どもが迷子になっても仕方ない。
「リトくん、一緒にママを探そうか。私とこのお兄さんが手伝うよ」と、フレイヤがこっちに目線を投げてきたので瞠目する。
「……」
勝手に迷子の母親探しに参加させられることになったが、フレイヤ一人に任せるのも気が引けるので仕方なく「わかったよ」とサボはせっかくのデートを中断して、母親探しに付き合うことにした。
*
人間が自分ではない誰かに対して好意を抱くのは果たして何歳あたりなのだろう。それも親や友人に対する愛情ではなく、性的な意味で相手を認識したときに起こり得る感情のほうだ。少なくともサボは、出会ったときからフレイヤに対してそういう意味で好きなので(好きという特別な感情を理解したのはあとのことだが)、四歳ということになる。
六歳の少年リトの母親探しを開始してから一時間。広場に母親らしき人物の姿はなく、結局町中を探索する羽目になったサボ達は、露店が立ち並ぶ大通りを歩いていた。薬屋からだいぶ離れてしまうことになるが、目的の人物が見つかるまでは仕方ない。
それよりもサボには気になることがあり、今この瞬間も許し難い状況に唇をとがらせていた。
「フレイヤちゃん。ぼく、ジュースがのみたい」
「ジュース? じゃあさっきの果実屋さんで作ってもらえそうだから戻ろうか」
「わーい! ありがとう」
リトがフレイヤの胸に顔をうめて嬉しそうにする。子どもが純粋に喜んでいると思えたら楽だが、こいつはすでに三回目なので確信犯に違いなかった。確実にフレイヤをそういう目で見ている。
「おいリト。くっつくなって言っただろ」
「サボにはいってない。フレイヤちゃんがいいよっていったんだ」
リトの口調は明らかにこちらを敵視している言い方で、先ほどからサボに対してどこか攻撃的というかフレイヤへの態度と違いすぎる。
疲れたとこぼしたリトに、親切にも背負おうとしたサボを跳ね除けた少年はあろうことかフレイヤに抱っこを強請った。いくら六歳といっても彼女の小さい体には酷だろうと思ったのだが、意外にも彼女はリトを容易く抱えて歩き出したのでこちらが拍子抜けしたほどだ。
フレイヤが母親に似ているから甘えていることは百歩譲っていいとして、こうもベタベタされるといくら子どもとはいえ、下心があるとしか思えなくて腹が立ってくる。こうしてサボがやきもきしている間もリトの行為は止まらない。
だから、なんで胸に顔をくっつけんだよ。そこはおれの――
「あ、果実屋さん発見。リトくん何にする?」
と、フレイヤが一旦足を止めてリトを下ろしてから、左側に並ぶ露店に向かっていく。
サボも後からそれに続くが機嫌はすこぶる悪い。おまけに荷物があるせいで歩きづらさも相まって、最初の浮かれたデート気分はどこかへ吹っ飛んでいた。
果実屋にたどり着いた途端、リトが興奮したように「これ!」と黄緑色の粒がたくさん集まった果物を手に取った。この店ではどうやら好きな果物をその場でジュースにしてくれるらしい。砂糖などを使うことなく、いわゆる果汁百パーセントだ。果実そのものを味わえることがウリだという。
いらっしゃいと店主の快活な声に軽く返してから、サボもどんなフルーツがあるのか並べられたカラフルな固体に視線を向けた。
「ゴールデンマスカットだね。サボは?」
「……へ?」
「疲れたでしょう? 買い出しのお金とは別にちょっと多めに持ってきたの」
小さな財布を取り出してみせたフレイヤはどうやらリトだけではなく、サボの分まで買うつもりがあるらしい。思ってもみない施しに少しだけ気分が上昇する。
「ずっと荷物持ってもらっちゃってごめんね」耳打ちされてくすぐったさを覚えるのとは別に、彼女が自分にまで気を配ってくれていることに心を打たれたサボは一瞬言葉に詰まって返事ができなかった。
ぼうっと彼女に見惚れている隙に、足元のリトがボトムを引っ張って「ジャマだ」とか何とか言ってくるがもはや気にならない。
しかし当の本人であるフレイヤはこちらを気にしたふうもなくフルーツ選びに夢中になっていた。自分の分も忘れずに買うようだった。
「良い奥さんだねえ。大事にしなよ」
と、向かいから声をかけられる。店主は四十代くらいのおっさんだった。ニコニコと人の好い笑みを浮かべて、微笑ましそうにこちらを見ていた。
どうやらフレイヤとのやり取りを聞かれていたらしいが、彼の発言には一点誤りがある。正確に言えば、彼女はまだ奥さんではない。今後確実にそうなると誓ってもいいが。
「あっ、いえ……私と彼は――」
「だろ? おっさん見る目あるな、おれの奥さんは世界一良い女だ」フレイヤが否定しかけたのを遮って答えた。こちらの返しに店主はぽかんと目を丸くさせたが、やがて我に返ったようにガハハと豪快に笑った。
「いいねえ兄ちゃん。見事な惚気っぷりだ、そういうの嫌いじゃねェぜ。気に入った! 子どもの分はタダにしてやるよ」
「お、気前がいいな。ありがとう」
サボは礼を言った。気にすんなと答えた店主は鼻歌を歌いはじめたかと思うと、棚に置かれたゴールデンマスカットを一房手に取り、専用の機械に入れて作りはじめた。
本当にこの場で生のジュースを作るらしい。珍しい工程だなと眺めつつ、自分は何のフルーツにするか悩む。無難に知っている定番の味でもいいが、どうせならこの地域にしかないフルーツのほうがいいだろうか。
「ちょっとサボ。どうして夫婦なんて嘘ついたの……?」
横からコソコソと話しかけられて、サボは声のするほうに顔を向ける。そこには頬を染めて恥ずかしそうにするフレイヤがいた。先ほどの答えが気になるらしく、どうしてかと訳を聞きたがった。
「説明しなきゃわからねェか?」
「えっ?」質問で返されるとは思っていなかったフレイヤがきょとんとした顔をする。
「だからさ。説明しなくてもわかるだろ?」
彼女の肩を抱き寄せて耳打ちし返した。赤い頬がさらに赤く染まり、わたわたと慌てはじめる。きちんと伝わったらしいこちらの想いに、サボは高らかに笑った。
その間にマスカットのジュースが出来上がり、リトが受け取るのを見守る。結局、フレイヤがりんごジュースにするというのでサボも同じものを頼むことにした。
*
「おい」
ジュースを飲みながらリトの母親探しを再開したサボは、目線よりはるか下で声をかけられて「なんだ」と答えた。リトの不服そうな顔が目に入る。
「サボはフレイヤちゃんの"おっと"なのか……?」
何を聞かれるのかと思えば、六歳のくせに夫なんて単語を知ってるのかと呆れる。薄々感じていたが、生意気にもこの六歳児はやはりフレイヤに気があるらしい。まったく、リュカといい六歳のガキにまで好意を持たれるとは末恐ろしい。
サボはひと呼吸ついてからリトの肩に手を乗せた。
「いいかリト。フレイヤはおれの女だ。お前の言う"おっと"と同義……あーつまり、おれとフレイヤは愛し合ってる関係で――」
「でも"けっこん"はしてないんだろ? だったらぼくもフレイヤちゃんの"おっと"になれるかもしれないじゃん」
「なれねェよ」
大人げない強い言い方になってしまったがこの際仕方ない。男同士の戦いである。
むうっと頬を膨らませたリトはこちらを睨みつけて「なんでだよ」と抗議してきた。説明するのが面倒になってきたサボは、いっそのこと「フレイヤがリトを好きになることは絶対にない」とはっきり伝えたほうがいいのではないかと思ったが、さすがにそこまで言うのは六歳のガキに酷かもしれない。
すぐそばで様子を見ていたフレイヤが困ったように考える素振りを見せていた。彼女ならリトを傷つけない言葉を知っているだろうか。しばらく待っていると、ゆっくり彼女がリトの前に歩み寄っていく。
「リトくん、ありがとう。君の気持ちはとても嬉しい」その言葉にぱっと明るい表情を見せたが、「でもね」フレイヤの言葉に続きがあるとわかると、しゅんとして目を伏せてしまった。
「私とサボは、結婚はしてないんだけどいずれする予定があって。その……リトくんの言う"おっと"なんだ。未来のね」
未来の。リトがはたしてどこまで理解できたのかはわからなかったが、眉を下げて寂しそうにしているあたりなんとなく察したのかもしれない。
リュカのときと同様、フレイヤは遠回しな言い方をすることなくストレートに自身の気持ちを伝えた。子どもだからと優しい言葉で傷つけないように言うこともできるはずだが、あえてそれを選ばない。しかし、それが彼女なりの優しさなのかもしれない。
「フレイヤちゃんは……サボがすき?」
リトが俯いていた顔を上げて尋ねる。はっきり言われたことでショックを受けていることは明らかだった。しかし、変に期待を持たせる答え方をするほうが酷だ。自分達はずっとここにいるわけではないのだから。
そもそもフレイヤを好きになったのも母親に似ているという理由だろうし、この先いろいろな世界を経験するたびに出会いはたくさんあるだろう。それこそサボが彼女と出会ったように、この少年にも運命的な出会いが待っているかもしれない。
「うん、大好き」
フレイヤがリトの目を見て、とびきりの笑顔で答えた。本人が聞いているのも構わず、彼女は堂々と「大好き」と発言する。わかりきっていることだとしてもはっきり言葉にして言われるとこみ上げるものがある。リトはやはりどこか寂しそうな表情を見せたが、しばらくすると「ふーん」と納得したのかそうでないのか曖昧な相槌を打ってフレイヤから少し距離をとった。
「そっか……」
「リト。お前は小せェくせに女を見る目はありそうだから、将来きっとフレイヤみてェな良い女を見つけられるさ」
まァ見つけたとしてもフレイヤには勝てないだろうが。と、これは胸中で続けてリトの頭を乱暴に撫でる。すかさず「やめろよッ、ばかサボ」と彼が嫌がって逃げていったので、元気そうで安心する。まったく憎まれ口までリュカにそっくりだ。
「リト〜〜」
と、反対方向からリトを呼ぶ声が聞こえる。声の先をたどると、彼の母親らしき女性が血相を変えて走ってくるのが見えた。どうやらこちらの役目は終わりのようだ。
リトも母親の姿を見つけた途端、「ママっ」と駆け寄って抱きついた。
「心配したんだから! ママの手を離しちゃダメって言ったでしょう。でも無事で本当によかったっ……」
「うん、ごめんなさい。でもサボの兄ちゃんとフレイヤお姉ちゃんがママをいっしょにさがしてくれたんだ、ジュースもくれた」
その言葉で母親はようやくサボ達の存在に気づき、慌ててぺこぺこと頭を下げはじめた。息子を見つけてくださってありがとう。なんとお礼をすればいいか。彼女が恐縮しながら訴えるのを、フレイヤが必死に顔を上げてくださいと彼女を支える。
そのとき、初めてリトの母親の顔をはっきりと見たのだが、サボは目を見開いた。確かに目元がフレイヤに似ている――ような気がする。とはいえ、自分なら絶対にフレイヤとほかの女を間違えたりしないが。
確かにこの母親だったらフレイヤを気に入るのも頷ける。子どもにはやはり親の存在が大きいのだろう、両親と確執があるサボには理解できないことだが、それが一般的なことだとは理解していた。
「本当にありがとうございました」
フレイヤと話の落としどころがついたのか、母親は最後にもう一度深々とこちらに向かって頭を下げた。リトの手をとって、仲良く町の中心へ歩いていく親子の背中を二人で見守る。もう離れるなよと念を送りながら。
と、突然リトがくるりと振り返った。彼は自分を見ている気がする。
「おいサボ。フレイヤちゃんをたいせつにしなかったらゆるさないからなッ!」
何を言うのかと思えば、振り返ってまで言うことではない。母親が焦りながらまたぺこぺこと首を垂れるので苦笑しつつも、「当たり前なこと言うな!」と返した。元気に手を振る生意気な六歳児を、サボはどこか清々しい気持ちで今度こそ見送った。
「数時間ですっかり仲良くなったねサボ」
隣で同じように親子を見送っていたフレイヤがクスクスと笑いながら言った。どう見ても仲が良いわけではなく単純に彼女を取り合いしていただけなのだが、大人げない場面もあったかもしれないと今更ながら少しだけ反省する。少しだけ。
「どこがだよ。ライバルだろ」
「当たり前って言ってくれて嬉しかった。よろしくね、未来の旦那さん」
唐突にフレイヤがこっちを見てそんなことを言うものだから心臓が馬鹿みたいに跳ねた。しかし、本気で言ったことなので何も間違っていない。サボは彼女を本気で愛しているし、幸せにしたいと心から思っている。ほかの誰でもない自分が。
最初こそ、迷子のお守りなどという面倒なことに巻き込まれて憂鬱な気持ちだったが、不思議と今は幸福感で満たされていた。サボは彼女の手をとって指を絡めると、「こちらこそ。おれの可愛い未来の奥さん」と笑って返した。