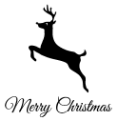
小さな愛のクリスマス(2)
今、ものすごく緊張している。
自分の心臓がばくばくとうるさい音を立て、今にも口から飛び出そうだった。
カマバッカ王国のあるモモイロ島から西に数十キロと非常に近い島に、おれはフレイヤさんと、そしてあのサボさんの三人で上陸していた。クリスマスパーティーの物資調達のために来たフレイヤさんの手伝いをするついでに、あいつと仲直りするための「本」を選ぶのがおれに課せられた仕事――というと仕方なくやっているように聞こえるが、そうじゃない。きちんと謝って、前みたいに話せるようになりたくてここへ来たのだ(あと彼女の手伝いを任されたのもちょっと誇らしい)。
まだ十二歳で体力も実力も大人たちに比べたら不足している自分は、任務には加勢できないゆえに、こうした見知らぬ島を散策するのは新鮮味があって胸が躍る。革命軍に来る前のことはあまり思い出したくないが、記憶にある限り遠出をしたことがない。近い島とはいえ、だから住んでいる場所以外を探検できるのは嬉しかった。
しかし、フレイヤさんだけでなく憧れのサボさんまで一緒だとは思わず、先ほどから会話に参加している(といっても聞かれたことに答えるだけ)とはいえぎこちなさは拭えない。それもそうだ。おれはここへ来てからずっとこの人に憧れていたんだから。
「大体フレイヤ。お前とガキ一人でどうやって全部の材料を運ぶつもりだったんだ」
「船に積めば大丈夫だと思ったから」
「時間かかるだろ。おれがいなかったら夜になっちまう。そんな時間まで帰って来なかったら心配するからやめてくれ」
サボさんが深い息を吐き出して、フレイヤさんを窘めた。その点に思い至らなかったらしい彼女は「ごめんなさい」と謝ったあとすぐに表情を明るくさせて「来てくれてありがとう」という感謝の言葉を述べた。微笑まれたサボさんはそれ以上なにも言えなくなったようで、照れくさそうに「いいよ別に」と彼女の手をさりげなくとって指を絡めたから、むずがゆくなって視線をそらした。
フレイヤさんの存在については先輩兵士たちが噂していたので、実を言うと彼女がここへ来る前から知っていた。戦争などに巻き込まれた国の人々が保護されることはよくあるし、そのまま入隊する人間や島の子どもたちが来るのも珍しくない。でもどうやら国外へ逃げた一般人ではないらしいというのを小耳に挟み、二年前に保護された”革命の灯”ロビンさんのように重要な人なのかと思ったら、気になって仕方なかった。
しかし、そのあと教えてもらった情報におれは馬鹿みたいに口をあんぐり開けて驚いた。保護されたのは、憧れの参謀総長ことサボさんの婚約者だというのだ。あの人にもそういう存在がいたのかという衝撃と、ほんの少しのショックもあった。女性には興味なさそうに見えたし、弟であるかの有名な麦わらのルフィの話ばかりする兄弟馬鹿(これは先輩が言ってた)だと思ってたのに。
とはいえ、おれもフレイヤさんの姿をこの目で見てみたいという好奇心には逆らえず、あのサボさんが夢中になる人がどんな人なのか、本ばかり読んでるあいつに聞いたことがある。「どこに行ったら会えるのか」と。
そうして、中庭で花の手入れをしているフレイヤさんを見たのが数か月前の話だ。もちろん相手には気づかれないようにこっそりとだけど。
遠目だったが、綺麗な人だった。帽子をかぶって、鼻歌を歌いながら楽しそうに水やりをする姿についうっかり見惚れていたら、「サボさんの恋人だし、そもそもあんたなんかじゃ釣り合わない」なんて偶然通りかかったあいつが白けた目を向けてきたのでその場で喧嘩になった。
そうした経緯があって一方的に知っていたフレイヤさんと初めて会話を交わしたのが、あいつに酷いことを言った二週間前のことだ。仲直りの方法として本をプレゼントするのはどうかという彼女の提案を受けて、一緒にやって来たわけである。
「早速なんだけど食材を買う前に本屋さんに寄ってもいい? 仲直りのお手伝いをしたいの」
「仲直り?」
「ね」
と、突然フレイヤさんにウインクされてどぎまぎしたおれは「う、うん……」という情けない返事しかできなかった。サボさんは事情を聞いていないのか、ただの手伝いで来ただけの少年だと思っているようだ。
あれ? おれ、本当について来てよかったのか?
急に怖くなって口の中がからからに渇く。手の汗もひどい。むしろ二人の邪魔をしているんじゃないかと思えてきたし、サボさんの視線が心なしか冷たい気がしてきた。
参謀総長として憧れていたサボさんの別の面を目の当たりにしておどおどと困っているおれを見かねたフレイヤさんがもうっと呆れてサボさんの鼻を摘まんだ。
「昨日話したでしょ。女の子と仲直りをするためにプレゼントを選びたい男の子がいるって話」
「痛っ……あーそういやそんなこと言ってたか」
鼻を押さえながらサボさんはおれに視線を戻して品定めするみたいにじろじろ見てくる。訓練中のきりっとした表情とは違い、こちらをライバル視するような鋭い視線でなんだか落ち着かない。あいつの前では強がることもあるけど、自分が彼に追いついたなどとは一ミリも思っていないし、ライバルにも及ばないだろう。そもそも同じ土俵に乗れるとも思わない。
サボさんはしばらくこっちを見ながら何かを考える素振りをみせた。何を言われるのか、さっきよりもさらに心臓の音がうるさく跳ねる。デートの邪魔をするなよ、とかかな。さすがにそれはないか。元々おれが手伝いで来ることになってたんだし。じゃあなんだろう。
しかし、サボさんが口にしたのはこちらの予想に反して意外な言葉だった。
「お前はその子が好きなのか?」
「へ?」
「喧嘩したんだろ?」
まさかの質問に素っ頓狂な声をあげたおれは、慌てて我に返ってぶんぶん首を縦に振った。ただし、これは後半の質問に対する答えであり、前半の質問の答えではない。
あいつが好きかと聞かれると、正直よくわからなかった。同い年で弱そうで、けど熱心に考古学を勉強している。楽しそうに本を読んでいる姿は結構いいと思う。訓練も少しはしてほしいと思わなくもないけど。でもあいつが弱くたって、おれが強くなればいいんだって思ってる。そしたら守ってやれるから。
そうした気持ちがサボさんの言う「好き」なのか、今のおれにはわからなかった。だから正直にそのまま伝える。
「好きっていうのかわからないけど……でも、守ってやりたいと思う――ます」
変な言葉遣いになったが、サボさんは冷やかさずにふっと表情を緩めて優しく笑った。おれが知る参謀総長と同じ仲間を想うときのそれで、ようやく気持ちも楽になった気がする。どうしてそんなことを聞いてくるのかわからなかったけど。
「今はいいんじゃねェか、それで。そのうちわかるさ」
サボさんが朗らかに言うので自然とそう思えた。彼がそのうちわかるというならそうなのだろう。「けど、好きな女を泣かせることだけはするなよ?」釘を刺すように続けた彼の表情はどこか憂いを帯びていた。もしかしてと思って、おれはこっそりサボさんだけに聞こえるよう尋ねる。
「それってサボさんも経験ある……んですか?」
耳打ちすると、サボさんは驚いた顔を見せてからばつが悪そうに笑った。「なんだ。おれとフレイヤの関係を知ってたのか」「……知らない人はほとんどいないと思います」「それもそうか」軽いやり取りを交わしあと屈んだ彼は一呼吸置いてから「おれにもフレイヤを悲しませた過去がある。だからこれからは泣かせることがないように、あいつの笑顔を守っていく」と、こっそり教えてくれた。その表情には参謀総長というより一人の男としての矜持――誇りという意味らしい、が垣間見えた。かっこいいなと思う。おれも早くこんな人になりたい。
ちらりとフレイヤさんのほうを見ると、こちらの会話は聞こえていないようでほっとする。これはたとえフレイヤさんであっても教えられない。男同士の秘密だ。けど、聞きたそうにうずうずしているのがわかってかわいい。
「なに話してたの?」
「さァな。おれとこいつの秘密だ。な?」とサボさんがこっちに尋ねてきたから勢いよく頷いた。
「うん、フレイヤさんでも教えられない」
「え〜急に仲良くなってずるいなぁ」
「拗ねるなよ」
「ちょっとどこ触ってるのっ……」
「尻」
「そういうこと言ってるんじゃない!」
「ハハ、怒るなって」
サボさんの左手がフレイヤさんの腰を抱いて、そのまま二人が歩き出したので急いでついていく。彼女は文句を言っているようでどこか楽しそうだ。ちっとも怒っている感じがしない。噂には聞いていたけど、本当に仲がいい恋人だった。サボさんに至っては、参謀総長のときのような緊張感が微塵も感じられない。
二人の仲睦まじい様子に、おれは恥ずかしくなりながらもちょっとだけ羨ましいなと思いながら本屋までの道のりを歩いた。