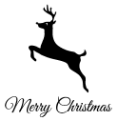
小さな愛のクリスマス(3)
十二月二十五日。
世界ではクリスマスというイベントの日らしい。といっても地域によってはまったく関係ない文化なので、わたしはここへ来るまで一切知らなかったし、何なら知ったのもつい先月のことだ。わたしの生まれ故郷では知られていないクリスマスは、だからちょっとお祭り感があって内心ワクワクしていた――はずだった。
ボサ男に「本ばっかり読んでる弱ェ奴」と馬鹿にされたのは二週間前のことだ。
いつものように食堂で黙々と読書をしていたら突然話しかけられ、しかし相手はボサ男ではなく見知らぬ年上の兵士だった。どうやらわたしが読んでいる本を自分も以前に読んだことがあるらしく、小難しい考古学の本だから誰とも感想を分かち合えないと思っていたようだ。同じ本を読んでいる同志がまさかこんな身近にいるとは思わず、すぐに意気投合したわたし達はいろいろな話で盛り上がった。
その兵士はわたしよりももっとたくさんの本を読んでいて博識だったが、最近は任務に出ることも多くなかなか読書の時間がとれないという。こうして本の話題で盛り上がり、今度おすすめを教えてほしいとも言われて内心嬉しく思っていたところに、突然ボサ男が割り込んできたのである。
何を言われたのか一瞬わからなかったが、理解したくなかっただけかもしれない。心を入れ替えて邪魔をしなくなったあいつがあんなひどいことを言うなんて思ってもみなかったから――
そのあとのことはよく覚えていないけれど、「そっちだって全然サボさんに一ミリも似てないじゃない」とかたぶんそんなようなことを言い返したと思う。
思った以上にボサ男の言葉に傷ついている、というのを一番驚いているのはわたし自身だろう。あんな猿みたいな男子、サボさんに比べたらちっともかっこよくなんかないし……。そう思うのに、結局ボサ男と仲直りできないままクリスマス当日を迎えてしまったことがこんなにも寂しいなんて思わなかった。
城の前にはクリスマス料理やデザート、そしてたくさんのお酒(しかもいつも見るものよりお洒落なグラスが使われている)がテーブルに並んでいる。みんなで一斉にスタートしたからか、今日はあまり見かけない兵士たちがわんさかと集まってすっかり盛り上がっている。頬を赤らめているところを見るに、すでにもう酔っぱらっているのかもしれない。
わたしはと言えば、テーブルの端っこでちまちまと料理を食べている。ローストビーフにミートパイ、フライドチキンにクリスマスツリー型のポテトサラダという見た目が可愛いものまであった。食べるのがもったいなくてしばらくぼうっと見つめていたけど、通りすがりの女性兵士に「あまりぼけっとしてると料理がなくなるわよ」と言われたので慌てて口に運んだ。
――美味しい。サラダってついてるけど、野菜を食べている感覚じゃないみたい。
もぐもぐとゆっくり咀嚼しながら、これを作ったであろう人物がいる方向に視線を投げた。誰が調達したのか、カマバッカ城の前には大きなクリスマスツリーがそびえたち、小さな子たちの興味の対象になっている。その中心にいるのが料理の発案者であるフレイヤさんだ。
彼女は、サボさんの恋人であり婚約者だ。ここにいる人間なら誰もが知っている事実であるがゆえに有名人。わたしも話したことこそないけれど、いつも明るくて優しくて料理が上手な女性として認識している。可愛くて元貴族だというのに気取ってなくて、憧れのロビンさんとはまた違う魅力を持った女性。
そんな彼女が作ったクリスマス料理が美味しくないわけがなく、それなのにわたしの気持ちはあいつのせいでどんよりしたままだ。
「はあ……」
ポテトサラダを飲み込んでため息をついたときだった。
「あのさ、今ちょっといいか?」といつもより少し控えめなあいつの声が背中越しに聞こえた。あの日から今日まで一切声をかけてこなかったのに、どういう風の吹き回しだろう。
あの日の言葉が刺さった棘のようにまだ心の中に残っていたわたしは、けれど無視をするのはもっと関係を悪化させると思ってひとまずボサ男に応える。
「別にいいけど」
あまり乗り気ではなかったけど、ボサ男の後ろにくっついていったんパーティーの輪から抜け出した。
*
パーティーはあっという間にお開きになって、「ここからは大人の時間だ」とかなんとか言われた十五歳以下のわたし達はパーティーの余韻を引きずったまま各々の寝床に戻っていた。ただし、みんなが不満そうに文句をこぼして城内に戻っていく中、わたしだけは気分上々で廊下をひとり歩いている。今日はクリスマスだから夜更かししても怒られないかな、と胸に抱えた物をぎゅっと抱きしめなおして部屋へと急ぐ。
現在わたしの寝る場所は保護施設から移って、兵士たちと同じ居住棟にいる。末端の女兵士三人と相部屋だが、全員わたしより年上で、任務でほとんど"西の海"にいるから実質ひとり。寂しく思いつつ、静かに読書できる利点もあってなかなか居心地がいい。
いま読んでいる本も面白いけれど、さっきもらった女性考古学者を主人公にした物語なんて初めてでワクワクする。早く部屋に戻りたくて自然と小走りになっていた。
それがいけなかったのだろう。浮ついた気持ちで角を曲がったわたしは、その方向から誰かが飛び出してくることに気づかずに思いきりぶつかり、その反動で見事尻を床に打ちつけた。
「悪い、気づかなかった。立てるか?」
「大丈夫です。わたしも歩くことに集中していなかったので――ッ!」
尻をさすりながらぶつかった相手を見上げたとき、わたしは身も凍るような思いがして言葉の続きが出てこなくなった。みっともなく口をあんぐり開けて驚いたまま、ただただその人物を見つめていた。
心配そうにこちらを見つめる双眸はわたしの知っているみんなから慕われた参謀総長そのもの。まさかこんな場所で遭遇するとは思ってもみなくて言葉が紡げない。早く何か言わないと怪しまれるというのに――こちらが内心あたふたしているのをよそに、恐れ多くもぶつかった相手、サボさんはわたしの手元をじろじろ見ていたかと思うと、「それ……」となぜか本をさして呟いた。
「……この本ですか?」
「あのガキがフレイヤと選んでた本だよな」
「え?」
「ってことは君があいつの仲直り相手なのか。なるほどな」
「えっと、」話についていけなくて困惑する。
どうやらサボさんは本の存在を知っているだけでなく、ボサ男からもらったものだということも知っているらしい。おまけにあのフレイヤさんまで関わっているというから驚きだ。一体この二週間であいつに何が起きたのだろう。
ますます混乱したわたしは困った果てにどうして知っているのか、事情を聞くことにした。
「ああごめん。この前、仲直りしたい子がいるけどどうしたらいいかわからねェってガキがフレイヤに相談したらしくて、クリスマスプレゼントを贈るのはどうかって話になったみたいなんだ」
いまいち事情を理解できていないわたしのために、サボさんは丁寧に教えてくれた。
なんでもボサ男は例のあの日にフレイヤさんと会って、わたしと喧嘩した(というより向こうがひどいことを言ってきたのでこの場合は喧嘩とは言わないかもしれない)ことを打ち明けたようで、そうしたら彼女から仲直りの印として本をプレゼントすることを提案されたという。思えば、二週間のうち一日だけ城内のどこにもあいつの姿が見えない日があったが、あれはモモイロ島の外に出ていたからなのだ。
こうしてボサ男はクリスマス料理の物資調達のために出かけるフレイヤさんたちにくっついていったらしい。物語に詳しい彼女がボサ男にいろいろおすすめを紹介してくれたらしく、最終的にあいつがこの本を選んでくれたそうだ。本なんか一度も読んだことなさそうなあいつが。
「真剣に悩んでたぞ。"あいつにひどいこと言って傷つけたから今度は喜ぶ顔が見たい"って」
「そう、なんですね」
「まァ男として気持ちはわかるけどな。自分の好いてる女がほかの男と楽しそうに話してたらそりゃ気分が悪くなるもんだ」
「……?」
急に話が変わってよくわからないことを呟いたサボさんにわたしは首を傾げた。なんのことだろうと疑問に思ったが、「ともかく」と再び話題を戻されてしまったので質問する暇はなかった。
「その様子だと上手くいったみたいだな」
ニッと歯を見せて笑ったサボさんの言葉に、こっくり頷いたわたしはこの本が単なるクリスマスプレゼントではないことを知って心がさらに温まる思いがした。
ボサ男がフレイヤさんと一生懸命選んでくれた本。ちょっと前まで山猿みたいにキーキー声でわたしの読書を邪魔していたデリカシーのないあいつが、フレイヤさんの提案とはいえプレゼントに本を選んでくれた。その事実が改めてとても嬉しかった。そういえば、珍しくボサ男が顔を真っ赤にして「ごめん」と言いながら渡してくれたので、多少気恥ずかしさもあったのかもしれない。だって、しょっちゅう訓練だとか言ってまだ全然似合っていない鉄パイプを振り回すボサ男が本を贈ることになるなんてきっと自分でも驚いたはずだ。
事情がわかったらこうしてはいられない。発案者であるフレイヤさんにもお礼を言いたかった。
「じゃ、なるべく早く寝ろよ」
「あのっ……」
「ん?」
「フレイヤさんの部屋ってどちらに――」
「あー……あいつ疲れて眠っちまったから礼を言うなら明日にしてもらえるか?」
その瞬間、不思議な光景を見た。
サボさんの表情がふと緩み、急に甘ったるい雰囲気が自分の周囲を覆った気がしたのだ。もちろん比喩だけれど、彼から発する空気がとてつもなく砂糖菓子のように甘くてふわふわしたものになったように感じる。それはフレイヤさんのことを語るときのサボさんであり、仲間たちに向ける顔とはまた違った恋人にしか見せない表情だった。わたしにはまだ恋も愛もよくわからないけど、二人が心の底から愛し合っていることだけは理解できる。
誰しもいろいろな面があるものだが、あの参謀総長を骨抜きにするフレイヤさんにまた少し憧れの気持ちが強くなる。彼女みたいに想われてみたいし、わたしもいつかそういう相手ができるだろうか。まだ考古学にしか興味ないわたしにも。
「サボさんはいいんですか? その……フレイヤさんのこと」
「いいよ。さっきまで一緒にいたし、向こうが終わったらまた部屋に行くから」
と、城外のほうをさした。どうやら大人の時間とやらにサボさんも付き合うらしい。遠くからにぎやかな笑い声が聞こえてくるので、まだまだ大人たちはお酒で盛り上がる気満々のようだ。そして、女性が居住するエリアから来たのは今の今までフレイヤさんと一緒だったかららしい。野暮なこと聞いちゃったな。
じゃあなと今度こそ去っていった彼を見送り、わたしは自分の部屋へと歩きはじめる。なるべく早く寝るように諭されてしまったが、少しくらいなら許されるだろう。こんな素敵なプレゼントをもらったのに明日の朝まで放置するなんて可哀想だ。
廊下の窓から月明りが漏れている。ふと、そっちに視線をやって夜空を見上げた。モモイロ島の冬は雪が降ることはないけれど、それでも夜は冷えるし手がかじかむほどには寒い。はあっと吐き出した息が結露を起こして窓ガラスを白くさせる。わたしはもう一度息を、今度は自身の手に向けて吐き出してから急ぎ足で部屋に向かった。