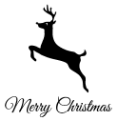
小さな愛のクリスマス(4)
小さな奇跡が起こったクリスマスの翌日。
わたしはとある部屋の扉の前に立っていた。女部屋が集まるエリアのとある一室。今からわたしはこの扉をノックする。
昨晩、ボサ男からもらったプレゼントをちょっと夜更かしして第一章だけ読んだら、想像以上に引き込まれてめくるページが止まらなかった。しかし、サボさんに言われた言葉をふと思い出して、惜しみながら机の上に本を置いて眠ったのだ。そうして、朝の七時半きっかりに目が覚めて、支度を済ませること二十分。もらった本を片手にわたしはある人の元へと急いだ。
こんな早くに訪ねて大丈夫かと心配になったが、途中で遭遇したコアラさんから「いつも七時には起きてるから問題ないと思うよ」という言葉に背中を押してもらってここにいるというわけである。
サボさんの恋人、フレイヤさん。ボサ男に助言してくれた人、仲直りの手助けをしてくれた人。見かけたことはあっても話すのは初めてだから緊張する。ちゃんと話せるだろうか。
わたしはそっと扉をノックした。
コンコン――
木の音が響いてから数秒後、「はーい」という可愛らしい声がくぐもって聞こえた。コアラさんの言う通り、もう起きているらしい。向こうから扉が開かれるまでの間、わたしは話すと決めていた内容を頭の中で反芻する。
まずはプレゼントをもらったお礼。ボサ男との仲直りを手伝ってくれたこと。そして、クリスマスの料理がとても美味しかったこと。うん、よし、大丈夫。緊張するかもしれないけど、きちんと感謝の言葉を伝えよう。
「おはようございます、私に何か……あ、」
意気込んでいた直後、唐突に扉が開かれフレイヤさんが顔をのぞかせた。ロング丈のジャンパースカートに刺繍がほどこされたベージュのブラウス。朝だというのに柔らかい笑みで挨拶されたことに心臓が跳ねて、「お、おはようございますッ」と声が裏返ってしまった。
けれど、フレイヤさんは気にすることなく笑顔で話を続ける。
「ふふ、その様子だと仲直りが上手くいったみたいだね」
「え?」
「結果を教えに来てくれたのかなって」
わたしが胸に抱えている本をさして、フレイヤさんは「読んでみた? 面白いでしょう」とまるで少女みたいに笑う。その瞬間、ぶわっと全身に血が巡り、わたしは勢いよく首を縦に振って肯定の意を示した。
「フレイヤさんがアドバイスしてくれたって聞きました。ありがとうございます。仲直りもできたし、それから昨夜に一章だけ読んだんですけど、とっても面白くて……早く続きが読みたいです!」
「私も昔ね、仲良かった司書のお姉さんに教えてもらったの。物語の本も、そうじゃない本もいろいろ知ってて憧れてたんだ。考古学には詳しくないけど、物語の本ならおすすめできるからよかったら声かけてね」
「はいッ……!」
わたしの中にある恍惚感や優越感といった嬉しさや喜びを表す感情があふれ出していく。胸がいっぱいでどうにかなりそうだ。クリスマスプレゼントをもらった上に、まだこんな奇跡があっていいのだろうか。わたしは高鳴る胸を抑えつつ、せっかくだから少し話そうというフレイヤさんの提案に乗って立ち話をはじめる。
彼女は普段通信部の仕事を手伝いながら、料理を作ったり、中庭の手入れをしたり、時には掃除を手伝ったりといろいろな雑務を請け負っているらしい。それからここへ来る前はカフェで店主を務めていたらしく、どうりで料理の腕がいいわけだと納得した。だから昨日のようにクリスマスといったイベントには料理の考案者として参加しているそうだ。なんだかあちこち駆け回っていて大変そうだが、彼女なりに好きでやっているみたいでサボさんも了承しているらしい。始終楽しそうに話すので、わたしも読書以外に興味を持ってみようかな、なんて――
と、ここで料理のお礼を伝えていなかったことを思い出す。
「あのっ……昨日の料理も――」
「フレイヤ。お前、そんな寒そうな恰好でうろうろするなって言ったろ?」
わたしの言葉に重なるようにして、フレイヤさんの後ろからひょっこりと顔を出したのは昨夜ぶりのサボさんだった。ただし、いつものウェーブな髪型ではなくところどころ跳ねて寝ぐせがついている、ちょっと抜けた感じの親しみやすさが増したサボさん。眠そうにしながらも彼女の心配をしてさらっと上着をかけてあげるところが本当に恋人想い。彼女を見る目がとてもやさしい。むずがゆくて、でも羨ましくて。自然と笑みがこぼれてしまう。
やっぱりボサ男がこの人に近づくなんて到底無理な気がしてきた。
わたしの存在を気にすることなく、彼はフレイヤさんに甘い言葉を吐いて二人だけの世界を築く。そもそもこんなに朝早くからいるということは、もしかして昨晩はずっと一緒にいたのかもしれない。特に深い意味を考えずそう思った。
「つい夢中になっちゃって……上着ありがとう」
「それ、隠しちまったのか。残念だな」
「……ッ、笑いごとじゃないよ。隠れる服があったからよかったけど、なかったらどうするつもりなの」
「別にいいじゃねェか、見せておけば。おれにもある」
サボさんがフレイヤさんの首元あたりを見て愉快そうにしている。何の話なのか、わたしにはさっぱりだったが、二人の会話から察するにサボさんには困らないけどフレイヤさんにとっては困ることらしい。隠すとか隠さないとか。彼女の首に何があるのか、わたしにはわからなかった。
数十秒、二人は攻防戦を繰り広げていたが、やがてフレイヤさんがはっとしたようにわたしのほうへ体を向け直す。
「あ、ごめんね。何か言いかけてたよね?」
「いえ、ただ……昨日の料理がとても美味しかったのでそれを伝えようと――ッ!」刹那、わたしはあることに気づいて言葉を失ったが、フレイヤさんはわたしの様子に気づくことなく続ける。
「ありがとう。頑張った甲斐があったよ。なるべく喧嘩はしないように彼と仲良くね」
「はい、いいえ……! じゃあ、わたしはこれで。本当にありがとうございましたッ!」
フレイヤさんが「あ」と何かを言いかけていたが、自ら会話を切り上げて言い逃げするみたいに部屋をあとにした。はい、いいえって我ながら何を言っているのだろう。自分でも意味がわからなかったのだから、フレイヤさんたちはもっと意味がわからないはずだ。
けれど、わたしは気づいてしまった。いや、サボさんが現れた瞬間から視界には入っていたのだと思うけど、意識して見ていなかったから今になってようやく理解した、と言うほうが正しい。
サボさんの、全開のシャツからのぞく鎖骨あたりに見えたわずかな紅い印。十二歳のわたしにも、なんとなく理解できるもの――思い出した瞬間、わたしの顔に熱が集まってくるのがわかった。
「大人なんだなぁ……」