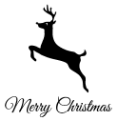
まるで宝箱みたいなひと
※現パロ
下降する狭い箱の中で、デジタルの階数表示を見ながら少しイライラしていた。
朝から理不尽な要求で顧客対応し、それが終わって仕様書の修正をしていたら突然パソコンがフリーズしてデータは吹っ飛ぶし、残業確定で気分はすっかり落ち込んで、ようやく会社を出られたのは午後八時を過ぎた頃。
エレベーターが一階に到着する。ビルのエントランスホールの奥にある化粧室で軽く化粧を直し、唇に最近買った新作ルージュを塗っていざ出陣。目指すは恋人が待つスターバックス。
今日はクリスマスだ。普段社畜で仕事に追われている私も今日くらいは定時で上がりたかったものだが、そんな奇跡も起こらずいつも通りの時間に帰るはめになった。上司も人が悪い。気を利かせて「もう上がっていいぞ」のくらい言ってくれてもいいのに、「仕様書の修正が終わるまでは帰れないぞ」なんて脅しみたいな発言をするのだから。
ビルを出て左に向かい、ひとつ目の信号を渡ってすぐの通り沿いにあるこの辺りじゃちょっと奇抜なデザインの二階建ての建物。ガラス張りの開放感がある窓側のカウンター席は一人客が勉強したり、読書したり、はたまたパソコンを広げたりと様々な用途で利用されている。
クリスマス当日。この時間帯にもなるとさすがに客は少ないが、七席あるうちの端から二番目の位置に目的の人物が長い脚を組んで文庫本を熱心に読んでいる姿はどの客よりも目立っていた。おまけに賢さを強調するような眼鏡までかけていている。本を読んでいるだけで絵になるなんて羨ましい。と、同時にその容姿のせいで余計な注目を集めていることに気づく。
大学生っぽい感じの女の子三人組がスタバの前で立ち止まっているかと思えば、キャーキャーと盛り上がりながら彼を見ているではないか。「イケメン」「本読んでるだけでかっこいいとか何者」「声かけちゃう?」等々。
まあでも気持ちはわかる。どちらかと言えば私もそちら側だ。
金髪に高身長。がたいがいいというわけではないが、程よい筋肉がついていて力持ち。地頭がいい。社交性が高いから顧客ウケがいい(らしい)。文句なしに顔がいい。中身? 兄弟馬鹿でだらしないところもあるけど、まあ可愛くて許せる範囲だし思いやりがある。こっちが遅く帰ってきたときには料理を作って待ってくれているのもポイント高い。……挙げたらキリがなかった。
彼女たちから少し離れたところで同じように恋人を見つめる。彼――サボの勤務する会社はスーツでなければならないという規定はなく、カジュアルな服装で出勤してもいいらしい。もちろん客先へ訪問するときはスーツだけれど。
以前から似合うと勧めていたタートルネックの黒いニット(予想通り似合いすぎて、心の中に小躍りする私がいる)にグレーのスマートパンツ。シンプルだけど、長身の彼によく似合っている。ロゴ入りのカップを片手に文字を追う眼鏡の奥の双眸が何とも言えない色気を放っていてズルい。これで歩くとさらに目立つから本当に困る。
嘆息してからなんとなくこのままサボを見ていたくて、寒さも忘れてぼうっと端正な顔に夢中になった。かっこいいにもほどがある。残業によるイライラも、この姿を見れば解消されるというもの。今からこの人とデートするのだと思うと、初めてでもないのになぜか緊張してきて口の中が乾く。
大学生女子たちに混じって恋人観察をしようという試みはしかし、あっけなく終了する。ふいにサボの視線が本からこちらに向けられ、ガラス越しに立つ私を捉えたのだ。「え」と驚いた直後、彼の口がゆっくり開く。
(な・に・し・て・ん・だ)
声に出していなくても、口の動きは明らかにそう伝えていた。立ち上がったサボはカウンターの上を片付け、椅子に引っかけていたコートを羽織って颯爽と扉をくぐり、一目散にこちらへ向かってくる。イケメンがいきなりガラスから飛び出してきたせいで女子たちも驚いていたが、彼の視線がそっちに向くことはなかった。
目の前までやって来たサボに呆れた表情で見下ろされる。居たたまれず、とっさに視線を地面へ流した。
「ようやく来たかと思えば店の外で往生するから本当に何してんだと思った」
「……え? 気づいてたの?」
「まァな。信号を渡る前から気づいてた」
しれっと答えた彼に唖然とする。ということは、私が馬鹿みたいにドキドキして見惚れてたのをわかってて放置してたってこと……?
その事実に気づいたら恥ずかしさがこみ上げてきて顔から火を噴きそうだった。寒いはずなのに体が熱い。
「おれのこと熱心に見てたよな」
「ちがっ……そんなこと――」
「ないって? へェ」意地悪そうにサボの口元が弧を描いた。これはまったく信じていないときの顔。悔しい。
「何よ。ちょっとお洒落したからって別に私は、」
「けど好きなんだろ? 言ってたじゃねェか、似合うと思うって」
ついこぼしてしまった正反対の言葉を即座に返され、ひょいと右手を持ち上げられたかと思うと互いの指が絡まった。繋がれた手はそのままに、電飾で彩られた並木通りに向かって歩き出す。
自信たっぷりな顔と心の中を見透かしたような発言を憎らしく思う一方で、サボの言う通りなのだから反論できない。だからといって素直に認めるのも彼の手中に落ちたようでやっぱり悔しいからちょっと抵抗する。
「じゃあ女子大生は?」
「女子大生? なんだそれ」
「若い女の子たちが近くにいたでしょ。サボのことイケメンだって騒いでたよ、よかったね」
「ほかの女のことなんか知らねェよ。お前以外は興味ないって言ったろ?」
「……」
嫌味をものともせず、それどころか何枚も上手な返しを言えてしまうあたりがサボのズルいところだ。正直な身体はたったその一言で火照り、心臓をうるさくさせる。
だけど、そうだったと思い出す。彼は社交性が高くて誰とでも打ち解けられそうに見えがちだが、興味のないことには一切関心を示さないゆえに聞き流したり、そもそも覚える気がなかったりといったことが普通にある。その代わり、身内にはとことん甘い。特に弟。たまに羨ましくなるくらいルフィくんには超絶甘い。
並んで歩くサボの手は自分のそれより大きくて温かかった。少し前まで室内にいたからかもしれないが、それを抜きにしても彼の体温は人よりちょっと温かい気がする。すっかり気分が良くなって、このあとの美味しい食事を想像したら思わず笑みがこぼれた。
「大体お前こそ、会社でこんな口紅つけて色気づくなよ」と、急に立ち止ったサボの親指がせっかく塗った新作の口紅を拭ってしまった。
「なにす――」
「同じ職場じゃねェんだ。着飾るのはおれの前だけにしてくれ」
意地悪に笑ったかと思えば今度は拗ねた顔して子どもみたいなことを言うサボに私の身体は硬直したように動かなくなる。だからズルいんだってば。
「これは直前にっ……」
言いかけた口をいったん閉じた。いつも一枚上手な恋人に、少しでも仕返しができないかと数秒躊躇ってから上目遣いで恋人を見つめる。「これ新作なんだけど可愛くない?」我ながらあざとい聞き方だったし、こんなあからさまな態度にサボが引っかかるはず――あれ……顔、赤くない?
「可愛くないわけねェだろッ……可愛いから言ったんだ、言わせるな」
最後のほうはちょっと怒ったような口調だったが、言葉の中に照れている空気が混じっているのが私にはわかる。それを誤魔化すようにサボが先に行ってしまったので、「照れなくてもいいのに」と彼の左腕に抱きついて揶揄ってやった。