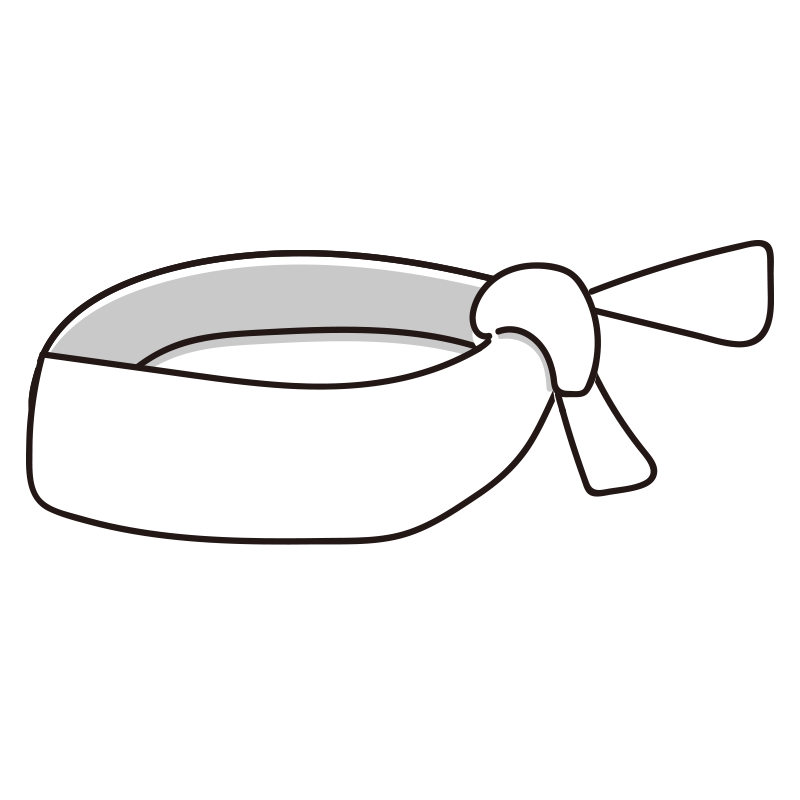
肝心なところで鈍感だね
体育祭で一番盛り上がる競技と言えばリレーだろう。何と言っても学年別のリレーは応援席も沸くし、昨年見た三年生の走る姿はやっぱり格好いい。後輩として自分も熱い声援を先輩に送った記憶がある。特にアンカーはそのチームで最も速い人が走ることが多い。私のクラスも陸上部とまではいかないまでも、サッカー部のエースストライカーが走ることになっていた。ちなみに、私はリレーに縁のない文化部育ちなので応援に徹する。
ゴール最後のコーナー付近という一番盛り上がりそうな位置まで移動するべく友人たちと歩いていると、入場門のほうへ向かっていくリレーに出場する選手たちとすれ違う。男女ともに陸上やバスケ、サッカーといった運動部の選手が多いが、まれに文化部でものすごい足が速いという稀有な生徒もいる。クラスの子に頑張ってと鼓舞して見送り、踵を返したときだった。
「ナマエ」
名前を呼ばれて、再び振り返る。
声の主をきょろきょろと探した先に、ジャージ姿の幼なじみであるサボが立っていた。身長百八十七センチのスタイル抜群な男は、学校指定ジャージも着こなすモテる男の代表格である。同じ高校生だというのに相変わらず眩しすぎる。
運営に携わる生徒会所属の彼はずっとグラウンドの中心かテントの下で係の仕事をしているなと思っていたけど、どうやらリレーには参加するらしい。
「サボもリレー出るんだ。クラス違うから面と向かって応援するのは難しいけど、幼なじみとしてはめちゃくちゃ応援してる。頑張って」
「知ってるよ、そう思ったから今声かけたんだ。その言葉が聞けてよかった、行ってくる。……ついでに上着をあずかってくれ」
「え、なんで私? ちょっとサボっ……」
行っちゃった……。
さらっとジャージの上を脱いだサボがそのまま私に向かって強引に上着を渡すので受け取るほかなかった。呼び止める暇もなく、彼の背中はほかの選手とともに入場門のほうへ消えていく。
残された私は自分のそれよりかなり大きいサイズの上着に視線を流して困惑する。持ち主の温もりが残っていてなんだか落ち着かない。もう、一体どういうつもりなの。
「ちょっとなにナマエ。サボくんとはそういう仲じゃないとか言ってなかった〜?」
すぐそばでやり取りを見ていた友人が肘でつついて冷やかしてきた。私の内なる想いを知っている数少ない友人なので、こんなふうに言ってくるのだ。けれど私だって動揺している。
「……そのはずだけど」
「向こうは案外そう思ってないのかもね。これは脈アリなんじゃない?」
ニマニマと表情を緩めた友人がからかうような口調で言ってきた。「早とちりしすぎだって」やんわり否定してから三歩ほど進んだところで足をとめる。
"脈アリなんじゃない?"
友人の言葉にちょっとだけ心を動かされた私は早くも自分のクラスを応援するか幼なじみを応援するかを天秤にかけていた。
*
いやいや、あんなに速いなんて聞いていない。
まだ心臓がバクバクとうるさい音を立てている。思い出してはこの高鳴りを抑えられず、上着を胸の前でぎゅっと握りしめてどうにか落ち着けようとしていた。
リレーはうちのサッカー部エースを抜いてサボが一位という結果に終わった。運動神経がいいのは昔から知っていたけど、まさかここまで速いとは思っていなくて正直最後はサボしか目に入らなかった。つまり、非常に格好よかったのである。「好き」のフィルターがかかっているせいもあるし、体育祭というイベントマジックのせいもあるだろう。先ほどの件といい、本当に質が悪い。
グラウンドから少し離れた水飲み場にいるサボに、あずかった上着を返す。
「お疲れさま。負けたのは悔しいけど、すごかったね」
「ん……ありがとう。まァ体を動かすのは昔から好きだったからな」
汗を流すために水道に思いきり頭を突っ込んで顔を洗っていたサボがひと息つく。タオルで顔を拭って、上着を受け取った彼の髪にはまだ水滴が残っていて、それがまた同じ高校生とは思えないほど眩しくて思わず視線をそらした。
「そう、だね……」
会話が上手く続かない。視線を地面に泳がせて口ごもっていると、「あれ?」とサボが近づいてくる。
「お前ハチマキはどうしたんだよ」
「……ハチマキ?」
問われて少し考えてから、ああと理解が及ぶ。チームごとに色の違うハチマキをするのが体育祭におけるルールであり、それを必ず身につけなければならない。私もさっきまで首元に巻いていたのだが、炎天下ではどうにも鬱陶しくてとってしまった。そういえば、自分の上着を応援席に置いてきてしまったせいであずかっていたサボの上着のポケットに一時的に入れていたんだった。でもそれが何だというのだろう。
「ここに巻いてたじゃねェか」
何を考えているのか、サボがさらに距離を詰めてきて先ほどまでハチマキがあった場所を指先でくすぐってきた。自分でもあまり触れない場所を何度も往復するように撫でるから、私の思考はピタリと停止してしまう。
「せっかく交換しようと思ったのに」
「こ、うか、ん……?」
絞り出した声は情けないほどか細かったが、サボは気にしたふうもなく言葉を続ける。
「もう体育祭も終わりだろ? お前のハチマキと交換しようと思ったんだよ」
「なんで? 終わったあとに交換する意味ある? しかもチームが違うのに」
「……まさか知らないのか?」
「……?」
なんの話だろうと首をかしげる私に、サボはあからさまに不満そうな顔をして、けれどそれ以上なにも言うことなく代わりに額に巻いていた自分のハチマキを少し乱暴にはぎとり、私の鼻先に突き出してきた。
「おれのをやるから鞄のどこかにつけとけ」
「え? 意味わかんない」
「意味わからなくていいよ。いいか? 必ずつけろよ」
念を押しながら、最終的に怒って水飲み場を離れていくサボをやっぱり意味がわからないまま見つめる。なんだったの……。私のドキドキを返してほしい。まだ微かに高鳴ったままの心臓を落ち着かせるように、強引に渡された彼のハチマキを握って私も自分の席に戻る。
ハチマキのジンクスについて知ったのは閉会式後の教室でのことだった。動揺を隠せずぼうっとしていた私は、自分のハチマキを入れっぱなしにしたままサボに上着を返してしまったせいで、強制的にハチマキ交換をさせられたことに気づいてその場で発狂したのである。