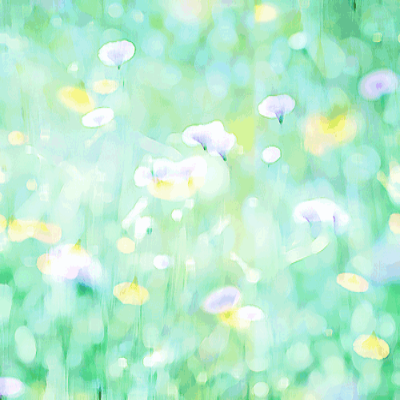
世界は無味乾燥
それは、この世界でよくあることだったし、特別騒いで目くじらを立てることでもなかった。高校二年に進級して二週間しか経っていないことは問題だったが、そのうち収まるだろうと今は願うばかりしかない。
きっかけは金曜日の帰り道でのことだったと思う。
エミとリンとリカ。中島エマが普段所属しているグループであり、クラスの中でも派手で中心にいて目立つ――言い換えればリア充なグループだ。スクールカーストなんていう言葉が最近あるらしいから、それに合わせると頂点にいる子たちで形成されている。
部活が終わって四人で帰るのはいつものこと。会話の内容は学校での出来事とか彼氏の話とか、流行っている音楽、コスメとか先生の悪口とか他愛ないことばかり。エマはたいてい聞き役で適当に相槌を打つ。気が抜けないのはグループのリーダー的存在であるエミの機嫌を損ねないことなのだが、このときエマは何を思ったのかつい口から出た言葉で周りの空気を一気に氷点下まで下げてしまった。
エミが彼氏と映画を観に行った話だった。公開を待ちきれなかった映画らしく初日に観たというその内容は、エマもテレビやネットを通してあらすじは知っていた。こてこての恋愛映画である。よくあるパターンの、病を抱えた女の子とそれに寄り添う男の子。
"ありきたりなストーリーの映画だよね"
あのとき確かエマはこんなことを言った気がする。別に映画自体を否定したわけではない、素直に思ったことを口にしただけだ。それがどうやらエミの癪に障ったらしい。帰宅してから失言だったということに気づいたのだがもちろん手遅れで、週末が明けた月曜日、エミは早速グループの輪からエマを弾いた。リンとリカはエミに逆らわないから三人とエマ一人という構図が出来上がる。
教室移動、トイレ、班活動。学校生活というのは何かとグループで行動することが多いというのに、進級して早々何をしているのかと問いたい。特に女子は群れで行動しがちだから余計に。いじめられているわけではなくても、いつも一緒にいる四人が急に仲間割れを起こしたのだと周りには思われるし、標的が自分であることを晒すのは生意気にもエマのプライドが傷つく。
実験室での化学授業。水中に塩素が含まれているかどうかの実験を班ごとに実施するとかで、それぞれの机には先生があちこちでとってきた水がビーカーに入って置いてある。このビーカーに特定の試薬を入れて確認するというので、エマたち七人班は二、二、三の組み合わせで実験をすることになったのだが。
案の定、三人組はエミたちでエマは男子と組まされた。険悪な雰囲気は肌で感じていたけれど、ほんの少しの望みをかけてエミたちに話しかけてみる。
「ねえ、私も一緒にいい?」
しん、とエマがいる机の周りだけが静まり返る。エミたちがお互いを見合って黙り込んだかと思うとクスという笑い声が聞こえた。気まずくなったエマはそれ以上なにも言うことができず、男子のほうに足を向けてそのままやりたくもない実験をすることにした。
男子がこちらの事情をどう感じているかはわからないが、険悪な雰囲気は伝わったらしくあえて聞いてこようとはしなかったのでほっとする。そもそもクラス替えして初めて知り合った男子だし、いわゆるエマたちリア充とはかけ離れた地味で草食な理系男子――エミに言わせるとそうらしい。
試薬を数滴たらして確認していく淡々とした作業。正直に言ってつまらなかった。男子と喋ることもなければ、こちらから話しかける共通の話題も見つからない。何よりすぐ隣で楽しそうに笑う三人の声が耳ざわりで、早く終わらないかと何度も時計を見た。
当然のことながら昼食も三人で食堂に向かったので、エマは仕方なしに外の空いているベンチで黙々とぼっちご飯時間を過ごした。この学校の良いところは、食堂や教室以外にもランチができる場所がたくさんあることだ。ひとりで優雅に読書を楽しむ生徒もいるので、エマが浮いているというわけでもない。
そのまま昼休みに突入し、教室に戻ろうとしたところで「エマ」呼び止められた。振り返ると、走って来たのか息をきらしたリカだった。エミとリンがいないところを見るとトイレにでも行っているのかもしれない。続けてごめんねと謝罪してくる。
「エミはああいう性格だから仕方ないよ。でもさっき化学の授業でエマが話しかけてたのはすごく偉いと思う。エマがそういうふうに懸命な態度でいればエミもそのうち溜飲が下がると思うから」
リカの言葉に頷きながら頭の中ではなにを言ってるんだろうと首を傾げたい思いだった。
そういうふうに懸命な態度。そのうち溜飲が下がる。どうしてエミに媚びを売らなきゃいけないのか。そして同時にリカはエマにも媚びを売っている。こうやってエミの見ていないところで、密かに話しかけてくるあたりリカはどっちつかずだ。そのわりに無視されているエマに対して優越感を抱いているから苛立ちを覚える。エミが怖くて堂々とこっちに話しかけることができないくせに。
ばかばかしいと思いつつ、話しかけられて内心ほっとしている自分もいる。ばかばかしいのはどっちだろう。結局自分も同類なのかもしれない。
「部活も休まないほうがいいよ」
「うん、わかってる」
そろそろエミたちが戻ってくるからと逃げるようにして去っていった背中を見つめて、思わず大きなため息をついた。
学校という箱庭でエマたちが築く世界は、狭くて息苦しくてそれでいて無味乾燥だった。