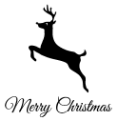
革命軍のクリスマス
※このお話は『たしかに恋をしていた』の番外編です。
クリスマスというイベントがあることを教えてもらった二か月ほど前。フレイヤの暮らしていた島、セント・ヴィーナス島はいろんな文化を取り入れている場所だと改めて知る。つい先日、本部でハロウィンパーティーが盛大に開かれたばかりだというのに、もう次のイベントが待っているとは忙しい。
コアラがその話を聞いたとき、ハロウィンと同様に保護施設の子どもたちも呼んでパーティーをしたいと願い出たフレイヤに「彼女らしいな」とつい笑みがこぼれた。子どもたち一人ひとりにプレゼントを渡してあげたいらしい。何でもとある国ではサンタクロースという名の白髭を生やしたお爺さんが夜中、家々を回って子どもたちにプレゼントを置いていくそうだ。彼女はそれを真似たいという。
そういうわけで、クリスマスも目前に迫った日の午後。コアラはフレイヤとともに町へ繰り出していた。モモイロ島内の町はいつの間にか冬の装備をしているが、コアラの知る冬は辺り一面が真っ白の雪景色だ。寒くて、吐く息が白くなる。もちろんここも一気に寒くなったものの、雪景色には程遠い。クリスマスという文化がない地域では街並みがそうした装飾で埋め尽くされることはないし、モモイロ島もその地域に入る。
町の雑貨店やおもちゃ屋が並ぶ通りにはいつもと同じ和気あいあいとした雰囲気が漂っている。新作商品を売りだすために看板を掲げたり、チラシを配ったり、店員が声掛けしている店もある。コアラはフレイヤと事前に購入先を町一番のおもちゃ屋にすると決めていたので、目移りしそうになるのをこらえて『ハムワーズ』という老舗のおもちゃ屋の扉をくぐった。
一階は量産されたぬいぐるみや一点もののテディベアが並び、地下には絵本やボードゲーム、外で遊ぶためのボールやスポーツ遊具などが陳列している。二人で商品をあちこち見て回る中、フレイヤがふと呟いた。
「女の子は絵本や人形が好きな子が多いけど、外で遊ぶ子もいるから数はどれも同じくらいにしたほうがいいかなって思う」
フレイヤは時間があると、保護施設の子どもたちの面倒を見ている。普段から彼らの好みを把握しているからか、必要なおもちゃの種類や数にも安易に想像がつくらしい。
「男子だって本好きはいるだろうし、小さい子であれば人形が好きな子もいるもんね」
「うん。だからどれも同じ数にして、あとは譲り合ってもらおうと思ってる」
「それがいいかもしれないね」
コアラは同意を示して、籠の中に目いっぱいぬいぐるみを入れていく。指定の時間になったらハックたちが荷物持ちで来てくれることになっているので問題ない(ちなみに「おれも行く」と参謀総長が執務室を出ていこうとしたが、入れ違いに入って来たイワンコフに止められていたので彼は留守番)。
『ハムワーズ』は業界の中でも有名なおもちゃ屋で世界に十店舗構えている。そのうちの一つがカマバッカ王国にあることには驚いたが、子どもだけでなく意外と大人も利用するようだ。特に一点もののテディベアは大人気だそう。
フレイヤが地下に移動するというのでそのままついていくと、早速何か目ぼしいものがあったのかこっちに商品を掲げて見せてきた。
「コアラちゃんこれ見て! リュカくんたちが好きそうだと思わない?」
「いー、りおん……?」
フレイヤの手にある正方形の箱に書かれた商品名を読み上げる。聞いたことない遊びの名前が書かれていた。詳しく聞くと、領地を拡大させるカードゲームらしく複雑なルールはないのに戦略性に富んだゲームだという。戦略を練るなんて革命軍らしくて確かに面白そうだ。
「ほんとだ、楽しそう」
「でしょう? 複数人で遊べるものが一つか二つあってもいいな。サボに時間があったら一緒に遊んであげてほしいなって思うけど忙しいよね」
「今はね。でもサボ君だってずっと忙しいわけじゃないから、休憩中に遊んであげられるんじゃないかな。だから、ボードゲームもいくつか選択しようか」
コアラは、フレイヤとともに子どもたちが楽しめそうなボードゲームを吟味していく。大人が楽しめるものから小さい子でも簡単に参加ができるものまで世界には様々なゲームがあるようで、自分の知らない世界を見て回るのは興味深かった。彼女と二人だけでショッピングするのも久々だったので、時間があれば自分たちの買い物もして帰ろうと決めて、コアラは隣で楽しそうに商品を見ている友人を微笑ましく見つめた。
*
「それが買ってきたプレゼントなのか?」
仕事を終えたサボが部屋に戻るといつもいるはずのフレイヤの姿がなく、どこにいるのかと思えばテーブルの上にメモ書きで「自室にいる」とのことだった。そのまま彼女の部屋に向かったサボは、ノックもそこそこに入ってすぐ、床とテーブルの上に広がったおもちゃの山を見て目を見開いた。それらを丁寧に包装している彼女はおもちゃの山からひょっこり顔を出して「お疲れさま」とのんきに手を振った。
そういえば、明後日はクリスマスとかいうパーティーを中庭で開催するからそのためのプレゼントを買いに行くと言って、コアラと午後に出かけていた。自分もついていくつもりが、イワンコフのせいで留守番になった。
「うん、必ず全員の手に渡るようにコアラちゃんと選んできたよ。……あ、そうだ! イーリオンっていうカードゲームが頭を使う戦略ゲームみたいでね、サボもリュカくんたちと一緒に時間ができたら遊んであげてほしい」
「ふーん」
包装中のおもちゃの中に、彼女の言う「イーリオン」というゲームが目に入る。裏に簡易的なルールが記載されているのでざっと目を通してみると、自分の領土を広げていくことを目的とするゲームのようだ。シンプルだが、カードの種類が豊富なので単純というわけではなく逆に複雑で戦略的部分が色濃く出るらしい。
面白そうだということはすぐにわかった。プレイするたびに違う展開になることが容易に想像できる。そういうゲームは面白いだろう。確かにやってみたい気はしているが、リュカへのプレゼントだと聞かされると途端に喜びは半減する。それもこんな楽しそうな顔して包んでいる姿を見たら尚更。
「……? サボはこういうのあんまり好きじゃないかな」
「そういうことじゃねェけど……これ、あいつのために選んだやつだろ? おれにとったら全然面白くねェよ」
こういうことを言うと、リュカがすぐ「大人げない」とか指摘してくるので最近は口に出さないようにしているものの、目の前であからさまに楽しそうにされるとどうしたって言わずにはいられなかった。子ども相手になにムキになってんだと自分でもわかっているのに、フレイヤの好意はすべて自分に向けられるべきだという独占欲がふとした瞬間に湧き上がる。特にリュカは彼女に好意を抱いている男だ。油断ならない。
何も反応がないことが気になって彼女に目を向けると、保護施設の子ども見ているときと同じ表情でこっちを見ていた。おれはガキと同等か。
「――笑うなっての」
「サボってたまに子どもみたい」
子どもみたいって……。いや、まァ否定はできねェか。けど何と言われようとも今はいい。
サボは、笑って手が止まっているフレイヤの真横に立つ。
「んじゃ、その子どもと今から遊んでくれるか?」
「まだ包装終わってないからもうちょっと待っ――」
「あとでおれも手伝うからさ」
フレイヤの手にしていたプレゼントを半ば無理やり取り上げてテーブルの上に置いたサボは、そのまま彼女の手首を掴んでベッドへ誘導した。
*
サボは居たたまれない気持ちで中庭に佇んでいた。景色に溶け込んではいるが周りからの視線が痛いほど突き刺さる。特に子ども。大人は見て見ぬふりをする奴もいるが、気心が知れた仲間からは「似合わない」「いや、逆にいい」「若いサンタクロース」といった揶揄の言葉を浴びせられた。
中央に設置されたのっぽな木はフレイヤが特注で取り寄せた高さ十五メートルもあるクリスマスツリーという今回のイベントを象徴するものだ。深い緑色をした木に、キラキラと輝く飾りがたくさんつけられている。
クリスマス。聖なる夜。信仰に関係したイベントだというが、フレイヤの故郷では家族で一緒に食事やケーキを食べて祝うらしい。例のごとく彼女の提案で、本部の仲間達が集まり盛大なパーティーを開くことが決まった約二か月前から下準備は始まっていた。
世界には子どもたちにプレゼントを配る人間――サンタクロースという名の不思議な爺さんがいるそうで、彼女自らその役を買って出たらしいのだが、コアラの「サボ君も一緒にやったら?」などという一言で再び変な服を着せられる羽目になった。ハロウィンのときよりも可笑しな赤と白の服だ。これがサンタクロースという爺さんの正装らしい。ちなみにフレイヤは料理の準備中で、まだここに合流できていない。
「そんな怖い顔しないでくださいよ。ちゃんと似合ってますって」
陽気になっている複数の部下が再びサボの周囲に集まってきた。メイン料理はまだ運ばれてきていないが、酒と軽いつまみがすでに並べられており、グラスを片手に赤ら顔の奴までいる。グラスの中はしゅわしゅわと弾ける泡が見えるシャンパンやワインだ(子どもにはココアを用意しているらしい)。ハロウィンのときと同様、フレイヤ達がスペシャルドリンクというやつを考案したようだ。サボもさっきワインを飲んでみたが、ただのワインではなく温められたホットワインというやつで、中に蜂蜜を入れ、さらにオレンジのスライスを添えてある洒落た飲み物だった。
「フレイヤさんとお揃いでいいじゃないですか。革命軍のサンタクロース」
「そうそう。バカップルっぽくていいです」
「お前それは総長をバカにしてないか?」
「してねェよ。仲が良いってことだ」
口々に好き勝手言っている部下達に呆れた視線を送る。別に今更なにを言われてもどうでもよかったが、子どもたちから好奇の目を向けられるのは勘弁してほしい。「サンタクロースだ」「プレゼントはまだ?」「おひげ触らせて」等々、散々興味の対象になった。一度は落ち着いたが、彼らの好奇心は収まらずキラキラした視線をいまだに感じる。
フレイヤが来ればいくらか居たたまれなさは解消されるというものだが、一人だけ仮装した状態はどうあっても目立つ。
「お前ら、ガキ以上に楽しんでるだろ」
「そりゃまあ。だってフレイヤさんが来てからじゃないですか。こういうことするようになったの」
「これまでも仲間内でガヤガヤ飲んだり食ったりすることはありましたけど、子どもも一緒に楽しめるイベントはいいですよねえ。平和の象徴みたいで」
「……そうだな」
そう言われると納得せざるを得ない。
サボは中庭で各々楽しんでいる仲間や子どもたちに視線を移す。何気ない光景だが、確かに平和であることの証だ。世界政府と対立してあちこち駆け回る日々に終止符を打つとき、この景色にフレイヤと溶け込むことができることを願って、サボは未来に思いを馳せた。
しばしば感傷に浸ったところで、料理長を筆頭にメイン料理やデザートが運ばれてきた。一番後ろに自分と同じくサンタクロースの衣装をまとったフレイヤもいる。どういうわけか、丈が短いスカートをはいて惜しげもなく白くてやわらかそうな脚を晒している。
「おれ達料理人とフレイヤちゃんで考案したスペシャルクリスマス料理だ。たくさん用意したから焦らずにな。もちろんケーキもある。思う存分食ってくれ」
料理長の言葉を歯切りに、みんながテーブルへ群がる。部下達も早速とばかりに料理のほうへ向かっていく。
子ども用もあるのか、背の低いテーブルにはかわいらしいデコレーションがなされた料理が並んでいた。近くにフレイヤがいるので、きっと彼女が担当したのだろう。たちまち囲われてちょっと照れくさそうに笑う姿を前に、相変わらず子どもに好かれる性分だと微笑ましく思う。しかし、彼らもハロウィン以来の物珍しい凝った料理には我慢ができないのか早々にフレイヤから離れて飛びついた。
サボは彼女の周囲に誰もいなくなったのを見計らって近づく。
「お疲れさん」
「あ、サボサンタ」
「……その呼び方はやめろよ、恥ずかしいだろ?」
「おひげがとってもお似合いですよ」
「お前なァ……まーいいや。それよりその丈は短すぎなんじゃねェか?」
あくまでサンタクロースであることを主張するフレイヤに呆れつつ、けれど今日はそういう日だと思ってサボは諦めることにした。とはいえ、彼女の格好には納得いかない。
「やっぱりそう思う? 私もちょっと抵抗あったんだけど、先輩たちから"それでいけ"って。普段出さないんだからこういうときに出しとけってよくわからない理論を言われたのと……総長だけなんてもったいないとも言ってた」
露出が少ない用もあったのになあ、と苦笑いするフレイヤにサボは眉をひそめた。もったいないってフレイヤはおれの女だぞ。当然じゃねェか。
通信部で手伝いをしている彼女は、その部署の先輩から主にろくでもないことを吹き込まれてたびたびサボを悩ませていた。完全に遊ばれているのだが、真面目な彼女はたいていのことをまっすぐ受け止めている。本当に嫌なら断っているだろうから、きっと本人も多少なりとも着たかったのだと思うが。
「――っていうのは建前。別にほかの人に見せたいわけじゃないけど……サボにはちょっと見てほしいかなって下心があったの。ダメだった?」
「……」
そんなふうに言われたら咎めることもできない。メイド服といい、随分と大胆になったフレイヤを複雑な思いで見つめる。再会してからますます綺麗になっていく彼女に喜びを感じると同時に焦燥感も覚える。これまでにも自分達の関係を知らない新人が彼女に好意を寄せて近づいてきたり、かと思えばガキに結婚を申し込まれたりと油断も隙もないのだ。
何を隠そうそのガキというのが――サボは視線を子どもたちのほうへ移し、目的の男子を探し当てる。視界に入れたその子どもは、みんなとの会話に加わることなく一点をぼうっと見つめていた。
「リュカ。お前誰の許可とってフレイヤの足を見てんだ、このエロガキ」
「なッ……ちげーよ! ただいつもより肌がっ――」
「肌がよく見えるって? はは、お前いい度胸だなァ」
「怖ェよばかサボ! こっち来んな!」
つい先日十三歳になったリュカはますます生意気になり、相変わらずフレイヤへ想いを募らせたまま消化できないでいるらしかった。気持ちはわかるが、彼女の恋人という立場としては看過できない案件だ。子ども相手に本気にならなくてもいいとわかっていても、こいつは結婚を申し込んだりデートに誘ったりと油断ならない相手である。
「もう〜どうして二人は喧嘩口調でしか会話できないの。仲がいいかと思ったらすぐこれなんだから」とフレイヤが少し離れたところでむっとしていた。会話の内容までは聞こえないのか、何に怒っているのかわからないらしい。
「サボのせいでフレイヤに怒られた」
「おれのせいにするな。お前があいつの生足見て顔赤くしてたから指摘しただけだ」
「ッ……フレイヤに余計なこと言うなよっ」
「誰が言うか。あと呼び捨てにするなって言ってんだろ」
「うるさい。サボに関係ない。フレイヤがいいって言ったからいいんだ」
よくねェよ。おれが。とは言わずに、サボは嘆息して渋々フレイヤの元に戻った。
最年長であるリュカは施設内の子どもたちから信頼を得ている面倒見のいい少年だが、ひとたび好きな女のことになると思春期真っ只中の男だ。そういうことに興味を持ち始めてもおかしくない。ただ、その対象がフレイヤであることは気に入らないが。
「なんでそんなにむすっとしてるの? リュカくんと何かあった?」
戻ってきて早々、フレイヤが心配したような優しい声で問うのでサボは首を横に振った。
「これは男同士の問題だからお前は気にしなくていい。それより、もうプレゼント配らねェか?」
夜も八時を過ぎて、見上げた吹き抜けの先に瞬く星がいくつも見える。さすがに冬ともなると入ってくる空気は冷たく、けれどサボの体には寒さへの耐性があるため震えるほどではない。
サボはクリスマスツリーの前にフレイヤと共に立ち、大きな袋から一つずつプレゼントを取り出しては目を輝かせる子どもたちに手渡していた。すでにもらって包装紙からおもちゃを取り出した子どもが感嘆の声をあげている。彼らが列を作ってソワソワしながら順番を待っている様子を見ていると、まるで自分が本物のサンタクロースになった気分だ。実際は子どもが寝ている間にやってきてプレゼントを置いていくらしいが。
フレイヤの滑らかで程よい肉のついた白い足をいつまでも公然に晒すのは不満という私的な理由で、サボはクリスマスプレゼントを配ろうと提案した。もちろん三、四歳の子がいるので、あまり遅いのはよくないというまともな理由もある。
ちなみにリュカが例のボードゲームを受け取るとき、緊張なのか興奮なのか視線が彷徨っていてフレイヤに心配されていた。隣でその様子を見ていたサボは、彼の心情が手に取るようにわかるため少しだけ同情した。こういうところはまだまだガキである。
「はい。これは二人で一緒に使えるお絵描きボードだよ」
列の最後にいた姉妹にフレイヤが渡したのは長方形の箱。カラフルな配色の包装紙がかわいらしい。数の多さから包むのは帰ってから自分で行うと、コアラと二人で雑貨屋にも行ってきたそうだ。
受け取った二人が仲良く開けていて、宝を探し当てたみたいな表情でおもちゃを見つめる姿はとても尊かった。子どもたちはすっかりプレゼントに夢中で、施設長の「そろそろ帰るから片付けなさい」という言葉も聞こえていないようだ。ほかの連中はアルコールを楽しんでおり、大人はこれからが本番とでもいうように話が尽きない。
すべてのプレゼントを渡し終えたフレイヤに労いの言葉をかけた。ふうっとひと息ついた彼女が頬をゆるめて「疲れたね」と寒空の下で汗を拭った。
「あれだけ渡せば疲れるだろ。ドラゴンさんも礼を言ってた、ありがとう」
「ううん、私も買い物するの楽しかったから。人の喜ぶ顔っていいよね」
十歳まで貴族として生きてきたフレイヤが素直にこう言えることは、たまに奇跡なのではないかと思ってしまう。カートレット家の長女として生まれ、食うものも寝る場所も何ひとつ不自由なく与えられ、かつ豪華なものに囲まれた生活を送れば、傲慢になってもおかしくない。両親がそういう考えなら尚更。確かに彼女の価値観は自分と同じだったが、離れていた五年間もあれば無理やり捻じ曲げられてしまっても無理ないというのに。
純粋で無垢で、自分の知らない新しいものには目を輝かせて。そういうフレイヤだからこそ、サボは好きになった。
「フレイヤ。お前、本当にいい女だな」
「……急にどうしたの。なにか企んでる……?」褒められて恥ずかしいのか、言葉のフレイヤの顔が赤く染まる。
「別に。改めてそう思っただけだ。けど、その衣装は早く脱がせたい」
「なに言って……わっ――」
「コアラ! 悪ィがおれ達は先に抜ける。片付け頼んでいいか?」
目を丸くさせているフレイヤに構うことなく彼女を抱き上げたサボは、ツリーの左側に位置するテーブルを囲って幹部達とシャンパンを飲んでいたコアラに声をかけた。ほとんどが頬を赤らめているが、ベティだけはまだまだといったところだ。今夜、ここに並んでいるアルコールは普段飲みなれている種類ではなく、ワインやシャンパンといったクリスマス仕様なので飲み足りない者もいるかもしれない。
「また二人で抜け出す気ィ〜? サボ君って暇さえあればフレイヤにがっついてるよね」
「いいじゃないか。サボも好きな女の前じゃただの男ってことだろ」
「ベティさん、甘やかさないで。大変な目に合うのはいつもフレイヤなんです」
「まァ確かに……食ったら美味そうな感じはするな」と、ベティがこっちに近づいてきた刹那――
「ひゃぁ!」
フレイヤが突然甲高い声を上げた。何事かと思えば、ベティの手がフレイヤの外気に晒された足に触れていた。それだけでなく上下に往復している。
「少し太腿を触っただけだ。そんな騒ぐな」
「けどベティさんっ……それ、少しじゃなくて撫でてますッ」
「なるほどな。サボが夢中になるわけだ」
「……その辺にしておけ。サボが怒るぞ」
口を開こうとしたら、カラスが先にこちらの心情を読み取ったような口ぶりで言った。普段は寡黙で拡声器を使わないといけないほど声が小さいが正義感に溢れたいい奴だ。指摘されたベティは、しかしあまり悪いと思っていない様子でぱっと手を離したかと思うと、「そう怒るなサボ」と軽く言い放つ。ったく、どいつもこいつも油断ならねェな。
「おいベティ。フレイヤに触れていいのはおれだけだって伝えたろ?」
不機嫌を隠すことなくそれだけ言うと、サボは踵を返して中庭を出ていく。
今宵のサンタクロースはもう仕事を終えて、これからはプライベートの時間だ。フレイヤとのクリスマスはまだ終わっていない。