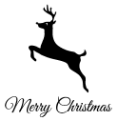
小さな愛のクリスマス(1)
※このお話は『たしかに恋をしていた』の番外編です。
クリスマス料理の打ち合わせのため料理人たちと話し込んでいたフレイヤは、夕方になってようやく厨房から出て自身の部屋に戻るところだった。すっかり日も傾いてきて、年中春らしいこの地域も多少寒くなっている。
イベントごとに皆が集まって大宴会を開くのは恒例行事になりつつあった。クリスマスは城外の開けた場所で料理とお酒(子どもたちはジュース)を広げてパーティーをすることが決まり、今から楽しみにしている人が大勢いる。コアラたちからは早速料理を期待する言葉をかけてもらい、フレイヤはやる気に満ち溢れていた。保護施設の子たちもクリスマスケーキやプレゼントがもらえるという噂をどこからか聞きつけたようで、昨日訪ねたときには「何がもらえるのか」と聞かれたくらいだった。
ケーキは一番気合が入るところなので料理長が張りきって指揮を執ることが決まり、フレイヤはサポートしながら料理のほうをメインに担当する。今日はその初回の打ち合わせだった。どういった料理を作るか、材料の調達はどうするかといったことだ。
比較的仕事の自由がきくフレイヤが近くの大きな島まで買い物に行くことになり、早速来週に外出することが決まった。
「忙しくなるなぁ」
呟いてから、フレイヤはクリスマスなどの特別な料理専用のレシピ本を借りてみようと思い至り、踵を返した刹那――
どん、と誰かがぶつかってきて耐えきれず尻餅をついた。
「うわあ!」
子どもらしい叫び声が聞こえたかと思うと続けて「ごめんなさい」という謝罪が聞こえてきた。
フレイヤは目をぱちくりさせてぶつかった相手を見る。帽子にゴーグル、鉄パイプ……まるでサボを彷彿とさせるような恰好をした十歳くらいの男の子だった。ゴーグルは片側がひび割れしているけれど。
ぼうっとしたまま動かないこちらを訝んだ男の子が恐るおそる口を開き、
「もしかしてどこか打った……?」と心配そうに見てきた。
「あ、違うの、私こそ急に振り返ってごめんね。君があまりにもサボにそっくりな恰好だから驚いただけ」
そう言うと男の子は目を見開いて固まった。どこに驚いたのかわからなかったが、たちまち顔を赤くさせた彼は口をパクパクさせながら「あ」とか「えっと」とか上手く言葉を紡げずにいた。保護施設の子かと思ったが、見たことない子なので兵士として訓練を受けている子だろう。サボと同じ武器である鉄パイプがその証拠だ。
男の子は俯いて口をもごもごさせたかと思うと、決まりが悪そうにぼそっと呟いた。
「おれのほうこそごめんなさい。ちょっと落ち込むことがあってぼうっとしてたんだ」
「落ち込むこと?」
「うん……」
男の子の目が伏せられ、悲しい表情になる。このまま放置するのも気が引けたフレイヤは思い切って尋ねてみることにする。どうせこのあとは夕飯まですることがないので話を聞くくらいならできるだろう。
「その話、聞いてもいい?」
こちらの言葉に男の子は一瞬きょとんとしたが、すぐに顔を綻ばせてフレイヤの手を引くと談話室のほうへ向かうのだった。
*
中途半端な時間帯だからか、談話室は珍しく誰もいなかった。それでも誰かに聞かれるのは困るらしく、フレイヤの手を引いて端へ向かっていく男の子の背中を見ながらますますサボの真似をしている彼のことが気になって仕方ない。
カーブしたソファの奥側へ腰を下ろした男の子の隣に腰かけたフレイヤは、彼をまじまじと見つめて首を傾げた。鉄パイプが彼の身長に合っていない。あきらかに長すぎる。もしかしたらこれから身長が伸びることを見越しての長さなのかもしれない。しかし、そのちぐはぐさもサボに近づきたい気持ちの表れなのかと思うと可愛らしい。ちなみに年齢は十二歳だという。
フレイヤは彼が口を開くのを待った。
「おれ、ひどいこと言っちゃったんだ……」
しばらく俯いていた彼はようやく話してくれる気になったようで、「ひどいことを言った」という言葉を歯切りに数時間前に起こった出来事を打ち明けてくれた。
彼のそばには仲のいい同い年の本好きな女の子がいるらしく、以前は事あるごとに揶揄っていたという。しかしあることをきっかけに自身の態度を改めて、彼女を守れるくらいに強くなると誓い、訓練に励んでいる最中とのこと。
ところが、今日たまたま彼女が食堂で知らない兵士(しかも自分より年上)と仲良くしているのを見かけてつい暴言を吐いてしまったそうだ。
「お前なんか本ばっか読んでるだけで弱ェくせに」と――
男の子の表情は話していくうちに段々と暗くなり、最後のほうは死ぬ直前みたいな蒼白した顔になっていた。
事情は粗方理解した。なるほど、本好きな女の子はさぞかし傷ついただろう。言われたときの彼女の気持ちを考えると胸が痛い。聞けば、麦わらの一味であるニコ・ロビンのように考古学者になるのが夢だという。
彼の口ぶりからして、自分の知らない男の人と仲良さそうにしていたのが面白くなくて言うつもりのなかったことを言ってしまった、というところだろうか。
つまり、嫉妬したのだ。十二歳でまだ体つきは子どもの範疇を出ないものの、男として気になる女の子の周囲にいる人間には敏感なようだ。こうして自分でも傷ついているあたり、その感情の正体には気づいていないだろうけど。
フレイヤは思わずクスッと笑みをこぼした。
「でも君はそれを言っちゃダメなことだってわかってるんでしょう?」
尋ねると、男の子はゆるやかに首肯した。そして悲しそうに「ちゃんとわかってる。あいつを傷つけたってこと」そう続けた。
子どもの頃の喧嘩は本当に些細なきっかけが多いものだが、こうしてそばにいるなら仲直りするチャンスがいくらでもある。この先二人がどういう道を生きるかわからないのだ。互いに何も言えないまま会えなくなる前に誤解はきちんと解いておいたほうがいい。何より、彼は彼女をとても大切に想っているようだから。
男の子の手を握ってフレイヤは目を細めた。
「だったら、何を言えばいいかわかるよね」
「……うん。おれ、きちんと謝るよ」
男の子の思いつめたような表情はすっかり抜け落ち、希望にあふれているように見えた。まだ兵士としては頼りないかもしれないが、こうして素直に謝ろうとする態度はとても立派だし良い男に成長するに違いない。サボの真似をしているようだから、そのうち竜爪拳なんかもできるようになってりして――
そんなことを思いながら、しかしフレイヤはせっかくならもうひと工夫あってもいいなと名案を思いついた。
「こういうのはどうかな。謝るだけじゃなく、彼女に本をプレゼントするの。クリスマスも近いことだし、ちょうどいいと思わない?」
こちらの問いかけに男の子は顔をぱあっと明るくさせて「それいいな!」と両手を拳の形にして喜んだ。
「クリスマス料理の材料を調達しに近くの島へ行くから頼んでみるね」
「ありがとうフレイヤさん! 午後の訓練も頑張るよ」
じゃあおれはもう行きますと、別れの挨拶もそこそこに彼は談話室から姿を消していった。十二歳ゆえに、まだまだやんちゃな部分が多く残っている元気な背中だった。その姿を見ながら、自身の恋人を重ねて思わず笑う。
だが、すぐにハッとしてフレイヤはあることに気づいた。
「名乗ってないのに知ってたんだ」