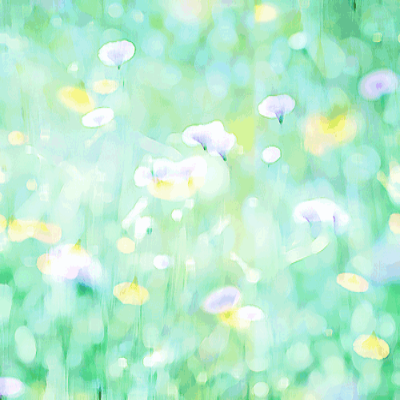
光さす深海
エマの朝は基本的にハイペースで物事が進む。ギリギリまで睡眠時間を確保するためだ。だから起きてから家を出るまでの時間は三十分。その間に髪のセットも着替えも朝食もすべて済ます必要がある。
母とのわだかまりは解消されないまま、翌日を迎えた。サボが練習を終えるのと同時にエマも帰宅することにしたが、結局そのまま部屋に直行して寝てしまったのである。分かり合おうとしなくてもいいと言ってもらえたことで、悶々とした気持ちは多少すっきりしたが、勝手に処分したことは許されない行為だ。だからこちらから和解を示すのはやめておく。かといって無視するのも子どもっぽいので業務連絡くらいは会話しないと。
「今日はちょっと寄るところあるから」
「そう……わかった」
「じゃあもう行く」
ダイニングテーブルの端に置いてある鞄をとって出ていこうとしたとき、
「エマ」
母の苦しげな声が背中に届いた。振り返って「なに」思った以上に冷たい響きを伴った音が出て自分でも驚く。目線を合わせるのも億劫で、エマはずっと床を見ることしかできない。
「ううん、なんでもない。いってらっしゃい」
娘の態度に恐怖したのかもしれない。言いたいことを言わせない雰囲気を作ってしまい胸が少し痛むが、元はと言えばこの状況は母が作り出したのだ。それをエマが修復する義理はないように思う。
学校に着いて真っ先に図書室へ向かった。ガラス張りの扉を引いてカウンターをのぞくとマキノの本を読んでいる姿が目に入る。夢中になっているのか、エマが入ってきたことに気づいていない。
その姿にふっと笑みをこぼして、エマはマキノに声をかけずに文学の棚へ直接向かった。海外文学の棚。国ごとにまとめられているのだが、そのうちの一角にドストエフスキー本が並んでいる。
罪と罰。貧しい元大学生ラスコーリニコフは「一つの犯罪は百の善行に償われる」と「選ばれた非凡人は新たな世の中の成長のためなら社会道徳を踏み外す権利を持つ」という独自の思想を持ち、それゆえに金貸しの老婆を殺害してしまう。しかし、次第に罪の意識が増長して苦悩するようになる彼は、自分より壮絶な生活を送る娼婦ソーニャの自己犠牲の生き方に心を打たれて変わっていく――
犯罪や死に関する本を読んでいると母はその思考回路を心配するが気にしすぎであるとエマは思っている。本や音楽、映画などの創作物は人の人生を変えたり、救ったり、価値観を変えたりとさまざまな影響を与える。人が一から作ったものはそのくらい重みがあるのだ。
しかし、それをきっかけに母が心配するような犯罪行為をする人間はごくごく一部にすぎない。少なくともエマはそんなつまらないことはしない。理不尽な社会に抗おうと何か行動を起こすなら、もっと別の――たとえば彼らと同じように何かを残す方法をとる。誰かの記憶に残るには、形あるものを残さなきゃ意味がない。
罪と罰は上中下と三冊にわかれているようで、ひとまず上巻を手にする。なかなか分厚い。読めるか不安だが、無理ならすぐ返してもいいとマキノは常々言っているのでそうさせてもらおう。
そろそろ教室に行かなければ予鈴が鳴ってしまう。カウンターで手続きをしてもらうため、体を反転させた瞬間。
「わっ!」
正面に大きな影ができていた。そこに思いきり顔をぶつけてしまう。なんでこんな近くに人が、と思うより早く手首を掴まれたエマはぎょっとしてその相手を見上げた。
「サボ……」
「脅かすつもりはなかったんだが、エマが急に振り返るからおれも驚いた」
「びっくりしたのはこっちなんだけど」
「悪かったって」
昨日話しているうちにわかったことだが、彼はポートガスやルフィよりも学校に来ている日数が多い。勉強もきっちりやっているというから素直にすごいと口にしたのに、毎日真面目に通ってる奴に言われてもなァと苦笑された。どうも基準がポートガスなので二人も同じように思ってしまう(ルフィはサボとポートガスの中間くらいだそうだ)。
手首を離してくれたサボは、エマが図書室に入っていく姿を見てついてきたらしい。
「放課後のことなんだが、前にお前が覗いてた東校舎の――」
「ちょっと! だからその言い方やめてってば」
「はは」
悪びれたふうもなく楽しそうにしているサボに恨みがましい視線を向ける。くそう、イケメンだからって何しても許されると思うなよ。と胸中で悪態をつきつつ、けれど満更でもない自分がいる。
昨日、練習とやらに二時間ほど付き合ってサボとはそのままライブハウスで別れた。そのときポートガスたちはバイトをしていたらしいが、学校にいる時間帯からやっているなら学校に行けばいいのにと思わなくもない。学校に来ない理由がバイトなら高校生として大問題だ。他校の人と喧嘩というのはまったくの嘘であるが、不良なのは間違いない。
そんなふうにしてサボとはだいぶ打ち解けたように思う。ポートガスに比べたらはるかに話しやすい雰囲気だし、物腰柔らかで紳士的なところもある。かと思えば、今みたいに意地悪い面も持ち合わせていて掴めない人だ。
今日はルフィが休みでポートガスは来ているらしい。二人で来いよ、と言って彼は先に図書室を出ていった。
……って言われてもなあ。ポートガスってクラスでは誰とも接触しないまま一日を過ごす強者なんだけど。
思案にふけっていると、マキノの注意を促す声が聞こえてエマは慌てて本をカウンターに持っていった。そのときタイミング良く――いや、悪く予鈴が鳴ってしまい、そのあと二分ほどして教室に入ったエマは案の定遅刻扱いになった。どこのクラスか知らないが、原因ともいえる金髪の男に恨みの念を送った。
*
人気のない東校舎も放課後になると活気あふれる場所になる。怪しい文科系の部活が活動を始めるからだ。
各教室がある南校舎から移動してきたエマは、想定通り先に行ってしまったポートガスの後を追いかける形で向かっていた。期待はしていなかったが、まさか本当に先に行くとは。彼の懐に入り込むには相当距離を縮めないといけないらしい。
南校舎と繋がるほうから廊下を通って端の階段へ。その際、例の文科系部活の部室をいくつか通る。科学部や落語部、鉄道研究部、クイズ研究会。わかる。深海生物部、コンビニ研究部、文通部、ガロア理論研究部。わからない。何をするんだ一体。コンビニ研究部の部室を通り過ぎたとき、「陳列棚が」とか、「在庫品の」とか怪しい会話が聞こえた。……聞かなかったことにする。
前回は見つからないようにこそこそしていたが、今回は堂々と屋上手前の踊り場までのぼるとサボたちはすでに地べたに胡坐をかいて待っていた。
「話ってなんだよ」
エマが来るなり、ポートガスは低くそして不機嫌全開に呟いた。どうやら虫の居所が悪いらしく、今日は仲間のサボに対してもぶっきらぼうだ。
そして話は昨日、サボと別れる直前のこと。話したいことがあるから明日の放課後残ってくれと言われたのである。こうして言われるまま東校舎に来たわけだが、ポートガスのほうも知らないらしい。
「七月に控えてるライブで新しいことをやろうとしてただろ? そこにエマをゲストボーカルとして呼びたい」
「……」
「……」
サボの発言のあと、踊り場はしばし沈黙に包まれた。ぽかんとするエマとは対照にポートガスは眉間にしわを寄せて胡坐に頬杖をついている。
聞き間違いでなければ、サボはエマに一緒にステージに立って歌えと言った。一体どうしてそんな話になるのだろう。まさか昨日ちょっと演奏に合わせて歌っただけでそう判断されたのだろうか。確かに昔から音楽は好きだし、歌も得意か不得意かでいえば得意なほうに入る。だが、所詮は素人の歌だ。客を引きこむほどの歌唱力があるかと問われると否である。サボは綺麗と褒めてくれたけれど、でもきっとそれだけじゃダメだ。
「サボ。冗談も大概にしろ」
「おれが冗談でこんなこと言うと思うか?」
「こいつ歌えんのかよ」
「昨日偶然テウで会ったから練習に付き合ってもらったんだ。そこで聴いた」
「おれは納得いかねェ!」
二人の応酬にエマはどう入っていいのかわからず、立ち尽くしたまま会話の行く先を見守る。しかしどう見てもポートガスが首を縦に振ることはなさそうだ。
「エースの言いてェことはわかる。けど、おれは本気だ」
「はっ、そうかよ」
吐き捨てるように言って、ポートガスは脇目も振らずに去ってしまった。あ、とエマが声をかけようとしたがすでに背中は見えなくなっていて、右手が中途半端な位置で停止したまま、まるで時が止まったかのようにしばらく動けなかった。