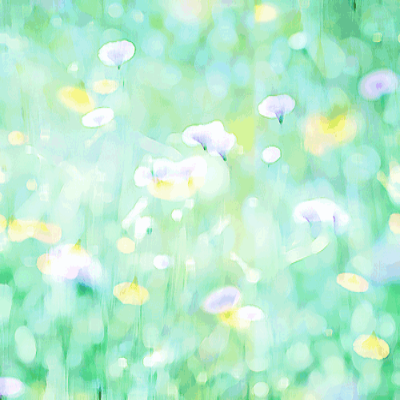
旗を振れない少女
こういうことはいつも突然始まり、突然終わりを迎えるということを知っている。それまでのことを忘れてしまったように、当然のように肩を叩かれ声をかけられたことにエマは戸惑った。
五月のおわり。エミたちと約一か月もの間、離れて過ごし感じたことは孤独であることは虚しいということだ。クラスでは相変わらず腫れ物扱いだし、高原たちと話すのも必要最低限でグループには混ざっていないし、何かと班行動が多い学校生活はエミたちからハブられる。シマモトも隙を見てはねちねち注意をしてくるし、母の遠慮がちな視線にも嫌気がさすし、おまけに大事なものはエマの部屋から消えてしまった。
正直良いことなんてなくて、やるせない日々なのだけれど。自分と同じかもしれない人たちに出会って、息苦しい場所から少し浮上した気がしている。エマだけが良いと知っていることを、彼らも同じように良きものとして――さらには自ら創り出す側として存在している。母にもエミたちにも決してわからない世界を。
光のささない深海を泳いでいるような、暗くて前が見えない場所に彼らは突如としてあらわれた言わば「道標」だ。ようやく、何かを掴みかけたと思った。それなのに。
エマおはよう。
今の自分に声をかけてくる人といえば、仲間に引き入れようとする高原たちくらいだが、声のトーンが異なる。それ以前に、彼女たちはエマのことを呼び捨てにはしない。
振り向くより先に、横に並んできた彼女がエマに微笑みかけてくる。思わず鳥肌が立った。それは彼らの音楽を初めて聴いたときの高揚感とは正反対の、悍ましさで恐怖を感じたときのそれだった。どうして、急に……?
「……」
固まって動けないでいるエマに気づいているのかいないのか、エミはやはり笑顔で「昨日の見た?」と例のアイドルが出ていたらしいバラエティ番組の話を振ってきた。見ているわけないし、そもそもそのアイドルに興味がないし、第一エミはエマと喧嘩していることを忘れてしまったんだろうか。彼女の中で、この一か月の出来事がなかったことになっている。
聞きたいことが山ほどあるのに、エマの口から出たのは自分でも驚く一言だった。
「見てない。昨日は忙しかったから」
「そうなの? まあいいや。今日は数学二時間もあってダルいよねー」
「そうだね……」
違う。ほかに言うことあるでしょう。なんで急に話しかけてくるのかとか、リカたちはどうしたのかとか。なんで私は普通に話してるんだろう。そして、それに対して心のどこかで安心している自分に一番腹が立った。エミの冷たい視線をもう浴びなくて済むと思うと安堵のため息がもれる。
呆然としながら受け答えするエマに少し不審な顔をしたエミは、今思い出したように「ごめんね」と一言告げた。
こんなことを、卒業までにあと何回繰り返すのだろう。孤立するのはどうしもなく虚無感に駆られるが、それ以上に表面的な付き合いを続けるエマたちの脆くて頼りない友情のほうが虚しさを積もらせる気がした。
結局、何も変わっていないのだと自分に絶望する。
教室に入って席についたとき、その異変にすぐ気づいた。班ごとに固まっていることもあってエマの席はエミたちと縦に続いている。エマ、リカ、エミ、リン。ここ一か月、後ろ三人で楽しげに会話をしていたはずだがなぜか今日リカの席を素通りして二人はエマのほうへやって来た。そこで察する。次のターゲットがリカであるということを。
理由は一限目の選択授業である美術のときすぐに判明した。昨日の昼休み、エミたち三人でトイレに行ったときのこと。用を足したあとも手洗い場でいつものように話し込んでいたらしい三人は、高原が一人でトイレに入ってきたという。そこまでは別に普通の日常のひとコマであって、リカが無視される理由にはならない。問題はそのあとだった。
『高原っていつも一人でトイレに行くよね。本当は友達いないんじゃない?』高原がトイレから出ていってすぐ、エミの嘲笑的な発言が女子トイレに響いた。
きっとリカだって、あのとき――エマがぽろっと思うまま口に出してしまった帰り道のときのように、思わず言葉がこぼれただけなのだろう。本音は意図せず漏れ出ることがある。
『別にトイレくらいいいんじゃない、ひとりでも』エミが毎回誰かとトイレに行くことを知っている側からすれば、この発言は失言だと気づく。リカも口にしてからすぐに失言だと気づいただろう。しかし一度口にした言葉はなかったことにはできない。
エミが無言でトイレを出ていくのを、リカはどんな思いで見送ったのだろう。想像するに難くない。
*
選択を迫られていた。ローファーを出したままエマの下駄箱は開きっぱなしで、しかし履きかえることを許さない瞳が四つ。エミとリン。二人に囲まれ、今後のエマの方針を聞かれた。バド部の非活動日、最近の癖からひとりで昇降口に来てしまい、まさか一緒に帰ろうと声をかけられるとは思わずにたじろいだのだが。
「どうなの、エマ」
「どうって言われても……」
「まさか、リカを擁護するつもりじゃないよね?」
「……」
方針も何も、勝手に始めて勝手に終わらせたのはそっちだろう。大体、ごめんの一言で済ませてあとは何もなかったみたいにされるのもよく考えれば都合がよすぎる。話しかけられたから受け答えはしたものの、こちらから話しかけた覚えはない。
朝の安堵感はどこへやら。うんざりした。エミの暇つぶしに付き合うのは。きっと、今回のことだって気づけばまた終わっている。しばらくは四人で一緒にいるけど、似たようなことが起きたらグループから誰かがはじき出される。それはエマかもしれないし、リカかもしれないし、リンかもしれない。エミ以外の誰か。歪になった関係はきっともう修復できない。
しかし面と向かってエミにそう言えるだろうか。学校と家しかないエマに孤独が再び訪れるということは、部活だって気まずいままあと一年と数か月続けなければならない。そんな生活に耐えられるだろうか。母とのことだって、解決したわけでもないのに。
エマの心は揺れていた。エミとのばかばかしい関係に嫌気がさしつつ、けれど"そこ"しかない居場所を失う怖さ。どっちを取ればいいんだろう。
「エマ、答えて」
「おい、邪魔だ」
エミの剣幕が、横から聞こえたそれによって一瞬和らいだ。
三人で一斉に視線を向けると、そこにいたのはものすごい不機嫌なポートガスだった。確かに今日登校していたのを知っていたが、ホームルームが終わると同時にすぐ出ていったのでもうとっくに帰ったとばかり思っていた。
彼の負のオーラを感じ取ったエマたちは、言われた通り塞いでいた下駄箱から距離をとって譲る。しかしポートガスは、自身の下駄箱を開けたる直前になって手を止め、くるりと振り返るとエマたちに鋭い視線を向けた。思わずたじろいで、構えてしまう。
「お前ら、くだらねェことしてるな」
重く低く響いたその言葉は、『お前ら』と言われたのになぜかエマだけに向かって言われたような気がして、心が急激に冷えていくのを感じた。ただでさえ、あのことがあって気まずいままなのに、彼とさらに距離ができてしまった気がする。