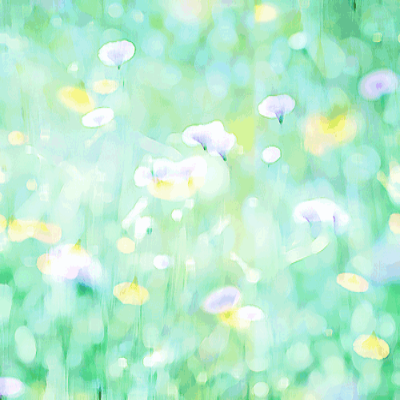
寄り添う少年S
夕方の河原は今日も変わらずジョギングする人、サッカーや野球をする小学生たち、犬を連れた老人などさまざまな人が行き交っている。エマのようにただ座ってぼうっと川の流れを見つめている人間はいない。今、何時だろうと思いながら、向こう側に見える夕日に目をやる。視界がぼやけていた。そっと頬に手を添えると、自分が泣いていることに気づいてやるせなくなる。
ポートガスに一刀両断されて呆然としたまま帰り道を歩いたが家に帰っても自己嫌悪に陥るだけだと思ったエマは、河原に来ることでその気持ちを落ち着かせようとした。しかし、一向には晴れてくれない。燃えるような橙に近い赤に、ますます自分の不甲斐なさを思い出して涙が止まらなかった。
彼に言われたこともそうだが、何より自分がそうだとわかっていて決断を迷ったことだ。少しでも安易なほうに走ろうとした自分が恥ずかしくて言い返す言葉もない。エミたちも何を言われたのか咀嚼するのに時間がかかっていたようでしばらくその場に立ち尽くしていたが、我に返って憤慨したように二人で出ていった。
どうしてすぐに断らなかったのだろう。今さら何を思っても後の祭りとはいえ、あのときの自分に戻れるならエミに堂々「嫌だ」と主張したい。クラスにおける居場所なんて、もう気にしたって仕方ないのに馬鹿みたいだ。
「あれ、もしかしてエマ?」
体育座りをして俯いているエマの後ろで、思わず耳を塞ぎたくなるような甲高い急ブレーキ音が聞こえた。涙でぐしゃぐしゃになった顔をゆっくり上げると、自転車に乗ったサボが不思議そうにこちらを見ていた。
「うわ、サボ!? なんでっ、ここに……」
「おれ? おれはこれからライブハウスで練習だよ、あいつらと待ち合わせ」
「そうなんだ……」
はっきりと顔を見られてしまった今、涙を拭っても意味のない行為だが念のため――というより体裁を整えるため頬に滴る涙を乱暴にふき取った。
その様子に何かを察したらしいサボは、自転車を降りてエマに近寄ると「なにかあったのか? 話くらいなら聞いてやるよ」優しく尋ねてくる。身から出た錆なのに、優しくしてもらう資格なんてないはずなのに、サボはポートガスより<エマに対して最初から柔和な態度でいてくれていた。それがひどく嬉しくて、冷え切った心の奥が段々と温かくなっていく。だからこそ、サボには正直でいたいと思う。
「私、酷いことをしようとしてたんだ」
*
練習に行く途中だと言っていたサボは、何も言わずにエマの話を最後まで聞いてくれた。同じクラスではない彼には、そもそもエマたち四人の歪な友人関係を話さなければならなかったし、現在のエマの立場も説明する必要があったが、一切の相槌を打たずに耳を傾けてくれていた。
夕方の土手に二人並んで、けれどお互いの体は真っ直ぐ川に向かっているので目線が合わない分、話しやすい状況だった。サボが乗っている自転車が地面と平行にぺったりくっついている。つまり斜めの方向に傾いた状態だった。上に停めておけばいいのに、どうやら値の張るクロスバイクらしく盗まれないように目の届くところに置くのが習慣なのだという。
「なるほどな。あいつは自分に正直な奴だから、そういう陰でコソコソしたことが嫌いなんだ。誤解されやすいが、本来は仲間想いの良い奴だよ」
「うん……あれは私が全面的によくなかったってわかってるし、保身に走ったのがポートガスには見え見えだったんだと思うから」
エミたちのことを自分とは違うと線引きしておきながら、結局独りになるのが怖くて楽なほうに進もうとした。その場しのぎだとはわかっていても、クラス替えのないこれからの二年間を思えば、学校生活が中心のエマにとってそれがすべてになる。
三人のように、学校の外で自分たちだけの世界を築いているわけではないのだ。言い訳と言われてしまえばそれまでだが、ライブハウスに行きづらくなってしまった今、エマの居場所は学校と家の二つのみ。みっともないと思われてもそれがエマの現実であり、でもだからこそ変わらないことにうんざりして絶望する。相反する心は常にどっちつかずだった。
「それで泣いてたのか。なんか女ってのは随分と大変だなァ」
「前のことといい、サボにはかっこ悪いところばっかり見られちゃうね……」
「んーけど、なんでも一人で抱え込む必要はないんじゃねェのか?」
話し始めてからようやくサボがくるりと体の向きを変えて、エマと視線を合わせてきた。
「……え?」
投げかけられた言葉の意味を解釈できず、数秒沈黙してもう一度聞き返す。
「だからさ、エマにはもうほかに居場所があるだろ?」いたずらが成功した子どものようにサボが笑った。それはとても柔らかく、まどろむ春の陽気みたいな暖かみのあるものだった。とくん、とくん。また心の奥底が温まった気がする。
何も返せず口をぽかんと開けた間抜けな顔を見て、今度は可笑しそうにしているサボがさらに続けて「そういえば」とリュックから何かを取り出した。
「これ」
渡されたのは透明なケースに入った一枚のCD。けれど、一般的にショップで売られているそれとは違い、書き込みで利用するような真っ白い表面のものだ。そこには油性ペンで「エマ」と殴り書きされている。
私の、名前……?
「どういうこと?」
「そのままだよ。エマに歌ってほしくて書いたんだ」そう言うや否や、自転車を地面から立て直した彼はそのまま土手をのぼっていく。
「あ、ちょっと……!」
「じゃ、おれは練習があるから。明日にでも感想聞かせてくれよ」
「えー……そんな勝手な……」
エマの呟きも虚しく、サボはお洒落で高価なクロスバイクにまたがり、颯爽と遠ざかっていった。