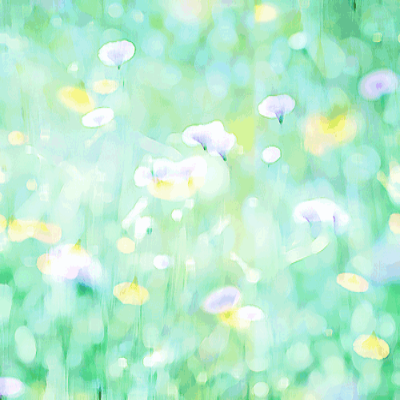
FLAG
半ば無理やり渡された一枚のCDを手に呆然としていたエマは、我に返って仕方なくそのまま帰宅することにした。嵐のような出来事に、気づけば涙も引っ込んでいて学校でのことが夢だったのではないかと思えるほどだった。
西日に向かって歩きながら地平線を眺める。昼と夜をつなぐ空には、もう夜の帳が下りはじめていた。問題はなに一つ解決していないのに、エマは心が少しだけ軽くなっているこに気づく。エミたちのこともエースのことも、どうすればいいのかまだわからないけれど、エマがエマである限り、答えは自分で見つけなければいけない。
玄関を開けたら、珍しく父親のくたびれた革靴がすでに脱ぎ捨てられていた。どうやら今日の帰りはいつもよりだいぶ早かったらしい。ただいま、といつものごとく聞こえるか聞こえないかの小さな声で呟くとそのまま階段を上がって自分の部屋へ向かった。背中越しに母の「おかえり」という声が聞こえた気がしたが、相変わらず母とも冷戦が続いている。
鞄を放り投げてベッドに座り込むと手にしたままのCDを見つめた。ケースを開いて自分の名前が書かれた箇所をそっと指でなぞる。
"エマに歌ってほしくて書いたんだ"
サボの言葉が耳の奥でリフレインする。いつの間に、こんなものを作っていたんだろう。曲を作るなんて、それ相応の時間や労力が必要だろうに。ましてやサボはエースに比べて学校に来ている日数も多いはずなのに。そう思ったらなんだか早く聴かなければいけない気がして、エマは机の隣に置いているコンポにCDをセットした。部屋に残っているCDと呼べるものがもうこの一枚しかないことに虚しくなりながら、サボが自分のために作ったというそれ。
エマは、震える手で再生ボタンを押した。
*
音楽をかけていたはずの部屋がいつの間にか無音であることにしばらく気づかなかった。あまりの衝撃に打ちのめされ、どうやら微動だにしないままベッドの上で呆然としていたらしい。はっとして、CDを取り出そうと立ち上がる。その拍子に、何かが床へ落ちていくのが視界に映った。
あ。頼りない自分の短い声が空気に溶ける。ふと、その何かが落ちた先に目を向けて動転した。フローリングの硬い床に、はっきりと綺麗な円を作った雫。その正体を目にして、エマは初めて自分が泣いていることに気づいたのだった。
取り出しマークのボタンを押してCDを抜き取る。表面に書かれた自分の名前に再び触れた瞬間、まるで走馬灯のようにサボとのやり取りが思い出された。
分かり合おうとする必要はないと言ってくれたサボ。踏ん張れと背中を押してくれたサボ。なんでも一人で抱え込むことはないと言ってくれたサボ。学校にも家にも居場所がないと思っていた自分に、ほかに居場所がある――ここにいてもいいと笑ってくれたサボ。
エミたちと感性が違うことに優越感を抱きながら、結局は何もない自分が嫌で、けど認めたくもなくて。ライブハウスにいるときだけが、自分は特別なんだってそう思えた。だからポートガスたちのような、本当の意味で自ら世界を築いている人間を見て、衝撃と動揺と興奮、そして嫉妬が入り混じった感情を抱いたのだ。羨望の眼差しとはよく言うが、きっと初めて見たときから三人に対する想いは変わらなかった。憧れにも似たこの感情を持て余して、どう処理するべきか迷っているところにいろいろなことが重なって、追い打ちをかけるようにエミから選択を迫られた。
心のどこかで、いつかはやめなきゃいけないとわかっていた。エマたちがやっていることは、ターゲットが変わるだけで終わりがない。本当の友情なんて考えること自体中二病っぽい気もするが、間違いなくエマたちの間に友情などという純粋かつ尊い関係性は存在していない。エミたちがどう考えているかは別として、少なくともエマの中では成立していなかった。だから、本来であればいつ関係が崩れてもおかしくない状態ではあったのだ。
"自分に革命を起こせ"
サボが作った曲はすでに詞もついているのか、彼自身の声が音源になっていた。
そのうちの一節に綴られている言葉。心を見透かされているようだった。どうして、わかるんだろう。サボとはクラスも違う、ましてや知り合って一か月と経たない。それなのに、まるでエマに立ちふさがる壁が見えているかのような詞に心が打ち震えた。立ち上がれと言われているような気がした。私は私を変えなければならない。
こぼれた涙を無理やり拭って、決意する。
「サボ、ありがとう。私は私を変えるよ」
もう、迷ったりしない。