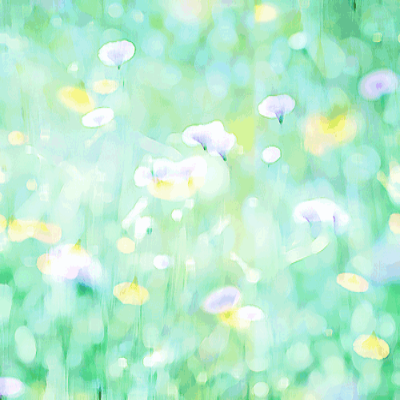
決意の朝
ひとしきり泣いたあと、そのまま疲れて眠ってしまったらしいエマは白んできた空を目にして慌てて起き上がった。夕飯を食べなかったどころか、制服のままで横になったせいでブラウスがしわくちゃだ。スカートにも微妙に癖がついてしまっている。
とりあえずブラウスとスカートに関しては替えがあるから良いとして、急いでシャワーを浴びることにする。さすがにこのままで学校に行くのは無理がある。
風呂場へ向かうのに一階へ下りると父も母もすでに起きていた。父はともかく母とは気まずいままだが、間に一人いるだけで雰囲気はだいぶ柔らかくなるらしい。
「おはようエマ、今日は早いな」
「うん……昨日、帰ってそのまま寝ちゃったみたいで」
父は、母と娘の張りつめた空気をどことなく感じ取っているのかあえて何でもないように振る舞っている。気を遣わせて申し訳ないが、こればかりはエマにも譲れないものがあった。両親に世話になっている身ではあっても、中島エマというひとりの人間として存在する限り、誰にもエマのアイデンティティを否定する権利はない。
シャワー浴びてくる。と一言残したエマは、母のぎこちない視線をやり過ごしてダイニングを後にした。
脱ぎ捨てたブラウスと下着類を洗濯機に詰め込んで風呂場に向かう。汗でべっとりとした気持ち悪さを取り払って、昨日の夜の決意をもう一度反芻した。
独りじゃないと暗に伝えてくれたサボの言葉に応えるために、エマがやるべきことは決まった。まずはエミたちに昨日の選択の答えを打ち明けることだ。くだらない探り合いも、エミを気づかって合わせる空気づくりも。もう同調することはない。エミがこの歪な関係に気づいてくれるかどうかはわからないが、本当にエミと友人でいたいならリカもリンもエミに対して態度を改めるべきだ。
そしてポートガス・D・エース。得体の知れないクラスメイトの素顔を垣間見て印象が変わり、もっと知りたいと思った人。彼を通して、同じバンドを組む仲間の二人とも知り合いになったが、自分の卑怯な部分を見られて、ただでさえ遠かった距離がさらに遠のいてしまった。せっかく近づけるチャンスだったのを、自ら手放すような真似をして、きっと彼にはエマが不誠実な人間だと映っただろう。まったくをもってその通りだから言い訳ができない。エミに対する不満を抱えながら、見て見ぬふりをし続けた結果が”今”なのだから。
けれど、不安や恐れはもうエマの中から消えていた。ポートガスのバンド仲間が作った、たったひとつの音楽によって。
彼の名前はサボ。ポートガスとは同じ中学出身らしいが、どうやら幼少期からずっと一緒にいるという。太陽に反射する明るい金髪に、ロールアップしていた制服のズボンと骨ばった腕が印象的な彼は、思えば最初からエマに対して好意的な態度をとってくれていた気がする。光の届かない深海の中で、さまよっていた自分の道標のような存在となった彼らの曲に惹かれ、気づけば追いかけるようになって。そんな三人の中で、サボは唯一話しやすい男の子だった。ポートガスは他人を寄せつけないし、もう一人のバンド仲間のルフィは一つ下の後輩なのでそもそも会う機会が少ない。どうしたってエマが関わりを持てるのはクラスメイトのポートガスか同学年のサボになる。なかなか心を開いてもらえないポートガスとは違って、サボとはプライベートな話もしたことを思い出し、かあっと頬に熱が集まった。
その熱を隠すようにシャンプーをおえて、体も洗い終えたエマはさっと新しい制服を着込む。ブラウスは市販のだったが、スカートは指定されたうちの一つ。ありがたいことにエマの通う高校は制服のバリエーションが豊富だ。女子はリボンのほかにネクタイもあるし、スカートは二種類あって気分によって変えられる。カーディガンもベストも自由なので、組み合わせによって何通りにもなるのがこの高校の制服だった。
着替えとヘアスタイルを整えてダイニングに戻ると、父の姿はなくなっていた。母がエマの食事の準備をしていたので、定位置に座って待つ。相変わらず二人の間にはピリピリとした空気が漂っているが、エマの心は穏やかだった。捨てられてしまった宝物は戻ってこないけれど、もう無理に母を説得しようとは思わなかった。無理して分かり合わなくてもいいと言われてから楽になったのだ。
そんなエマの様子を感じ取っているのか定かではないが、何か言いたげな表情でちらちらとこちらを見ていることは知っている。だから、今日こそエマははっきりと告げる決意をしていた。朝食を持って席につこうとした母を見据える。
「お母さん。私は、大事にしていたものを勝手に捨てられたことは許してない。どんな理由があったって、持ち主の許可なく捨てることはダメだよ」
「……そう、ね」
「それからお母さんが好きだっていうアイドル、私は興味ないの。私の好きな音楽はもうわかってるだろうけど、お母さんがきっと好きになれないジャンルだと思う。でも、お母さんが嫌いでも私は好きだから」
そう、お母さんが好きなアイドルを私が好きになれないように。それぞれに好きなもの苦手なものがあって、周りの評価ももちろんあって。誰からも愛される音楽も本も映画もないだろう。称賛する者がいれば、批判する者もいて当然。世の中はそうやってできている。
けれど、それが相手を傷つけていい理由にはならないし、言葉はいつだって凶器になることを忘れてはいけない。自分の常識だけにとらわれて見失わないでほしい。
「つまり、何が言いたいかっていうと、人にはそれぞれ好きなものが違うし価値観もいろいろあるっていうことを知っていてほしいの」
「……」
「すぐには理解できないかもしれないけど、分かり合えないかもしれないけど……否定することだけはしないで」
エマの言葉に母は反応を示さず、ぼうっとしていた。どう捉えたかはわからないが、必死でかみ砕いているように見えた。
言いたいことを伝えられたエマは母の様子が気になりながらも、朝食に手をつけて胃の中へ運んでいく。今日もまた朝から丁寧なメニューで、こんな頑張らなくていいのにと悪態をつく。フレンチトースト生地にチーズやハムなどが挟んである――名前があったような気がしたが、エマは興味にないことには極端に記憶力を発揮できない質なので覚えていない。
そのあとも母は心ここに在らずといったふうに、エマが話しかけても小さく頷くか首を振るかのどちらかで会話は成立しなかった。自分の言葉がよほど衝撃的だったのか、ショックだったのか。彼女の心情はわからなかったが、きっと言葉自体は届いたのだろう。事態がどう転がっても、エマに後悔はない。
朝食を終えたエマはそっと席から立ち上がると、母に行ってきますと告げた。
*
学校について真っ先にポートガスの姿を探した。けれど、教室にいないのを見て今度はサボを探すことにする。彼ならポートガスの予定を知っているかもしれない。そう思って、一度教室を出たエマはほかのクラスを見て回ることにした。
そういえば、しかしサボのクラスを知らないことに気づいて辺りをきょろきょろしていると、偶然にも前から歩いてくる金髪がいるではないか。向こうもエマの姿に気づいたようで眠そうな表情が明るくなる。
「こんなとこで何してんだ?」
「サボを探してた。今日、ポートガスは? 学校に来る?」
「ん? ああ、どうだろうな。昨日の時点では何も言ってなかったから来ると思うけど」
「そう……」
「もしかして、聴いてくれたのか?」
「……うん」
エマはゆっくり頷いた。ポートガスに自分の想いを伝えることばかり考えていたが、もとはと言えばその決意をさせてくれるきっかけを作ったのはサボだ。先に伝えるべき相手は彼かもしれない。
「あの、えっと……その、ありがとう」
「なにが?」
わかっているくせにしらばっくれるとはいい性格をしている。それに、口元が笑っているのから全然隠せていない。隠す気もないのかもしれないが。落ち込んでいるエマに居場所があると言ってくれた彼はこの上なく優しい眼差しだったはずなのに、どうしてかにやにやと楽しそうにしていて居心地が悪い。
「だから、それはっ。昨日くれた、あのCDのこと……」
面と向かって言うのが恥ずかしくて俯くと、「冗談だって。わかってるよ」と腹を抱えてからからとやっぱり楽しそうに笑った。「サボの意地悪!」わかってるなら聞かないでほしい。詩を作ったり、歌うことが得意なエマは、けれど自分の気持ちを伝えるのが苦手だ。だからこそ歌うことが好きなのかもしれないが。しかし、伝えることを放棄したらいけないときがあることもわかっている。
「大丈夫だ。あいつならわかってくれるよ、エマが誠心誠意を込めて伝えてやれば」
と、いつかのようにくしゃっと頭を軽く撫でた。