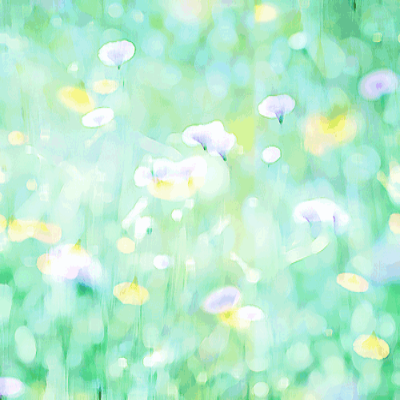
少年Aと和解
サボの来ると思うという予想は確かに当たっていたのだが、ポートガスが学校に来たのは五限目も終わる頃合いだった(五限目の終わりに学校に来る意味を知りたい)。
そうして寝てばかりの彼がホームルームを終えて帰っていこうとするのを「ポートガス!」と大声で呼び止めた。本人だけにとどまらず、クラス中が何事だとエマに視線を送る。それもそうだろう。一匹狼のポートガスに声をかけるなど、クラス替えしてから誰一人としてしたことがない。噂が独り歩きして、彼に話しかけることは禁じられた行為だという不文律ができていたからだ。
驚愕と好奇に満ちた複数の視線を無視するように教室を出ていくポートガスの後を追ったエマは、その大きな声にあからさまに不機嫌な顔をした彼の目を真っ直ぐに見つめた。
「話があるんだけど」
誰とも仲良くしないポートガスも、面と向かって言われたらさすがに無視はできないのか渋々「東校舎に来い」と命令した。話があるのは私なのに、なぜそんな偉そうな態度なのか。昨日の負い目もあるエマに強く言う権利はないかもしれないが、ポートガスの態度はもう少し人と距離を縮めようという努力があってもいいはずだ。
例の怪しい部活でにぎわう東校舎の廊下を横断して、屋上に続く踊り場まで来たポートガスはくるりと振り返るとエマに鋭い視線を向けた。
「話ってなんだよ」
世間話をするとかそういう前置きが一切ないのは予想通りだったが、本題に入るのが早すぎてエマは口ごもった。
サボに背中を押してもらい、昨日誓った決意は揺るがず灯火のように今もエマの心の中にあり続けている。ポートガスにもそれを聞いてもらうために今日この場で伝えると意気込んだはいいものの、いざ本人を前にすると切り出し方がわからない。
そもそもポートガスとは初めて会ってから一度も会話がきちんと成立した覚えがなかった。視線が定まらず右に左にさまよう。
「話がねェんならおれは帰る」
「あ、ちょっと待って。言いたいことがっ」
横を通り過ぎようとしたポートガスのワイシャツの袖を掴んで引き止める。突然のことによろけたものの、運動神経がいいのか踏み止まった彼はエマの顔をじろっと睨んで「なら早くしろ」としびれを切らした。ぶすっと口を尖らせていて相当機嫌が悪いらしい。これは一刻の猶予も許されないかもしれない。
「私……もう、やめることにしたから」
「……あ?」
「昨日みたいな見かけだけの、友情ごっこ。ポートガスの言う、"くだらねェ"こと」
あれだけ躊躇っていたはずの口は、開いてみれば簡単に次から次へと思いのたけを言葉にしていく。掴んでいた袖をそっと離すと、ポートガスはちゃんと話を聞くつもりなのか階段に座った。相変わらず仏頂面ではあるが、きちんと話そうとする人間をないがしろにするような人でないことは仲良くなっていなくてもわかっている。
サボが言うように、自分にも他人にも正直な人なのだろう。それでいて、サボとルフィという唯一無二の友人がいる彼には余計に曲がったことをしているように映ったに違いない。エマの事情など彼には知る由もないのだから。
一つ下の階では楽しげに笑う各部活の様子が伝わってくる。エマも階段に腰かけて、誰もいない階下の廊下を見下ろす。ポートガスと同じ段に座る勇気はなくて数段下だけれど。
「エミの機嫌を損ねると私たちのグループはつまはじきにあうから、みんな意識して話に乗っかるのよ。でもそんなの上っ面だけだよね、思ってることが言えないなんて。でもクラスでの居場所がなくなるのが怖かったし、部活も同じの私にはひとりぼっちになるほうが正直になることよりすごい怖いことだった」
エマが生きる世界はそれほど狭くて窮屈だ。自分が良いと思っているものを共有できる人間がいなくて、それがもどかしいようなけれど優越にも似たような感覚で満たされていた。でもそう思っていたのは、ただの思い過ごしだったのだ。本当はちっとも満たされてなどいないし、ただ虚しさだけが積もっていって残ったものは何もない自分。
唯一息のできる場所だったライブハウスも母には見つかって、集めていた大切な宝物は捨てられてしまう始末。かろうじてライブにはこっそり行っているのだがその回数は明らかに減った。母から問いただされるのが鬱陶しいということもあって、今のエマは学校と家の往復という一般的な生活を送っている。
それは偏に彼らの存在があったからなのだが、ポートガスの前で言うのはなんだか負けた気がするのでひとまず自身の決意表明にとどめておいた。
語り始めてから、相手に気持ちを伝えることが改めて恥ずかしく感じていたエマはちらっとポートガスを盗み見た。膝頭に肘をついて眉をひそめながら戸惑ったような、でもおれに言ってどうするのだとでも言いそうな顔をしていた。どうするって……どうするつもりなんだろう?
「それをおれに言ってどうすんだよ」
実際口に出されるとどう返していいのかわからなかった。
ポートガスは徐に立ち上がったかと思うと、そのまま階段を下りていく。上履きの規則正しい音とともに遠ざかる背中を、エマは呆然と見つめている。怒っているような気もしたし、呆れているような気もした。今更なにを言ってるんだと、咎められているような。
伝わったのかそうでないのかわからず、階段を歩くポートガスに声をかけようか迷う。どうするつもりなんて考えてなくて、ただただ彼に思いを伝えたかった、それだけなのだから。
「けどまァ、その根性だけは認めてやる。お前の事情は知ったこっちゃねェが、流されない生き方ってのは簡単なようで難しいからな」
自分の信念がありゃァ人は強くなるもんだ。
下りきった先で一度足を止めて振り返ったポートガスは得意げにそう言ったあと、エマの返事を待たずに消えていった。返事など元から求めているわけではなく、捨て台詞だったのかもしれないが。
しばらくぽかんとしていたエマはポートガスの言葉をかみ砕くのに数分ほどかかり、やがて沸々とお腹の底からマグマのような熱を持った塊がわきあがる感覚に手が震えた。