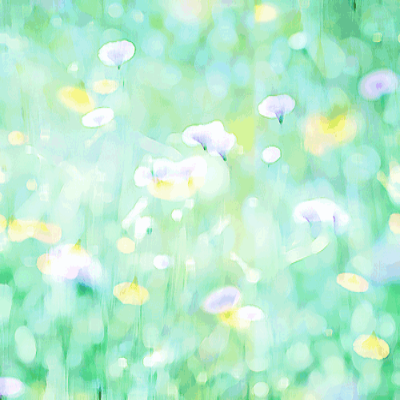
そして、少女は旗を振る
かつてフランスを救った聖少女、ジャンヌ・ダルクはこう言った。
"何者であるかを放棄し、信念を持たずに生きることは死ぬことよりも悲しい。若くして死ぬことよりも"
百年戦争でイングランド軍に攻められたとき、神のお告げを聞いた彼女は十六歳で先頭に立って戦い、フランス軍を勝利に導いたという。白銀の甲冑を身にまとい、オルレアンを解放したことでも有名な彼女の言葉はエマの心にも響く名言が複数あった。
これもそのうちのひとつ。教科書に書かれた彼女の生き様を指でなぞりながら、先生の説明を聞き流していた。なぜか二時間連続して世界史だというエマのクラスは、二コマ目の後半戦に突入してバタバタと机に突っ伏す人数が増えてきている。目を開けているのは真面目なグループと思考が別次元に飛んでいるエマくらいだろう。先ほどから中世の説明を一生懸命している世界史担当教師は、クラスの半分が聞いていないにもかかわらず律儀に授業を進行している。
――であるからして、ジャンヌ・ダルクはフランスの英雄となったのですがイングランド軍に捕まってしまい、異端者として十九歳という若さで火刑に処されたのです。
黒板に「火刑」と書いた先生はチョークを置いてクラスを見渡した。堂々と寝てる人間もいれば、気持ちよさそうに舟を漕いでいる人間もいる。そうした光景に盛大なため息をついて時計をちらっと見やると、では残りの時間はワークシートを埋めてくださいと告げたままこちらに干渉しなくなった。
細くて眼鏡の気弱な雰囲気なので普段からあまり生徒を叱らないタイプだが、時には強く注意することもしなければ教師としての威厳がなくなってしまう。まあ授業中の居眠りは自分の首を絞めるだけだから先生の知ったことではないだろうが。
ともかく終了チャイムまでの十五分間は各自でワークシートなので、エマはさっさと終わらせると周りと同じように机に突っ伏した。
騒がしいなと思って目を開ければ担任のシマモトが連絡事項をつらつらと述べているところだった。いつの間にか怒涛の世界史時間は終わっていたらしく、けれどエミたちから起こされないあたりこの前のことがうやむやになっているせいだろう。リカは一人でぼうっとしているが、エミとリンは仲良く喋っていた。シマモトの話も半分以上が聞いてないから、エマ一人が寝ていたって気づかれない。それに、エマをいびることに飽きたのかどうか知らないが、最近のシマモトは特別こちらに何かしてくるということもなかった。
騒がしいままホームルームがおわるのを確認し、上体を起こして帰る支度を始める。今日は部活があるなと思いだして憂鬱になりかけたが、先日のポートガスとのやり取りを反芻する。
"見かけだけの、友情ごっこはもうやめる"
"流されず、自分の信念を持てば人は強くなる"
ここはスタートラインだ。エマはまだ踏み出したばかりで、これからそう生きようとしている。狭くて暗い世界は、けれどポートガスたちに出会って自分に正直になることを教えてくれた。分かり合えなくてもいいということ。こんな自分にも、新しい居場所ができたこと。ポートガスと仲良くなるにはまだ少し時間がかかりそうだけれど、あの日の彼の言葉はエマの胸にしっかりと刻まれている。
荷物を整えたエマは体育館に向かう途中で呼び止められて、しかしなんとなく予想していたことでもあったので怯むことなく彼女たちに向き合った。
「どうするか決めたの?」
エミは相変わらず高飛車な感じで直球に聞いてきた。少し前までだったら、この絶対的な存在には蛇に睨まれた蛙のように逃げることも立ち向かうこともできなかっただろう。頷いているほうが楽で、失う場所もない。エミのターゲットにならないことは、学校生活における平穏を意味していたから。
隣に立つリンはエミにまるで寄り添うようにくっついている。少しも疑おうと思っていない曇りなき目で、エマを見つめている。でもリン。これは、本当は間違ってるのよ。誰かをはじいた友情なんて最初から友情でも何でもない。
「私は……エミたちに賛同しない」
「は……? ごめん、もう一回言ってくれる?」
「聞こえなかったの? 私はもう、そういうのしないって言ったの」
ポートガスに言われたことなど覚えていないとでも言いたげな涼しい顔が歪んでいく。エマの答えに納得がいかないのか鬼気迫る勢いで詰め寄ってきた。
「それがどういうことかわかって言ってるの?」
「仲間に入れてもらえないっていうならそれでもいい。私はもう、そんなくだらないことしないって決めたから」
「はあ!? 調子に乗ってんじゃないわよ!」
エミが手を振り上げて、パシッとエマの頬をひっぱたいた。頬を叩く音なんて漫画の中でしか知らなかったが、随分と良い音が鳴るものだと他人事のように思った。じりじりと痛む患部を押さえながら、何でもないようにエミを睨みすえる。
廊下は二年の教室が並ぶ人通りが多いところなので、険悪な雰囲気を感じ取った周りの人たちは巻き込まれないよう避けて通り過ぎていく。しかしこういうとき、人は他人の諍いに好奇心をくすぐられてしまうものでちらちらとエマたちをうかがう視線が感じられた。
興奮しているエミとは正反対に、エマは始終冷静な面持ちで状況を判断していた。恐れるものがないとは、こんなにも心が軽くなるのか。今のエマはジャンヌ・ダルクのように、信念を宿した強くて勇敢な戦士だった。
「気は済んだ?」
努めて冷静な、何でもないよう装っているエマの態度は、エミの神経を逆撫でする一方でわなわな震えているのがわかった。でもそれでいい。やり返したり、逆上すれば相手の思う壺だろうから。何も言わずに成り行きを見守っていたリンは、けれどエマの行動に信じられないものでも見たような目を向けて驚いていた。
「じゃあ部活あるし、もう行くから」
このあとの部活を思えば、二人の返事を待つくらいのことはしてもよかったかもしれない。バドミントン部の活動はこれからも続くし、エマの学年はエマたち含めて五人しかいないから。現状リカが孤立しているとはいえ、エマとのことを聞けばすぐ元通り三人とエマという構図に戻るだろう。
だが、心のもやが晴れていくように気分は爽快だった。エマは鼻歌まじりに体育館へ向かう。その後姿を呆然と見つめるエミたちがいることなど、エマは知る由もない。
*
六月に突入すると雨が多くなるものだと思っていたが、今年はどうやら違うらしい。週間天気予報を見ても晴れマークが並んでいたし、くずれてもにわか雨程度だというから不思議だとエマは思う。
都会でも――かといって田舎というほどでもないこの町は、今日もにぎわっていた。高校から坂を下りると大きい通りに出るのだが、商店街並みにいろいろな店が軒を連ねているので人通りが多い。部活を終えた午後六時過ぎでも、行き交う人の数は昼間と変わらないかもしれなかった。
エマが向かっている先は河原だった。大きい通りを横切って、川に続く細い道を進む。
案の定、部活ではエマ一人が輪から弾かれたが運よく三年生が今日は奇数という理由で、三人グループを作っていた先輩が気を利かせてエマと組んでくれた。二年の事情にはあえて深く追求してこず、エマに対して常に明るく接してくれたことには感謝以外ない。
河原に向かっている理由は、サボから連絡をもらったからだった。
"部活終わったらいつもの河原に来いよ"
理由もなにも書かれていないシンプルなメッセージは彼らしい。いま向かってる、とこちらも短く返信して歩いている。
明日からのクラスの立ち位置がどうなっているのか、不安がないといえば嘘になる。この先もクラス行事は複数あるし、席替えはあってもエマが仲良くしている女子はエミたち以外にいない。自然と孤立することは目に見えている。しかし、そうした不安要素があってもエマの心が揺るがないのはそれ以上に彼らの存在が占めているからだった。
細い道を抜けて土手沿いの車道に入る。横断歩道を渡れば、見慣れたいつもの河川敷。そこには予想通り三人組が地べたに座って談笑していた。ルフィは後輩な分、学校で見かける機会はないが、相変わらず仲が良いようで楽しそうだった。サボがエマの姿に気づくと手を振って合図した。同時にポートガスもルフィもこちらを振り返る。
「よう、お疲れ」
「ありがとう。部活おわってから気づいたから危なかった」
サボが少し左に避けてスペースを作ってくれたので、エマも三人に倣って座った。サボが乗っていたクロスバイクは三人で同じ車種なのか、すぐそばに三台とも置かれていた。オレンジ、青、赤のドクロシールがそれぞれ貼ってあるからそれが目印なのだろう。
サボとルフィはいいとして、ポートガスに会うのは東校舎でのこと以来だった。エマに対して多少認めてくれた部分はあるようだが、どことなく距離を感じてしまう。まあいきなり馴れ馴れしくするポートガスというのも想像できないけれど。
納得いっていない彼は置いておいて、ここに呼ばれた理由はなんだろう。エマは問いかける。
「で、私を呼んだ理由はなに?」
「単刀直入に言うと、やっぱりエマに出てほしいんだ」
「出るってなにに」
「前に話しただろ? 七月のライブの話」
「七月、ライブ…………ええええ!?」
「うるせェな」
思わず叫んだら、右隣にいるポートガスが迷惑そうな顔をした。でも仕方ない。誰だっていきなりライブに出てほしいなんて言われたら間違いなく叫ぶ。
「あれって結局ナシになったんじゃ――」
「三人で話し合ったんだ、もう一度」
サボがリュックから取り出したのは一枚のCDで、表面に書かれた文字に見覚えのある単語があった。
"FLAG"
それは、サボがエマに作ったという曲の中に何度も出てくる単語だった。胸に秘めた感情をぶつけるように、心が叫ぶように。ひとりの少女が自分に革命を起こす歌。勇敢に立ち向かう姿は、まるでそう――ジャンヌ・ダルクを思わせる。
そういえば、サボはこの歌をエマに歌ってほしいと言っていた。けれどそれは個人的なことであって、ライブとかそういう公式な場ではないと思っていた。
「む、無理だよ! 前にも言ったでしょ。私は歌うのは好きだけど素人だし、ちゃんとしたバンドを組んでる三人と一緒になんてお客さんにも失礼だし」
「みんな最初は素人だ」
「そ、それはそうかもしれないけどっ」
そういう問題じゃない、という言葉をのみ込んでエマは項垂れた。話し合ったということはルフィもポートガスも了承したのだろうか。あの、おれは断固反対とか言っていたポートガスが? だとしたらどういう風の吹き回しなんだろう。彼の中であれから心境の変化でもあったのだろうか。
しかし考えてもわからなかった。戸惑いを隠せず、でもとかだってとか言い訳ばかりを絞り出そうとしてしまうエマに横から「ごちゃごちゃうっせェなァ」と暴言を吐かれて肩を竦める。え、と思う暇もなくがっしり肩を掴まれたエマは瞠目と不安な目をその人物へ向けた。そばかすが特徴的なポートガスだ。
「サボがお前の歌を聴きてェって言ってんだ。ルフィは最初っからこの調子だし、おれだけ反対してもしょうがねェだろ? だから、おれを認めさせてみろよ。中島エマ」
ぐいっと顔が近づけられる。さながら凄みをきかせたヤンキーのような表情でポートガスがそう言った。脅迫に近い発言に返す言葉を失ったエマは、さらに「いいな?」と確認させられて断る余地もないまま事が進んでいく。呆気にとられるエマを気にするふうもなく、サボもルフィも大笑いしていた。なんだ、この三人。
「無茶言うなあ……」独り言を呟いたつもりが、「あいつなりにエマのこと気にしてると思うぞ」と耳打ちするようにサボがこっそり教えてくれた。「ふうん」素っ気なく返したのに、サボは嬉しそうだなァと意味ありげにニヤニヤするから恥ずかしくなって訂正してしまった。そんなんじゃない。
でも私の名前知ってたんだ。と今更ながら些末なことに気づいて、あの日と同じように熱を持った何かが静かにお腹の底からわきあがってくる感覚におそわれる。
サボにはそんなんじゃないと言ってしまったけれど、この感情は――嬉しいんだな。まだ全然遠いポートガスとの距離は、けれど少しずつ確実に縮められているのだ。なら、もう少し踏み込んでもいいだろうか。たとえばそう、まずは――
「ねえ。エースって呼んでもいい?」