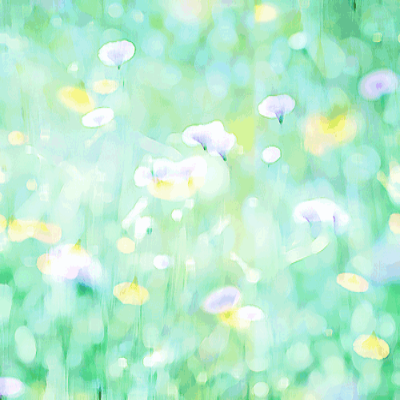
ふたつの正解
どのくらい走ったのだろう、バド部で鍛えている体力はすでに底をつきそうだった。
学校ではシマモトからクラス全員の前で恥をかかされ、部活をサボって家に帰れば母から自身の大切にするものを処分したと言われる始末。一体エマがなにをしたというのか。世の中は随分と自分に厳しい、などと悲劇のヒロインぶりたい。
そろそろ肺が苦しくなってきたところでエマは一度足を止めた。どうやら町の中心部まで来ていたらしく、地元の人々が多く行き交っている。休日はこのあたりで遊ぶことが多いのだが、今の時間帯はほとんどが部活をしているので学生は少ない。とはいえ制服姿の子たちがまったくいないわけではないからエマが浮くということもなかった。
とぼとぼ行くあてのないまま歩く。思えば鞄を放り出して家を飛び出してきたせいで財布がない。かろうじてポケットにはスマホがあるが、優秀な端末も今は頼りにならなかった。帰宅部の友人がいないエマはこういうとき頼る人間がいないことに気づいて急にやるせない気持ちになった。
――私って本当に何もないんだな……
虚しさでまた鼻の奥がつんとしそうになり慌てて首を振った。ここで泣くのは目立ちすぎる。
繁華街から少し離れると個人経営の変わった店が立ち並ぶ区域になる。学生では入りづらい場所もあるし、逆に若者であふれる店もある。エミたちとよく行くのは宇宙カフェという、店内がプラネタリウムみたいになっているところでこの辺では有名なカフェである。
そんな中で、誰もが気づかなそうな小さくて黒地に黄色で"テウ"という文字が書かれた看板がかかった複数のテナントを持つビルが存在する。地下へ続く階段はビル内の奥にさりげなくあるので、ここがまさかライブハウスだとは夢にも思わないだろう。ライブがある場合は外に宣伝の看板を出しているのだが、掲示板のタイムテーブルを見た限り、今日は特に予定がないらしい。
無意識に足がここへ向いていたようで苦笑する。一人のときはたいていここに来ているせいか、自然とたどり着くのはライブハウスになってしまう。そもそも財布がないのだからカフェには入れないし、知り合いに見つかりたくないという理由ではここがもってこいの場所だろう。
「といってもな……ライブがない日に来たことないし、ダダンさんいたら入れてくれるかな」
「なにしてんだ?」
階段付近でうろうろ怪しい動きをしていたエマに、突然後ろから声がかかった。人通りが少ない上、ましてやライブ予定のないライブハウスの入口で誰かに話しかけられるとは思っていなかったので「ひゃあ」悲鳴をあげて猫のように後方へ飛び退いた。
急に声をかけてくるなんて、とその人を恨みがましく振り返ったエマは、しかしその相手を捉えた途端目を丸くした。
「え、なんで?」
「それはこっちの台詞なんだが……まァ細けェことはいい。お前も来るか?」
*
当たり前のように階段を降りてライブハウスの中へ入っていくポートガスの仲間のサボは、勝手知ったるといったふうにスタッフ(ダダンさんはいなかった)へ軽く挨拶をするとそのままステージにあがっていった。
来るかと問われて反射的に頷いてしまったエマは一緒についてきたはいいものの、どうすればいいのかわからず立ち尽くしてサボの背中を見つめる。
あ。掠れた声が出る。サボの背中にギターケースがあった。いま初めて気づいたことだが、彼は制服姿でそれを背負ってきたようだ。鞄もあるところを見ると学校から直接来たのだろうか。いや、でもギターが目立ってしまう。
サボは慣れた手つきでステージ上のアンプと呼ばれる機械をいじったあと、自身のギターを取り出してケーブルに繋いでいく。まさかひとりで演奏でも始めるつもりなのか訝しげに様子をうかがっていると、その視線に気づいた彼がこっちへ来るよう手招きした。
「練習」
簡潔にそれだけ言うと、ステージの床に座り込んでギターを弾きはじめた。昨日聴いた音と寸分違わぬ、けれどひとつのパートだけが一本の線になってエマの耳に届く。これはライブでも演奏していた曲だ。もらったCDにも入っていた海をうたった曲――とエマは解釈している。
海を渡るひとりの少年の物語。どこかにあるという楽園を探す旅に出た少年は、クジラやクラゲといった生きものたちとともにふわふわと波に乗って果てない大海原へ繰り出す。
気づけばエマは、彼の音に合わせてそのメロディを口ずさんでいた。彼らの曲は昨日の夜からずっとエマの脳内で再生され続けている。詞は覚えていなくても音は体の中に確かにあって、心が弾んでいくのがわかる。乗ってきたエマに気をよくしたのか、サボのほうも声に合わせてくれている気がした。昔から耳だけはよく、一度聴いた音楽は頭の中で楽譜がほぼ出来上がるエマはこうして誰かの演奏に合わせて歌うことに憧れていた。楽器はできないけれど、歌うことはできる。
ほどなくしてアウトロに突入すると同時にうまく帳尻をあわせて音が止んだ。今まで息継ぎを忘れたかのように、空気をいっぱい吸い込んでゆっくり吐き出す。
「お前の声、綺麗だな」
「えっ」
「昨日聴いたばっかりだろ、この曲」
「うん。でも帰ってからCD流してて、今日もずっとあなたたちの曲が頭から離れなかった。一度聴いたものは頭の中で楽譜が作れるから」
「そう、なのか」
エマの言葉に驚いた表情をしたサボは、しかしすぐに笑顔になってすごいと褒めてくれた。今まで披露する機会がなかったために、こうして手放しで褒めてもらうのはなんだか照れくさくて素っ気なく返してしまう。エミたちとカラオケに行ったって、歌うのは彼女たちに合わせた曲ばかりで好きな音楽を歌うことはないし、そもそもエマが歌おうと思っている楽曲はきっとカラオケには入ってない。
なんとなくサボとの間に気まずい雰囲気が流れつつあったのを、彼は何事もなかったかのように話題を変えてきた。
「で?」
「……?」
「なんでこんなとこに一人でいるんだよ。今日はライブねェだろ?」
夢中になって、ここへ来た理由をすっかり忘れていたエマはその質問にどう答えるべきか悩む。正直に言ったところで身内とのいざこざなど他人の知ったことではないだろう。それに処分されたCDの中にはきっと彼らのも含まれている。不可抗力とはいえ、昨日の今日でそんなことをされたとわかったら気分が悪くなるに違いない。当たり障りのない程度で説明することにしたエマはステージに背を向けた。
「お母さんとケンカしたの。あの人、私の好きな音楽を否定するようなことを言うからついイラッとしちゃって」
「それで家を出てきたってことか」
「情けないけど……うん」
俯いて尻すぼみになる。テカテカと反射する床に、自分のシルエットがぼんやり浮かんでいた。
世界の価値観は日々変わっていくというのに、いつまでも同じ場所を漂っている母が気に食わない。自分が正しいと思うもの以外はすべて良くないと勝手に決めつける。私は絶対あんなふうになりたくない。
「まァ世の中いろんな奴がいるからな、そうしたぶつかり合いってのはよく起こる。お前はまだ両親に世話になってる身だが、自分のことくらい自分で決められるだろ。だったら、別に分かり合おうとする必要はないんじゃねェか?」
ギターをケースの上に置いたサボが、立ち上がってステージを降りてきたかと思うとエマの隣に並んだ。背が高い分、近い距離での会話は首を少し上に向けなければならない。あらためてまじまじと見てみると、ポートガスと同様女子にモテそうな顔をしている。それでバンドって、もう訳が分からない。エマのクラスの様子からしてバンド活動は学校に秘密にしているのだと思うが、バレたらきっと大変なことになるだろう。学校中の女子が押し寄せてしまう。
ああ、そうだ。エマは河原で彼らを見かけた少し前の出来事をいま思い出した。
図書室から出たときぶつかった金髪は、この人だったのだ。あのときはすぐに横切っていき後ろ姿しかわからなかったが、思えば髪型も背丈もそっくりだ。
「高校卒業したら親元を離れる奴も多い。一度距離を置いてみたら見えてくることもあるだろ、だからそれまではここで踏ん張れ」
頭上に重さを感じた。サボの左手がエマの頭に乗っかって、くしゃっと撫でていった。呆然とその仕草を見つめながら、ナチュラルにこういうことができるなんて、やはりモテる男の所業。ギターを弾く長細い指がエマの髪に触れたとき、むずむずとした感覚が身体を駆け巡って自分の体なのに得体の知れないものに支配された気分になった。
そして思い出したかのように今更、おれはサボと名乗るものだから、もうエマの感情はぐちゃぐちゃでよくわからなくなった。突っ込む気も起きなくて、代わりにこちらも名乗る。あまりにも和やかな雰囲気で、気づけばエマは母との確執を忘れてサボと話し込んでいた。