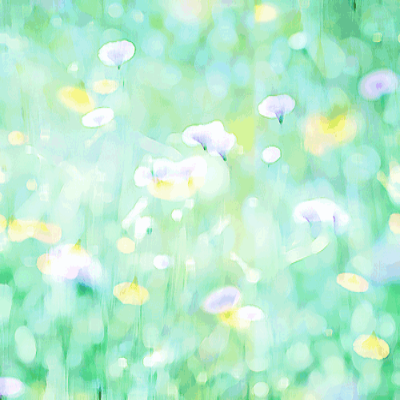
マザーズ・プレジデス
連休明けの朝、眠い目をこすって起き上がる。昨日の興奮が冷めずなかなか寝つけなかったのだ(それどころか、こっそりCDを流してヘッドホンをしたまま眠ってしまったらしい)。
歯磨きをして顔を洗って制服を着る。映画『レオン』のヒロイン、マチルダを真似したショートボブは忙しい朝でもオイルを使えば整えるのが比較的容易だ。髪にクセがないエマはボブカットがよく似合う。いつものように手櫛とオイルで綺麗にセットし、そのままダイニングへ向かって軽めの朝食をとる。勤め先が遠いせいで、エマより一時間半も早く家を出る父はすでにいない。母が優雅に紅茶を飲みながら本を読んでいるだけだ。
集中して聞いているわけでもないテレビから朝のニュースが次々に飛び込んでくる。ネット詐欺の話、どこかで起きた殺人事件の話、若い世代に流行っている食べ物エトセトラ。世の中は、思っている以上に速いスピードで過ぎていく。その中で、どれだけの人が世間に跡を残せるのか。
ふと、高校生という単語が耳に入り、エマはパンに向けていた視線をテレビに移した。
それは男女の高校生がいわゆる愛を確かめ合う場所に来て補導されたというニュースだった。自分と同じ年齢の、けれどどこか別の場所に住む人たち。名前も顔もわからない、でもきっと学校で噂になってしまうことは容易に想像できる。可哀想だなと思う。そんなことで、自分という人間を世間に晒してしまうなんて。高校生の性事情などエマには知ったことではないが、もっと何か方法がなかったのか。そういう意味では、エミやリカはうまくやっているのだと思う。
「近頃の高校生ってそうなの? エマたちの学校も、こういう感じなの?」
「さあ……」
いつの間にか本から顔を上げてニュースの内容に表情を曇らせていた母は、どこかの高校生に憤慨しているらしかった。母のいう"こういう感じ"が事実かは別として、きちんと同意の上でやることはやっている高校生は一定数いるだろう。
「エマは大丈夫だと思うけど、気をつけてね」
「気をつけてってなにを?」
「だからそれは……付き合うとかそういうことよ」
「高校生なのに?」
「もちろん、エマの見た目は可愛いと思ってるけど……それとこれとは別でしょう? エマはこの子たちとは違うって信じてるから」
母の言葉がまるで呪いのように感じられた。どうして母は娘があの子たちとは違うと思うのだろう。高校生なら好きな人や付き合っている人がいるのはおかしいことではない。むしろ自然なことだ。実際のところ、エマにそういう相手はいないのだが、母が無条件に自分を恋愛しない人間だと決めつけていることに対して腹が立った。
お母さん、私は確かにああいう場所には行ったことないけど、ライブハウスに一人で通ってるんだよ。煙草もアルコールも溢れかえる場所に。それでも信じてるなんて言える?
朝から母に幻滅したエマは朝食を残してそのまま席を立った。
「食べ終わってないじゃない」
「いらない」
ぶっきらぼうな言い方になったが構うものかと食器を洗い場に置いた。残ったものはゴミ箱へ。もう一度歯磨きをするために洗面所へ向かおうとすると「エマ」咎めるような声で呼びとめられた。
「なに」
「最近変よ」
「変ってどこが」
「だって、前はもっと本の話とか音楽の話とかいろいろしてくれたじゃない」
「そんなの中学生のときまでだよ! 私もうお母さんがいうような本も音楽も好きじゃないから!」
母の制止を振り切って洗面所とは反対の方向――玄関へ一直線に向かうとそのまま家を出た。
*
ただでさえ母のことでむしゃくしゃしているのに、それは数学の授業でのことだった。
シマモトの授業は相変わらず説明と問題の繰り返し。もちろん数学だから、公式などの理論が必要なのは理解できる。しかしシマモトはその導入の仕方に問題があるとエマは思っている。数学が苦手なリンのような生徒に、いきなり公式を説明したところでさっぱりだろう。そういうものだと呑み込めるエマとは違い、身近な事例や興味をひくものがなければ数学の理論ほどつまらないものはない。
世の中はあらゆるところで数学が使われているが、そのほとんどは知らなくても生きていけるし、生活するのに困らない。だから数学なんて四則演算ができれば問題ないと豪語する者もいる。実際にそうかもしれないが、数学の本質は答えにたどり着くまでの過程が大事であって、そうした思考はこの先役に立つのだ。
与えられたものから最適なものを選び取って組み立てていく。従来の方法と新しい方法。従来の考えと新たな考え。価値観は変わるものだし、いつまでも古い考えに縛られているとがんじがらめになって自分を追い詰めることになる。
そんなことを考えながらぼうっとしていた。だからシマモトの説明がすでに終わっていることも、名前を呼ばれていることにも気づかなかった。みんなの視線が一斉にこちらを向いていた。
「中島、先生の話を聞いてたか」
「……」
「聞いてたならわかるよな? 先生が言ったこと復唱してみろ」
ねっとり絡みつくような視線だった。例えるなら獲物に狙いを定めた蛇。内職はしていない。けれどシマモトの説明は右から左へ聞き流していたから、何を言っていたかはわからない。
しんとする教室で、シマモトの声だけがクリアに届く。この前のように助け舟を出してくれたポートガスは今日来ていない。ほかのクラスメイトはわざわざシマモトの反感を買うことはしない。苛々する。
「中島」
「……ません」
「聞こえないな」
「すみ、ません……聞いてませんでした」
「先生の話はちゃんと聞かないとダメだろう。気をつけなさい」
「は、い」
にんまりと気持ち悪い笑みでエマを見たシマモトは満足そうにすると授業を再開した。何がちゃんと聞かないと、だ。お前の説明がつまらないのを私のせいにするな。
エミたちと仲間割れをしているせいでただでさえクラスで腫れ物扱いなのに、シマモトがそれに拍車をかけた。そのあと、無心になって授業を受け続けたエマは、ホームルームが終わると同時に誰に挨拶することもなく教室を飛び出した。部活は休むほかない。
バド部の活動日なのに早く帰宅したことをなんて言い訳するか考えていたエマは、けれど玄関を開けてすぐ母が待ち伏せするようにそこに立っていることに驚いた。様子がおかしい。どうしたのかと問う前に、じっとこちらを見つめて何かを決心したように口を開いた。嫌な予感がする。
「エマ。お母さんはエマがちゃんとしてて真面目に学校も行ってて、だからそういう心配は必要ないと思ってたけど……」
「……」
「テウってライブハウスは、煙草とかお酒とか扱っている場所じゃないの?」
ああ。見られたんだ。クローゼットに隠していた箱の中を。いつ? 今日私が学校に行ってる間? それとももっと前から見つかってて、今日の朝のことがきっかけで? 頭の中は混乱していた。もう何も考えることができなかった。ただ、自分が大切にしていた宝物を穢された気分だ。
せめてもの抵抗としてこの人の前では絶対に泣かないと目に力を入れる。
「ねえエマ。どうしてあんなところに行くようになったの? エマが好きなのはお母さん一緒でアイドルじゃなかった?」
母の純粋に心配しているという顔が憎らしかった。まるで悪いと微塵も思っていない、本気で心配しているだけだという顔。
一体いつの話をしているのだろう。人の好みなど変わっていくというのに。いつまでも母と同じものが好きだとどうして思えるのか。この人の思考回路を想像して背筋が凍る。
「あんな訳のわからないアーティストを聴いてどうするの? 歌詞もなんだかよくわからなくてお母さん怖いから、エマには悪いと思ったけど、その……CDをね――」
「まさか捨てたの?」
「捨てたっていうか、まあ処分したっていうか」
「それは捨てたってことでしょ! ひどい、勝手にそんなことっ……」
「ごめんね。でも前はもっといいものを聴いてたでしょ、だから」
いいもの。あんたの言う"いいもの"ってなんだ。
反論する気も起きなかった。奥歯をかみしめて沸々とこみ上げる怒りを必死に押しとどめる。悔しい。この人には何を言ってもわかってもらえない。分かり合えない。もうどうでもいい。
通学かばんを玄関に投げ捨てると、エマは踵を返してもう一度玄関扉を開けた。
「どこいくの」
「どこだっていいでしょ、お母さんには関係ない!」
呼び止める声を振り切って走り出す。どこにいくかなんてそんなの知らない。でもここではない、どこかだ。
走りながらエマの頭の中は、自分の唯一の心の拠り所だったクローゼットの箱が占めていた。コツコツとためていたCDにチケット。あれは、訳のわからないものなんかじゃない。それぞれのディスクには、彼らの築く世界が存在して、エマを現実から遠ざけてくれる不思議な、それでいて強力なものだ。母なんかにわかるわけがない。
口の端に何かが伝った。少ししょっぱい。涙だった。
一度こぼれるとどうやら止められないらしく、次から次へと頬を伝ってくる。
けれどエマは走り続けた。まだ明るい空の下、制服を着た女が泣きながら走っている姿は周りにどう映っているのだろう。そんな些末なことを考えながら、エマは走り続けた。