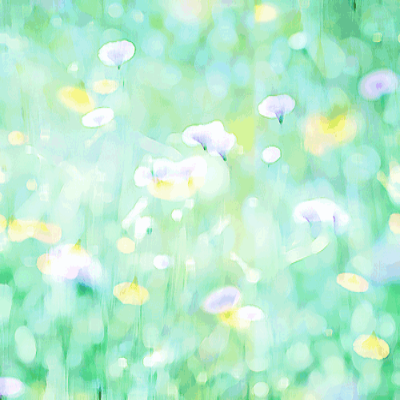
そうして世界を築く
そこにいたのは紛れもなくエマのクラスメイトであるポートガスと、あの日彼と一緒にいたサボとルフィという男だった。最初こそなぜ彼らがここに、という思いが頭を混乱させたがひとたび曲に聴き入ってしまえばあとはもう何も考える余裕などなかった。
人は本当に感動したとき、言葉を失うのだと思う。彼ら三人が生み出す音、発する声と空気感。そして旋律と歌詞。教室でいつも寝ているだけのポートガスがまるで別人だった。髪を振り乱さんばかりの弾きっぷりと、その拍子で飛び散る汗が。心臓を掴まれる、その音に。
気づけばステージの近くまで来ていた。瞬きを忘れるように、ただその姿を目に焼きつけるように。ポートガスだけではない、ほかの二人も音楽というものに真摯に向き合い”好き”が溢れていることが伝わる演奏だった。それは羨ましいほどに、彼らだけの世界がそこに存在していた。
何かに夢中になる。それはエマが持ち合わせていないものだから。
*
すべてのバンドが演奏を終えてもそのまま解散ということは少ない。インディーズバンドはCDやグッズなどの即売会を公演終了後に行う。特に対バンの場合、新規顧客を獲得する可能性もあり、初めて聴いた客がCDを購入していくことがあるからだ。その例でいくと、エマはまさに今日この場でクラスメイトが結成しているバンドに見事心を奪われたわけである。とてつもない悔しさがこみ上げてくるが。
終了後のCD即売会は可能な限り、出演者本人が行う場合が多い。これもインディーズの良さだとエマは思っている。直接本人にライブの感想や想いを伝えることができるのだ。
ポートガスたちも同じようにして立っているのでエマは列に並んで順番を待っていた。CDを買う目的はもちろんあるが、ほかにも言いたいことがある。
エマは前で列に並んでいた――この会場ではちょっと浮いているおじいさんが、彼らと親しげに話していた。親しい間柄のようだが、それを通り越して「ジジイ」だの「ふざけんな」だのなんだか物騒な言葉が飛び交っていて周りのスタッフが宥めている。三人の誰かの身内だろうか。
考えていたところで、おじいさんが列からはずれていよいよエマの番になった。自分の顔を見て彼らがどういう反応をするのか、どくどくと脈打つ心臓を落ち着かせながら彼らの目の前に立ったエマは、しかし肝心の同じクラスであるポートガスが例のおじいさんといまだに話し込んでいて拍子抜けする。
――別に今じゃなくてもいいけど。
拗ねるように唇を尖らせたエマは視線を床に向ける。あ、お前と叫んだ声が聞こえたのはそのときだった。その声に顔を上げて目の前の人物を対峙する。金色の髪がライブハウス特有の薄暗い照明に透けてきらきら反射していた。
「いつかの覗き魔」
「ちょ、違う! その呼び方やめてください。別に覗いてたわけじゃ――」
言いかけて口ごもる。あれは覗いていたことになるのだろうか。ポートガスを追いかけたつもりが、ほかに二人も合流するという仕方ない状況になってしまったとはいえ。
隣にいる黒髪も思い出したみたいで「あのときの変な奴」と指をさされた。どうやら彼らの中でエマは覗きをしていた変人になっているらしい。ほぼ間違っていないが、一部間違っているので訂正しなければならない。
「あのときはごめんなさい。ポートガスがどこに行くのか気になってついていっただけなの。実は私、それよりも前に楽器を練習するあなたたちを河原で見かけたことがあって……今日は本当に偶然だけど、話をしてみたかった」
エマの言葉に金髪の彼の目が見開かれる。今の台詞のどこにそんな驚いたのかわからなかったが、得心したように隣でまだ言い合いをしているポートガスを呼んだ。なんだよと振り返った彼は、サボが指し示すこちらに顔を向けて心底驚いた顔をする。
なんでお前が。小さい声でそんなふうに言ったと思う。サボから耳打ちされて同じように目を見開く動きをしたポートガスは、けれど訝し気な表情を向けた。
「事情はわかった。あと三十分待ってろ」
一方的にそう告げると、早くどけという仕草をしてエマを列から避けさせた。流れるままはじき出されてしまい、もう次の客に対応する彼らを見て諦める。エマは、まだ目的のものを買えていない。
ずっと会場にいるのも怪しく思われるのでライブハウスから出た目立たない場所で待つことにしたエマは、きっかり三十分後に出てきた彼らを、待っている間に買ってきた缶ジュースで労った。
高校生が外でバンド活動するにはいろいろ制限があり、その一つに夜十一時を過ぎてはいけないというのがある。学校にほとんど来ない(サボとルフィはわからないがたぶん一緒)彼らが律儀にそれを守っているとは思えなかったが、見つかった場合は活動自粛せざるを得ないので守るほかない。
同じ高校生だというのに背中のギターケースが妙に似合う三人組である。
「ほらよ」
「えっ」
「買えなかったんだろ?」
言いつつ渡されたのは一枚のCD。確かに買えなかったのだが、気づいていたとは思わなかった。まあ買えなかったというより、買わせてもらえなかったのほうが正しい気もする。
鞄から財布を取り出そうとしてポートガスに制止された。首を傾げるエマに彼は「その代わり教えろよ」と鋭い目つきで訴えてくる。
「あの日、どうしておれたちの会話を聞いてたのか」
「それは……」
「言えねェのか?」
「そういう、わけじゃないけど……」
「じゃあ言え」
「おいおいエース。お前女に手厳しくねェか?」
怒っているような態度のポートガスに、サボが肩を掴んで宥めようとする。あのとき盗み聞きするつもりがなかったとはいえ、彼にとっては気分のいいものではなかったのだろう。ここで誤魔化したら、もう二度と彼らとは関われない気がしたエマは、正直に自分の想いを吐露することにした。
「知りたかったから」呟いた声は少し震えている気がして頼りなかった。でもここで止めるわけにはいかない。エマはそのまま続ける。「あの日、河原でギターを弾く姿を見て気になったの。学校にほとんど来ないあなたが、どこでどんな日常を送っているのか、何を考えているのか。まあそれは、今日答えがわかったんだけど」
エマがライブハウスに通うのは音楽や歌が好きという理由のほかに、学校と家に本当の居場所がない自分を違う世界につれていってくれるからというのがある。あのままエミたちと一緒にいれば平和に過ごせるのかもしれないけれど、自分に何もなく終わるのが嫌でたまらない。あの子たちとは違う、そう思いたくて――
学校に来ていない彼らが、しかしここではステージに立って輝いている。学校でもなく家でもない、自分たちだけの世界を築いているということ。それがひどく羨ましかった。
「私、あなたたちの曲がすごく好きみたい。ライブ鳥肌立った。今日はありがとう、あとこれも」そう言ってCDを見せてから「じゃあ私はこれで、また学校でね」三人の反応を見るのが怖かったエマは一方的に思ってることを伝えてその場を去った。
彼らがそのあとどういう会話をしたのか、エマには知る由もないが、この日を境に平凡な日常が少しずつ変化していく。