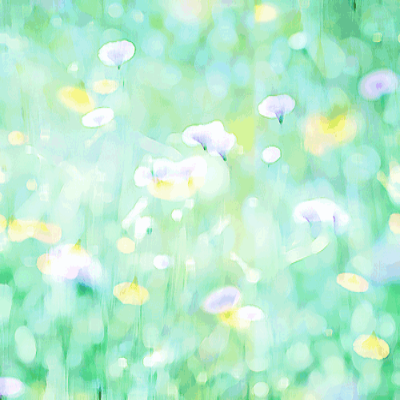
東校舎にて、再会
ゴールデンウィーク前、最後の登校日。少しずつ陽射しに蒸し暑さを感じるようになってきた頃、校門前にある坂をえっちらおっちら登るのは運動部といえどつらく感じるものだ。そのため、運動部のトレーニングとしてこの坂はよく使われる。かくいうバドミントン部のエマも一年の頃からいろいろな意味で世話になっている。
校則によれば自転車通学も可能らしいが、この坂を自転車で登ろうという強者は相当体力に自信のある者だけだろう。もちろんエマには無理な話だ。
二年の教室は地上六階建て校舎のうち三、四階に位置する。クラス数は十と意外に多く、一から五は四階で六から十が三階。エマは六組なので二階分登ることになる。朝のチャイムが鳴る前の廊下は騒がしい。教室をまたいで会話する生徒が多いので、自習スペースも今は女子たちで埋まっていた。
「エマっ!」
階段を登りきってすぐ駆け寄ってきたのはリンだった。どうしたのだろう、エミと一緒にいなくていいのかと要らぬ心配をしてしまうあたりエマは少しお人好しなところがある。
「どうしたの」
「えっと……その、この前のこと……」
「この前?」
「シマモトがっ……」
シマモト。その名前で倫理の時間のことを言っているのだとすぐに思い当たった。どうしてリンが気にするのかと訝るが、よく考えたらシマモトがエマを目の敵にした原因にリンも関わっていることを思い出して納得する。
リンはエマたち四人の中でも主張が少なく、ほとんどエミに同調する形でこのグループにいる。小学生のときからエミとずっと一緒だというが、正直エマには理解ができない。"何でも同じ"は息が詰まるだろうに、リンはすべて受け入れてつるんでいるらしい。とはいえ、自分の立ち位置を失いたくないエマがエミに不満を覚えつつもこのグループから抜け出せないでいることと同じだ。エマも独りになるのは怖い。
「別にいいよ、あれは私がしたくてしたことだから」
「うん……ありがとう」
「それより早く行った方ほうがいいんじゃない? エミに見つかったらマズいでしょ」
「ごめんね」
「いいって」
だって、私も同じだから。立場が変わればきっと自分も同じことをする。そんな自分が嫌でたまらないくせに、独りになる勇気もない。結局、エマだって変わらないのだ。だからエマからリンに言えることは何もない。
リンが先に教室へ入っていったのを見届けたあと、少し間をあけてからエマも入る。ちらっと後ろ側の席に目を向ける。その人がいつもの姿勢で寝ていることに気づいて、自分の席へ歩きながらそちらを盗み見る。今日は、来てるんだ……。
ポートガスが机に突っ伏していた。しわくちゃになった黒髪しか見えない。そもそもこの人が学校で起きて喋っているところを見たことがない。席に着いたらすぐ寝て、昼休みになったらどこかへ消えて、午後の授業には戻ってくるがやっぱり寝て、帰りのホームルームが終わるとそそくさと教室を出ていく。
あの日、河原で見た三人組の一人はポートガスで間違いない。ギターを嗜んでいることは意外だったが、どうにも他校の人間と喧嘩して周りから恐れられているというのはあの姿を見たあとではそう思えなかった。確かに、顔や腕に絆創膏をつけていた日もあったような気がするけれど。学校に来ないで、何をしているのか。一度気になってしまえば確かめられずにはいられなかった。
昼休みになると、全学年が一斉に動き出すので校内は騒がしくなる。小中学校と違って、全員がクラスにそろって一緒に食べるという習慣がないのでその辺は自由だ。食堂が一番混み合うのも高校らしく、メニューが豊富で人気である。
しかしエマが向かった先は人ごみから遠ざかった東校舎だった。そもそも東校舎はスピーキングやリスニングといった英語に関する授業のとき以外はほぼ使わないので立ち入る機会も少ない。あとは怪しい文化系の部室が立ち並ぶので、エマには縁遠いところなのだ。
四限目の終わりを告げたチャイムが鳴ると同時に、むくっと起きたポートガスの後を追ってやってきたはいいものの、なぜここにという疑問が生まれる。人ごみを避けるにしても他にあるだろう。基本的に屋上は開放されていないから、その手前の踊り場に――
「おっせーぞ、サボ」
「仕方ねェだろ? 化学の変態教師が実験の説明で悦に入って延びたんだ。ところでルフィがいないみてェだが」
「一緒じゃねェのか? おれは知らねェ。そもそもあいつは一年だ、おれたちよりここに来るの大変だろ」
廊下の影に隠れながらちらちら様子を見守っていると、下から別の人間がやって来た。サボと呼ばれたその人は綺麗な金髪に、すらっとした体型。制服のシャツは腕をまくっていて、下も暑いのか裾を数回折っているらしくくるぶしが見える。
とそこで、あれ?という既視感を覚えた。あの金色、どこかで……でもどこだっけ。考えているうちに、バタバタと慌ただしい音が聞こえてきた。何事だと思ったのも束の間、今度は黒髪の男が階段を駆け上がってくる姿が見えた。おーいお前らァと元気よく手を振っている表情は、少年らしさの残る柔らかい笑顔だった。どうやら彼が残りのルフィというらしい。
「ルフィ早くしろ、今日はゴールデンウィーク中の練習予定を確認するぞ」
「いいけどよ、ところであいつ誰だ?」
「あいつ?」
「あいつ」と、ルフィが指差す方向――エマに残りの二人の視線が集まる。げっ、気づかれてたの? とぼけているように見えて視野は広いのか、悪気は一切ない純粋な目を向けてくる後輩くん。それに比べて誰だこいつはと驚愕するサボ、なんでお前がという不機嫌なポートガスの視線には耐えられず、エマは諦めて三人の前に仕方なく姿を現すことにした。
「あはは。えーっと……友達を探しに来たんだけど、ここにはいなかったみたいですっ……すいません、じゃあ!」
六つの目に居たたまれなくなったエマは誰が信じるかという言い訳を残してその場から逃げた。特にポートガス、怖すぎる。敵でも見ているような、河原で演奏していたときの和やかな雰囲気はどこに置いてきたのかと問いたい。まるで別人である。
しかしわかったこともあった。あの日ポートガスと一緒にいた二人は、さっきのサボとルフィという男子だ。どんな繋がりがあるのか知らないが、ますます興味が湧いてしまったエマは三人が奏でる音楽を想像して胸が熱くなるのを感じた。