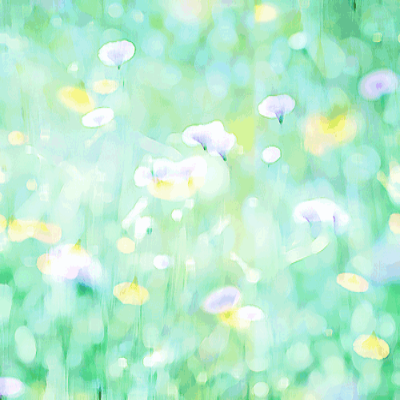
あの子と一緒にしないで
本来、部活がない日はエミたちとどこかに寄ってから帰るのが定番の過ごし方だった。それは町中を歩くだけだったり、カフェだったり、少し前にできたばかりの商業施設だったり、あるいはカラオケとかいろいろ。高校生だからお金を使わないことのほうが多いが、四人で楽しくやっていた。時々、エミとリカは彼氏と予定があるとかでいないこともあった。
本屋で時間を潰そうと考えて、エマの足に待ったがかかる。町中を歩けばエミたちと遭遇する可能性があった。会ったからどうということにはならないだろうが、浮かぶのは先ほどの倫理の授業でのこと。エマがノートに詩を書いていることは彼女たちもあのとき初めて知ったはずだ。それを聞いてどう思っただろう。いまどきポエムなんて流行らないとか言いそうだ。
エミたちの興味といえば、アイドル音楽、コスメ、流行っている映画、食べ物に飲み物、それから彼氏。だけれど、エマが本当に興味あるのはそんなありきたりなものじゃない。
たとえばマキノ先生に教えてもらった『車輪の下』。あの物語の主人公ハンスは将来有望だったにもかかわらず、本当にそれでいいのかと疑問を持ったために社会から見放される救いのない話だ。この世界は社会不適合者にやさしくない。すぐに変だなんだと決めつけて型から外れた人間だとレッテルを貼る。もしかしたら自分が違うのかもしれないとは思わない。そう、エマの母親のように。
たとえばクローゼットの中に隠された一つの箱。エマが密かに集めているCDは、母やエミたちが好きな流行りの音楽ではない。全然聴いたこともないようなインディーズバンドのものだ。そしてその下にはさらに長方形の紙きれたち。"TEU"という殴り書きしたみたいな、読みにくいロゴが印字されているそれは高校入学してから通うようになった地下のライブハウスのもの。エマが誰にも言っていない趣味であり、両親にも秘密で通っている。高校生が地下のライブハウスに一人で出入りしているなんて知ったら、きっと母は卒倒してしまう。普通のライブと違ってチケットが安いというのも高校生のエマにとってありがたい。
というようにして、エマは自分があの子たちとは違うとはっきり自覚するようになったのは高校一年の夏休みが明けてからだった。
現在高校二年になって二週間と少し。
世の中には中二病なんて言葉があるらしい。思春期にありがちな背伸びした言動や態度。自己について、死について考えたり、人と異なるものを好んだり。総合的判断をすれば、きっと中島エマは中二病だ。私はあの子たちのようにはならない、なりたくない。そんなふうに思っている。
結局、時々ひとりになりたいときに来ている河原で時間を潰すことにした。借りてきた本もあることだし、夕飯までいても問題ないだろう。
エマの住む町の近くにある河原には、トレーニングする人たちや学校帰りにサッカーや野球をする小学生たちで溢れている。エマのように読書をしたり、草の地面に体を預けて日向ぼっこをする人間は珍しい。しかし、今日はそれ以上に珍しい先客がいることに気づいて瞠目した。
野球をする小学生たちからだいぶ離れたところに三人組の男がいたのだ。制服を着ていることから学生であることは間違いないが、驚いたのはそれがエマの通う高校のものだった。あまり近づきすぎると気づかれる可能性があるので、ある程度の距離を保ったままその三人組を見つめる。
後ろ姿なのでここからでは顔がわからなかった。けれど何をしているかはかろうじてわかる。
彼らは楽器を持っていた。あれは、ギターとベース。エマがライブハウスでよく見る楽器。それを持っている高校生がいるなんて――いや、高校生だったら軽音部があるから珍しくないのだろうが、エマの通う学校にはないのである。
しばらくその光景にぼうっとしていると、突然ジャーンというあのお腹に響くような音がエマの聴覚を刺激した。あ、と思ったときには三人が演奏を始めていた。マイクはセットしていないのか声は聞こえないけれど、音は確実にエマに届いている。体の芯から震える。神聖なものを見るような目で彼らを凝視していると、三人のうちの一人が知り合いであることに気づいた。
「あれは、ポートガス……? と誰だろう」
呟いて再び彼らの様子を見守った。それからたぶん一時間半くらいだろうか、数曲(どれも知らない曲ばかりでもしかしたらオリジナルなのかもしれない)練習していったあと、三人は楽器をケースにしまい込んで河原を後にした。
カモフラージュとして本を開いていたエマは、けれど集中できないまま空の色が変わるまでその場に佇んでいた。