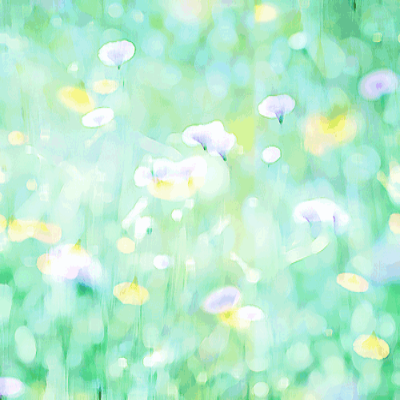
ユートピアはどこにある?
シマモトから反感を買ったとすれば、二年になって三回目の数学の授業だろう。
問題集を解いて答え合わせをする。数学じゃ当たり前に行われるその流れはシマモトの授業でも同じで、五分間は自力で考えてそのあと適当にあてて黒板で解かせる。しかし、シマモトの授業の嫌なところは明らかにわからないと主張している人間に解かせて恥をかかせるところにあった。五十代の半ばも過ぎて、さらにねちねちしてきたオジサン先生。
噂には聞いていたが、質が悪い。その日、前回の続きの単元で発展問題に取り組んでいたエマたちは五分後にシマモトから指名を受けて黒板に出てきて解答した。見た目から驚かれることもある(数学が得意な見た目というのもよくわからない)のだが、エマはこれでも数学が得意なほうだ。あと二人指名されたのち、一人は数学を苦手とするリンだった。ちらっと彼女のノートを見た感じ、途中式どころか最初の段階で違うアプローチをしているように思う。それでは回答にたどり着けないだろう。
三人のうち二人が解き終わったのを見て慌てだしたリンを見兼ねて、エマは声をかけようとした。
「なんだ三島。一昨日やったばかりのことがわからんのか? 発展といっても考え方は基礎的なこと、そんなのもわからんようじゃ受験はどうする」
エマより先に声をかけたのは、後ろで様子を見ていたシマモトだった。ニタニタと気持ち悪い笑みを浮かべている。もしかして絶対にわからないとふんでリンを指名したのだろうか。だとしたら性格が悪い。大体、高校二年になったばかりのエマたちに受験をつきつけるとは進学校でもあるまいし早すぎる。
案の定、黒板の真ん中で凝り固まったリンは口をぱくぱくさせ、右手のチョークが中途半端なところで止まったままになっている。クラスの雰囲気が悪くなる前にどうにかしないと。
「そういうシマモト先生は、ここの漢字が間違っています」
心臓がばくばくとうるさかった。目の奥が熱い。目を見開くリンとクラスの視線を一気に集める。目立つようなことをしたいわけじゃないけれど、リンのためには仕方ない。
実際に黒板の左端に書かれた説明文には漢字表記のミスがあった。誰も指摘しなかったのは全員が脳内で補完できたからだし、いちいち指摘するほどのことでもないと判断したからで、シマモトがあんなことを言わなければそのままでいられたのに。
シマモトは「え?」と訳が分かっていない間抜けな顔でエマを見た。リンをはずかしめているはずが、急に自分に火の粉が飛んできて驚いているようだ。形勢が逆転したとばかりに、男子たちが「そうですよ」「つーか先生、この前も漢字ミスあったんですけど」など次々にシマモトを窮地に追いやっていく。
「それはっ……」
「先生、私この問題わかりません!」
今度はリンが叫ぶように言い切った。ひな壇を蹴るようにして降りた彼女はそのまま自分の席へ戻っていく。呆気にとられたシマモトといえば、魂の抜けた頼りない「そうか」とだけ呟いてとぼとぼ黒板まで歩いていった。それから答え合わせと授業は順調に進んでいるかのように見受けられたが、心なしかシマモトの恨みがましい視線がエマに降り注いでいる気がして、板書して背中を向けているとき以外は顔を上げられたかった。
倫理の時間にエマが内職――といっても勉強しているわけではないが、していることは誰にも言っていない。もちろんエミたちにでさえ。だから誰一人として知るはずのないことだった。それがなぜかシマモトに知られているということで思い当たるのは、一度だけ自習になったときだ。シャーリー先生が家庭の事情でその日いなかったので、空き時間だったシマモトが監督として来たのだ。見られたとしたらそのときである。エマとしてはまさか見られているとは思いもしなかったが。
逆恨みのつもりだろうか。シマモトへの怒りがずっとくすぶっている。屈辱的な気分で残りの時間を過ごしたエマは帰りのホームルームが終わると同時に教室を出た。部活はなくても、どのみちエミたちとは一緒に帰れないから問題ない。
かといって家にも帰る気が起きなかったエマは自然と昇降口のすぐ隣に設置されている図書室へ向かっていた。鞄に読み終わった本があったのを思い出したのだ。
一年のときから何かと世話になっているエマは常連客だった。ガラス張りの扉を引いて中ヘ入る。紙の匂いが充満するこの空間がエマは好きだ。あくせくと動き回る人間がいる学校の中で、唯一時の流れが遅く感じられる場所のような気がしている。
入ってすぐのカウンターに司書のマキノ先生が座って本を読んでいた。マキノ先生は優しくて本の知識も豊富で、エマが懐く教師の一人。エマの知らないことをたくさん知っている。
「マキノ先生っ! これ面白かったです、また何かおすすめありますか」
取り出したのはヘッセの『車輪の下』の文庫本。主人公のハンスは天才児と呼ばれていたが、勉強ばかりしている自分の人生に疑問をもち次第に堕落していくという決して明るいストーリーではない。社会の軋轢に埋もれていくハンスが、けれどエマの心と妙にシンクロして、気づけばページをめくる手がとまらなかった。
「よかった。エマは最近難しいものばかり読んでるみたいだから」
「うん、ちょっと興味があって……」
「そうねえ、じゃあこれなんかどう?」
書架のほうに移動したマキノ先生は聞いたことのない作者の本を抜き出してみせた。首を傾げるエマにやさしく微笑んで「これはね」と説明する。
「オスカー・ワイルドの『ドリアン・グレイの肖像』という小説。とても美しい青年が卑劣な行為を繰り返していくことで肖像が老いていくの」
あらすじを聞いてもあまりわからなかったのが伝わってしまったらしく、マキノ先生は苦笑して読めばきっとわかると慰めてくれた。ありがとうございます、と礼を言いつつ貸出手続きをしてもらうと居座る気分でもなかったエマは図書室を飛び出した。
こちら側から見れば扉は押す形になるのだが、目の前を人が横切ったのとエマが扉を開けたタイミングが偶然重なってしまった。
――どんっ!
扉が思いきり人に当たり、その拍子でエマは扉の取っ手に額をぶつけた。鈍い痛みがじわじわと迫ってくる。額を擦りながら、扉の向こうにいる人に視線を向けた。
「おっと、悪ィ。急いでるんだ」
向こうも多少ダメージを受けたはずなのだが、意に介したふうもなく急いでいるからと走っていってしまう。背の高い金色の髪が特徴的な男だった。すぐに下駄箱の影へ消えたためにそれ以外のことはわからない。しかしエマも別に気にすることではないと、そのまま同じようにして二年の下駄箱へ向かったのだった。